印刷業界で使われる連量の意味 厚さや重さとの関係を徹底解説
2025.09.24
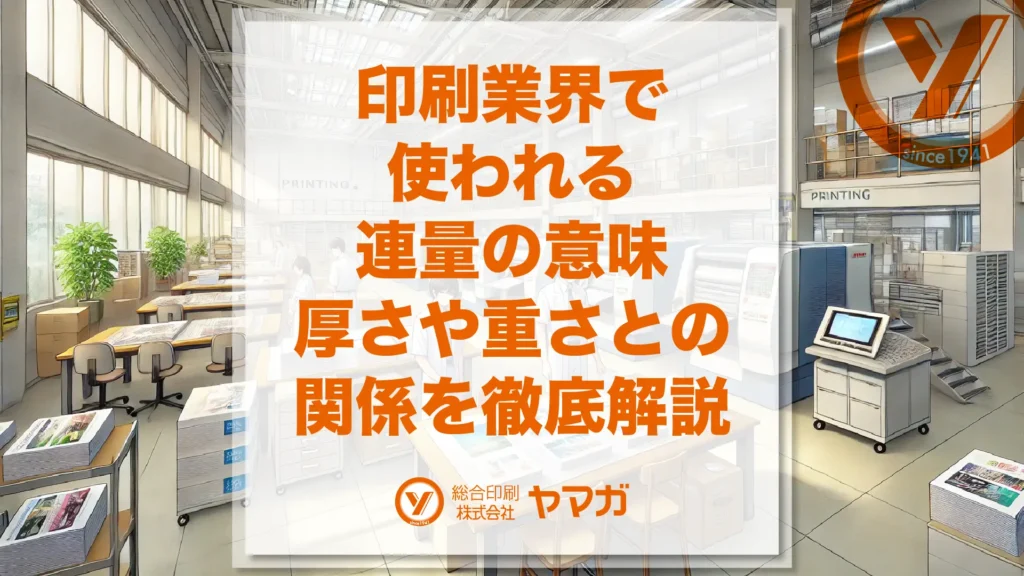
印刷物を制作するとき、デザインや色味に目が向きがちですが、実は紙そのものの選び方が仕上がりを大きく左右します。その中でも「連量」という指標は、紙選びの基礎ともいえる大切な要素です。連量とは、ある基準寸法の紙を1,000枚積み重ねたときの重さをキログラムで表したもので、数字が小さいほど薄く軽く、大きいほど厚く重くなります。この数値は単なる重さの情報ではなく、紙の厚みや質感、耐久性、印刷の発色や加工のしやすさなどにも直結します。
例えば、軽い連量の紙は大量配布や郵送物に適しており、コスト面や取り扱いやすさに優れていますが、耐久性や高級感の面ではやや劣ります。反対に高い連量の紙は厚みと重量感があり、存在感や高品質な印象を与えますが、加工や輸送の負担、コストの増加といった課題も伴います。このように、連量の選び方ひとつで、印刷物の機能性や印象が大きく変わるのです。
また、同じ連量でも紙の基準寸法が違えば、1枚あたりの厚みや重さが異なります。代表的な基準寸法には四六判や菊判があり、四六判のほうが面積が大きいため、同じ連量でも薄く感じられることがあります。さらに、コート紙やマットコート紙、上質紙といった紙の種類によっても手触りや印刷適性が変わり、同じ数値でも仕上がりの印象が全く異なります。
実務の現場では、こうした連量の特性を踏まえて用途ごとの選択基準を設け、サンプルや試し刷りを活用して仕上がりや加工適性を確認することが重要です。例えば、社内で「会社案内はマットコート110kg」「DMハガキはコート180kg」といった基準を共有すれば、品質のばらつきを防ぎやすくなります。また、保管環境にも注意が必要で、湿度や温度の影響によって紙の状態が変化し、印刷の安定性に影響を与えることもあります。
さらに、連量はコストや納期にも影響します。厚い紙は材料費や加工費、輸送費が増え、納期が延びる可能性があります。逆に薄い紙は軽く加工しやすいものの、耐久性や高級感を求める場面には不向きです。こうした特徴を理解し、予算や納期、目的に合わせて最適な連量を選ぶことが、完成度の高い印刷物を作るためのポイントとなります。
連量は、一見すると数字だけのシンプルな指標に思えますが、その背景には印刷物の品質や機能性を左右する多くの要素が隠れています。この知識を活かすことで、見た目も手触りも、使い勝手までも考慮された満足度の高い仕上がりを実現できるでしょう。
連量とは何か印刷用紙の厚さや重さを理解するための基本説明
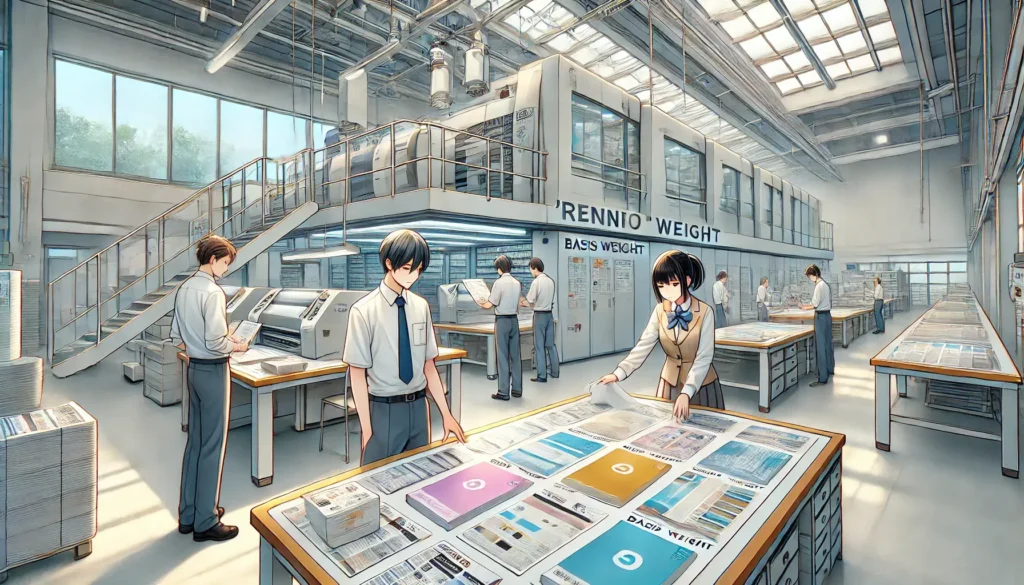
印刷の世界で頻繁に耳にする「連量」という言葉は、印刷物を扱う方やデザインに関わる方にとって欠かせない知識です。しかし、初めて聞く方にとっては少し専門的で、イメージが掴みにくい用語かもしれません。連量とは、ある決められた寸法の紙を1,000枚積み重ねたときの重さを示すもので、この1,000枚の束を「1連(1R)」と呼びます。単位はキログラムで表され、例えば「コート90kg」と表記されている場合、その紙を規定サイズで1,000枚積むと重さが90kgになるという意味です。この数字が小さいほど紙は薄く軽くなり、数字が大きいほど厚く重くなります。
この連量の概念を理解することで、印刷物の用途に合わせた適切な紙選びができるようになります。例えば、チラシやフライヤーのように大量に配布するものは軽く薄い紙が好まれることが多く、冊子やパンフレットなどの保存性や高級感を重視する場合は厚く重い紙が選ばれる傾向があります。連量の数値は単なる重さの指標ではなく、紙の質感や耐久性、印刷の仕上がりにも密接に関わっているため、印刷物を作る際の基礎知識としてしっかり理解しておくことが大切です。
また、連量は紙の種類や元の寸法によって同じ数値でも厚みや手触りが異なる場合があります。例えば「コート紙90kg」と「上質紙90kg」では、同じ連量でも厚みやしなやかさが違うため、印刷後の見え方や手触りに差が出ます。これは紙の製造方法や表面加工の有無によって性質が変わるためで、単純に数字だけを見て選ぶのではなく、実際にサンプルを触って確認することが望ましいです。特に高品質な印刷物やブランドイメージを大切にする印刷物では、この微妙な差が仕上がりの印象に大きく影響します。
連量を正しく理解するには、まず「四六判」や「菊判」といった基準寸法の知識も必要になります。四六判は788mm×1,091mm、菊判は636mm×939mmといった具合に、規定の寸法が決まっており、このサイズでの1,000枚分の重さが連量として表示されます。つまり、連量90kgの四六判と同じ連量90kgの菊判では、紙1枚あたりの厚さや重さが異なるということです。これを知らないまま連量だけを比較すると、意図した厚みや質感と違う紙を選んでしまうことがあるため注意が必要です。
また、連量は印刷機や加工のしやすさにも関係してきます。薄い紙は折りやすく軽いため郵送コストを抑えることができますが、逆に厚い紙はしっかりとした質感が出せる反面、折加工や断裁の際に負荷がかかりやすく、印刷機の設定や取り扱いに注意が必要になります。これらの点からも、連量は単なる重さの情報以上に、印刷物の機能性やコスト、仕上がりの印象を左右する大切な要素だと言えるのです。
さらに、業界によっては「斤量(きんりょう)」という表現が使われることもあります。意味は連量と同じですが、表現の仕方が異なるだけです。このように呼び方や表示方法が変わる場合があるため、発注や打ち合わせの際にはどの基準で話しているのかをしっかり確認することが、誤発注や認識違いを防ぐために役立ちます。
実際に印刷物を企画する場面では、デザインの内容や使用する写真、印刷方式によっても適した連量が変わってきます。たとえば、フルカラー印刷で発色を鮮やかに見せたい場合は、表面が滑らかでインクの乗りが良いコート紙を選び、その中で連量を調整することで理想の仕上がりを実現できます。一方、文字主体の冊子やナチュラルな印象を与えたい印刷物では、上質紙やマット紙のやや軽めの連量を選ぶことで、読みやすさと手触りの心地よさを両立できます。
このように、連量は印刷業界の専門的な用語ではありますが、理解してしまえば紙選びの大きな助けになります。特に企業で印刷物を発注する立場の方にとっては、予算管理や仕上がりの品質、配送コストなどに直結するため、ぜひ押さえておきたいポイントです。今後、印刷物の制作や発注に関わる際には、この連量という指標を意識しながら選定することで、より満足度の高い成果物を得られるでしょう。
連量の計算方法と1連1,000枚あたりの重さの考え方
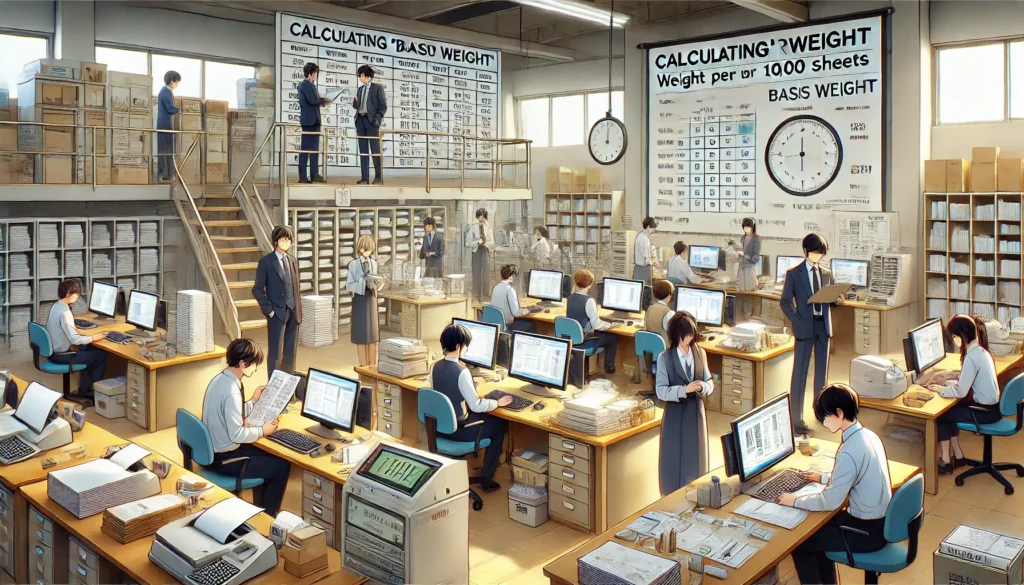
連量という言葉を正しく理解するためには、その計算方法と基本的な考え方を押さえておくことが大切です。連量は、特定の基準サイズの紙を1,000枚積み重ねたときの重さをキログラム単位で表したものです。この「1,000枚」という単位は、印刷業界で昔から使われている単位であり、これを1連(いちれん)または1Rと呼びます。例えば「コート90kg」と書かれていれば、その紙を規定サイズで1,000枚集めると重さが90kgになるという意味です。
計算の基本はシンプルですが、注意しなければならない点があります。紙には四六判や菊判など、あらかじめ決められた元の寸法があり、この基準サイズが変わると同じ連量でも紙1枚あたりの厚さや重さが変わります。四六判は788mm×1,091mm、菊判は636mm×939mmが一般的な寸法です。たとえば、四六判90kgと菊判90kgは数字が同じでも、面積が異なるため、1枚の重さや厚さは一致しません。四六判の方が面積が大きい分、1枚あたりの厚みは薄く感じられることがあります。
この仕組みを理解すると、連量の計算方法がより明確になります。まず、紙1枚の面積を求め、それを1,000枚分に換算します。そして、その合計重量が連量の数値です。もし四六判サイズの紙1枚の重さが90gであれば、1,000枚で90,000g、つまり90kgとなります。計算自体は単純ですが、実務では製造工程や紙質によって微妙な誤差が出るため、印刷所や紙メーカーが提示する数値を参考にするのが一般的です。
また、実際の印刷物は四六判や菊判をそのまま使うわけではなく、必要な仕上がりサイズに裁断して使います。このため、連量はあくまで「元のサイズ」での重さを示す指標であり、最終的な印刷物の重さや厚さは裁断サイズや紙の加工方法によって変わります。これを理解していないと、「同じ連量なのに仕上がった印刷物の厚さが違う」という誤解を招くことがあります。
さらに、連量の数値は印刷工程やコストにも関係します。例えば、連量が高い紙は厚みがあり重量も増すため、郵送時の送料が上がる可能性があります。逆に軽すぎる紙は、強度や高級感の面で不足する場合があります。そのため、単に計算式を覚えるだけでなく、連量がどのように仕上がりやコストに影響するのかをセットで考えることが大切です。
印刷業界では、こうした連量の考え方をもとに、発注の際に最適な紙を選ぶための基準を持っています。初めて紙を選ぶときには、印刷所に「この用途なら何kgの紙が適していますか」と相談し、サンプルを触って比較するのがおすすめです。計算方法の知識は、そのやり取りをよりスムーズにし、自分の希望を正確に伝えるための大きな助けとなります。
用紙サイズと連量の関係四六判や菊判などの基準寸法について

連量を正しく理解するためには、用紙サイズとの関係を押さえることが欠かせません。連量は「ある基準寸法の紙を1,000枚積んだときの重さ」で表されますが、その基準寸法にはいくつか種類があり、代表的なものが「四六判」と「菊判」です。四六判は788mm×1,091mm、菊判は636mm×939mmという大きさで、これらは印刷業界で長く使われてきた標準サイズです。同じ連量であっても、この基準寸法が異なると紙1枚あたりの面積が変わるため、厚みや重量感が変わってしまいます。
例えば、四六判90kgと菊判90kgでは数字は同じですが、四六判のほうが面積が大きいため、1枚あたりの厚さは相対的に薄く感じられます。一方、菊判は四六判よりも小さいため、同じ連量でもやや厚みがあり、しっかりとした手触りになることが多いです。この違いを理解していないと、同じ数値を見て「同じ紙質だ」と思い込んでしまい、実際の仕上がりに違和感を覚える原因となります。
また、これらの基準寸法は印刷機の規格とも密接に関係しています。印刷会社によっては四六判サイズを前提とした機械を使っている場合もあれば、菊判を標準としている場合もあります。印刷工程の効率や裁断のしやすさは、どの基準寸法を使うかによって変わるため、用紙選びの際には印刷所がどちらの基準を採用しているかを確認することが重要です。
さらに、四六判や菊判のほかにも、A列やB列といった国際規格の用紙サイズがあります。これらは主に事務用や出版物などで使われることが多く、四六判や菊判とは基準が異なります。そのため、A4やB5など最終的な仕上がりサイズだけを見て紙を選ぶと、連量との関係が分かりにくくなることがあります。基準寸法と仕上がりサイズを混同せず、それぞれの関係性を把握しておくことで、より的確な用紙選びができるようになります。
実際の発注現場では、仕上がりサイズと基準寸法の両方を踏まえて紙を選定します。例えば、A4サイズのチラシを作る場合でも、元となる紙は四六判や菊判を大きく使い、その後裁断して仕上げます。このとき、基準寸法ごとの連量を把握していれば、必要な厚みや質感を正確に指定でき、印刷会社とのやり取りもスムーズになります。
このように、用紙サイズと連量は密接に関係しており、基準寸法の違いを理解することが印刷物の品質やコストに直結します。数字だけに頼らず、基準寸法の大きさや用途を意識しながら選ぶことで、仕上がりに満足できる印刷物を作ることができるのです。
連量の数値と紙の厚みや質感が印刷物に与える影響

連量の数値は単なる重さの指標であるだけでなく、紙の厚みや質感、そして印刷物の仕上がりに直接的な影響を与えます。数値が小さいほど紙は薄く軽くなり、逆に大きいほど厚く重くなります。この厚さや重量の差は、見た目や手触り、印刷インクの発色、さらには耐久性にも関係してくるため、印刷物の用途や目的に応じて適切な数値を選ぶことが非常に大切です。
例えば、連量が55kgや64kg程度の軽い紙は、チラシや新聞折込など、大量に配布する印刷物に向いています。薄く軽いため持ち運びがしやすく、郵送や配布のコストを抑えられます。しかし、その分しなやかで折れやすく、耐久性は高くありません。また、光沢や色の出方にも影響が出やすく、インクが裏移りする場合もあるため、写真や高精細な印刷にはあまり向かないことがあります。
一方で、連量が90kgや110kgの紙は、パンフレットや名刺、ポストカードなど、しっかりとした質感や高級感を求められる印刷物に適しています。厚みが増すことで手に持ったときの安定感があり、めくる際の音や指触りにも存在感が出ます。また、表面が平滑な紙質であればインクがしっかりと乗り、発色も鮮やかになります。ただし、厚くなる分だけ加工や折りが難しくなり、製本や断裁の際には特別な調整が必要になることがあります。
連量の数値は、紙の質感にも大きく影響します。例えば、同じ90kgでもコート紙と上質紙では手触りや印象が異なります。コート紙は表面に塗工が施されているため滑らかで光沢があり、写真やカラー印刷が映える特徴があります。逆に上質紙は塗工がないためナチュラルな風合いで、文字主体の印刷や温かみを演出したい印刷物に向いています。このように、同じ連量でも紙の種類によって得られる仕上がりはまったく違うため、用途に合わせて選ぶ必要があります。
また、紙の厚みは印刷後の取り扱いにも影響します。薄い紙はページ数の多い冊子や大量配布物に向いていますが、厚い紙は単ページや少ない枚数の印刷物に適しています。例えば、DMハガキに薄い紙を使うと郵送中に折れやすく、受け取った際の印象も弱くなります。反対に、パンフレットやカタログに厚すぎる紙を使うと重量が増し、持ち歩きにくくなるだけでなく、印刷コストや送料も上がる可能性があります。
さらに、連量は印刷物の耐久性や保存性にも関係します。高い連量の紙はしっかりとした構造を持ち、長期保存や繰り返しの使用に耐えることができます。そのため、重要な資料や記念品として長期間保管される印刷物には、ある程度の連量を持たせることが望まれます。一方、短期間で役目を終える印刷物には軽い連量を選ぶことで、無駄なコストを削減できます。
このように、連量の数値は紙の厚さや重さだけでなく、質感や仕上がり、使用感までも左右します。印刷物をどのように使いたいのか、どんな印象を与えたいのかを明確にしてから連量を選ぶことで、完成度の高い仕上がりが実現できるのです。
コート紙や上質紙など紙の種類ごとの連量の特徴と使い分け

印刷用紙にはさまざまな種類があり、それぞれの紙には連量による特徴や適した使い方があります。同じ連量でも紙の種類によって厚みや質感が異なるため、用途や目的に応じた選び分けが大切です。ここでは代表的な紙の種類として、コート紙、マットコート紙、上質紙の特徴と、連量の違いによる使い分けについて詳しく解説します。
まず、コート紙は表面に塗工を施し滑らかに加工された紙で、光沢があり発色が鮮やかになるのが特徴です。写真やカラー印刷を美しく見せるために適しており、パンフレットやポスター、チラシなどによく使われます。例えばコート90kgなら適度な厚みと高級感を両立でき、折加工もしやすいため幅広い用途に対応します。一方でコート135kgなどの高い連量は、ポストカードや高級感のあるパンフレットに用いられ、しっかりとした質感と存在感を与えます。ただし厚くなるほど折りにくくなり、冊子のページ数が多い場合は製本が難しくなるため注意が必要です。
次に、マットコート紙はコート紙と同様に塗工されていますが、表面が光沢を抑えた仕上がりになっており、落ち着いた印象を与えます。反射を抑えることで文字が読みやすく、上品な質感を演出できるため、カタログや冊子、企業案内などに向いています。例えばマットコート110kgはしっかりとした厚みを持ちつつも手触りが柔らかく、読み物としての冊子や高級感のある配布資料に最適です。連量が低めの70kgや90kgであれば軽くめくりやすく、大量ページの冊子や雑誌にも向いています。
上質紙は塗工を施していないため、紙そのものの繊維感やナチュラルな風合いが感じられます。筆記性が高く、鉛筆やボールペンでの書き込みがしやすいのが特徴で、申込書やアンケート用紙、社内資料などにも多く使用されます。例えば上質紙70kgは軽量で扱いやすく、配布資料やページ数の多い冊子に向いています。一方、上質紙110kgはしっかりとした厚みがあり、案内状や冊子の表紙など、耐久性や質感を重視する場面に適しています。
同じ連量でも、紙質によって厚みの感じ方や印刷の見え方が変わります。コート紙は連量が低くても発色が良く高級感があり、上質紙は同じ連量でもやや厚く感じる場合があります。これは表面加工や紙の繊維密度による違いで、実際にサンプルを手に取って比較することでより適切な選択が可能になります。
また、用途に応じた使い分けも重要です。例えばDMハガキであればコート紙やマットコート紙の高い連量を使うことで耐久性と高級感を確保できます。逆に配布用のフライヤーや社内資料では、軽い連量の上質紙を使うことでコストを抑えつつも機能性を保てます。連量と紙質の組み合わせを工夫することで、印刷物の目的や使い勝手、受け取った人への印象を大きく変えることができます。
このように、連量の数値は紙の種類ごとにその意味合いが変わり、印刷物の完成度や効果に直結します。紙の質感や用途を理解したうえで最適な組み合わせを選ぶことが、印刷物の価値を最大限に引き出すポイントとなるのです。
連量を確認する際に役立つ印刷現場でのチェックポイント

印刷物を作る際、連量の確認は仕上がりや品質を左右する重要な工程のひとつです。数値だけで判断するのではなく、実際の紙を手に取り、質感や厚みを確かめることが欠かせません。印刷現場では、こうした確認を行うためのポイントがいくつかあります。これらを押さえておくと、紙選びの精度が上がり、発注後のトラブルを防ぐことができます。
まず大切なのは、サンプルの現物を確認することです。印刷会社や紙の仕入れ先では、実際に使用する予定の連量と紙種で作られた見本帳やサンプルを用意している場合がほとんどです。手に取ってみると、数字上は同じ連量でも紙種によって厚みやしなやかさが異なることがよくわかります。さらに光にかざして透け具合を見れば、印刷物の裏写りの可能性や紙の密度をイメージしやすくなります。
次に注目すべきは、印刷後の発色やインクの乗り具合です。同じ連量の紙でも、表面加工や紙質によって色の再現性や発色の鮮やかさは変わります。コート紙なら光沢感が強く写真が映えますが、上質紙では落ち着いた色合いになり、マットコート紙は反射を抑えつつもある程度の鮮やかさを保てます。試し刷りを行い、実際のデザインや写真がどのように見えるかを確認しておくことは、完成後の満足度を大きく左右します。
また、印刷後の加工適性も重要なチェックポイントです。折り加工や断裁、製本といった工程で紙がどのような状態になるかは、連量によって変わります。軽い連量の紙は折りやすく加工しやすい反面、耐久性が低く、角が折れやすい傾向があります。逆に高い連量の紙は丈夫ですが、厚みがあるため折る際にひび割れが起きやすくなります。このため、実際に加工してみて問題がないかを事前に確認することが求められます。
さらに、用途に応じた適正な連量かどうかも判断基準になります。たとえば郵送する印刷物の場合、連量が高すぎると重量が増して送料が高くなりますし、逆に軽すぎると輸送中に折れやすく、到着時の印象を損ねることがあります。印刷現場では、こうした使用シーンや輸送条件も含めて連量を提案することが多く、発注側もその背景を理解しておくと、よりスムーズなやり取りができます。
最後に、複数の候補を比較することが大切です。一つの連量や紙種だけで決めるのではなく、用途や予算に合わせて数種類を比べることで、理想に近い選択がしやすくなります。実際に紙を触り、印刷してみて、加工した状態を見比べることで、数字やスペック表だけではわからない違いを感じ取ることができます。
このように、連量の確認は単なる数値チェックではなく、実際の紙質・印刷適性・加工適性を総合的に見極める作業です。これらのポイントを押さえておくことで、印刷物の完成度を高め、期待通りの仕上がりを実現できるでしょう。
用途別に最適な連量を選ぶための判断基準と注意点

印刷物は用途によって求められる特性が大きく異なります。そのため、連量を選ぶときには、見た目や手触りだけでなく、使用目的や流通方法、保管期間などの条件を総合的に考慮することが重要です。同じデザインでも、チラシ、パンフレット、ポストカードなどでは適切な連量が変わり、最終的な印象や効果にも差が出ます。ここでは代表的な用途ごとに、選び方の基準と注意点を詳しく解説します。
大量配布するチラシやフライヤーでは、軽めの連量が選ばれることが多いです。55kgや64kg程度の軽い紙であれば印刷・裁断の作業がスムーズで、持ち運びや郵送時のコストも抑えられます。ただし、薄すぎる紙は透けやすく、両面印刷では裏面のデザインが見えてしまう場合があるため、写真や濃い色の多いレイアウトでは注意が必要です。
パンフレットやカタログのように保存性や高級感を求める場合は、90kg以上のしっかりとした紙を選ぶのが一般的です。適度な厚みがあることで手に取ったときの存在感が増し、ページをめくる際の印象も良くなります。ただし、ページ数が多くなる場合は、あまりに高い連量を選ぶと冊子全体が重くなり、開きにくくなるため、全体の構成とバランスを考えながら決めることが必要です。
ポストカードやDMハガキなど、直接手に取って見る印刷物はさらに高い連量が適しています。135kg以上の厚みがあれば、郵送中に折れたり曲がったりしにくく、受け取った人にしっかりとした印象を与えることができます。ただし、厚すぎると郵便料金が変わる場合や、一部の印刷機で取り扱いが難しくなる場合があるため、事前に郵便規格や印刷所の対応範囲を確認しておくことが大切です。
また、用途別の選び方では、デザインの内容や印刷方法も影響します。写真やカラー面が多い場合は、連量とともに紙の表面加工を意識することで仕上がりが変わります。コート紙やマットコート紙は発色を良くするために選ばれることが多く、軽い連量でも見栄えを高めることが可能です。逆に、文字主体で読みやすさを重視する印刷物では、上質紙の中程度の連量を選び、反射を抑えることで目の疲れを軽減できます。
注意点として、連量はコストや納期にも関わります。厚い紙は単価が高くなるだけでなく、印刷・加工・輸送のすべての工程で負担が増えます。特に大量印刷の場合、この差は全体の費用に大きく影響するため、予算とのバランスを見ながら選ぶ必要があります。また、薄い紙は低コストですが、印刷後の耐久性や高級感が不足しやすく、場合によっては目的を果たせない可能性があります。
用途に合わせて最適な連量を選ぶためには、まず完成した印刷物がどのように使われるのかを明確にし、それに基づいて厚みや質感、コストを比較検討することが欠かせません。この判断プロセスを意識することで、見た目と機能の両方を満たす印刷物を作り上げることができるでしょう。
連量の違いによるコストや印刷工程への影響

連量の違いは、印刷物の見た目や手触りだけでなく、コストや印刷工程そのものにも大きな影響を及ぼします。紙の厚みや重さは、材料費、加工のしやすさ、輸送コスト、納期のすべてに関係しており、用途や予算に合わせた適切な選択が求められます。ここでは、連量の差がどのようにコストや工程に反映されるのかを詳しく解説します。
まず、最も分かりやすいのは材料費への影響です。連量が高い紙は1枚あたりの重量が増えるため、同じ枚数を印刷する場合でも必要な紙の総重量が大きくなり、その分原材料費が高くなります。特に大量印刷では、この差が積み重なって全体の予算に大きく影響します。例えば、10,000枚規模のチラシでも、連量を64kgから90kgに上げるだけで、材料費が数万円単位で変わることがあります。
次に、印刷工程への影響です。厚い紙は印刷機への負荷が大きくなり、給紙や排紙の速度を落とす必要がある場合があります。また、厚さに応じて印刷機の設定を調整しなければならず、場合によっては対応できる連量の範囲が決まっている機械もあります。逆に薄い紙は印刷機の通紙性が高くスムーズに進みますが、軽すぎると紙詰まりやシワが発生しやすくなるため、注意が必要です。
加工工程にも連量の影響は及びます。例えば折り加工では、厚い紙は折り線にひび割れが出やすく、スジ入れ加工が必須となる場合があります。また、製本では高い連量の紙を使うと冊子全体が厚くなり、背表紙の幅や綴じ方の選択肢にも影響します。断裁作業では、厚い紙は刃の摩耗が早く進み、加工スピードを落とさざるを得ないこともあります。
さらに、輸送コストへの影響も無視できません。連量が高くなると1枚あたりの重さが増すため、同じ部数でも総重量が大きくなります。特に郵送物では、重量の区分によって料金が変わるため、連量の選択次第で送料が数十%変わることもあります。例えば、DMハガキを郵送する際、連量を上げすぎると郵便規格の重量制限を超えてしまい、送料が上がる可能性があります。
納期にも間接的な影響があります。厚い紙は加工や仕上げに時間がかかるため、同じ部数でも納品までの日数が延びることがあります。特に短納期案件では、厚すぎる紙や特殊加工が必要な連量を選んでしまうとスケジュールに影響が出る可能性があります。一方、薄めの連量は加工や輸送が比較的スムーズで、納期短縮につながることが多いです。
このように、連量の違いは単なる見た目や触感の変化だけでなく、印刷の全プロセスに関わる重要な要素です。コスト、加工性、輸送、納期など多方面への影響を踏まえて連量を選ぶことで、予算内で効率よく、かつ目的に合った印刷物を作ることが可能になります。数字だけでなく、制作全体の流れとバランスを見ながら決定することが、満足度の高い仕上がりへの近道となります。
実務で役立つ連量の知識印刷品質を安定させるための工夫
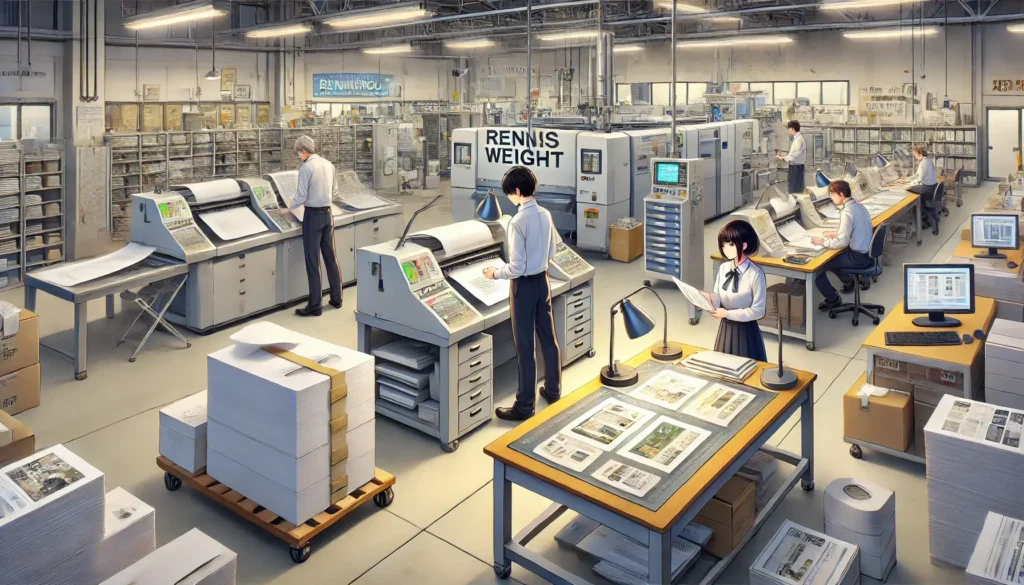
印刷物の品質を安定させるためには、デザインや印刷機の性能だけでなく、紙の連量に関する知識が欠かせません。特に実務の現場では、連量の選び方や扱い方が仕上がりの均一性や耐久性に直結します。ここでは、日々の印刷業務や発注の場面で役立つ具体的な知識と工夫について詳しくお伝えします。
まず大切なのは、紙の保管環境です。紙は湿度や温度の影響を受けやすく、連量が同じでも保管状態によって厚みや質感が変化することがあります。湿度が高い場所に長時間置かれた紙は水分を含んで膨らみ、印刷時に紙送りが不安定になる場合があります。逆に乾燥しすぎると静電気が発生しやすくなり、給紙不良や色ムラの原因となります。印刷現場では、紙を使う前に室温と湿度を安定させた環境に置き、必要に応じて調湿を行うことが品質維持に役立ちます。
次に重要なのは、用途ごとの連量の基準を社内で共有しておくことです。例えば社内マニュアルや仕様書に「会社案内パンフレットはマットコート110kg」「DMハガキはコート180kg」などと明記しておくと、発注時の迷いが減り、品質のバラつきも防げます。また、同じ連量でもメーカーやロットによって微妙な差が出ることがあるため、実際にサンプルを確認してから大量発注することが望ましいです。
さらに、印刷工程においては紙の厚みと機械設定の調整が欠かせません。特に高い連量の紙を使う場合は、印刷機の給紙圧やインク量、乾燥時間を適切に設定する必要があります。厚すぎる紙に通常設定で印刷すると、インクの定着が不十分になったり、乾燥が遅れて裏移りが発生する可能性があります。逆に薄い紙では、インクが染み込みやすく色が沈んでしまうことがあるため、発色を考慮した色補正が求められます。
加工工程でも工夫が必要です。例えば厚みのある紙を折る場合は、折り筋を事前に入れることで割れやひびを防げます。また、冊子製本では高い連量の紙を使うと背が厚くなるため、無理にページ数を増やさない設計や、綴じ方の工夫が必要です。こうした小さな調整が、仕上がりの完成度と使いやすさを高めます。
また、実務の現場ではコスト管理も重要な視点です。高い連量は品質面で有利ですが、材料費や輸送費、加工費が上がるため、全体予算とのバランスを取る必要があります。そのため、最終的な仕上がりの目的を明確にし、必要な部分にだけ高い連量を使うといった柔軟な判断が求められます。例えば表紙には厚い紙を使い、中面は軽めの紙にするなどの組み合わせで、品質とコストの両立が可能です。
こうした連量に関する実務的な知識と工夫は、日々の経験から蓄積されていくものですが、あらかじめ意識して取り組むことで品質の安定化につながります。印刷物は見た目だけでなく、手に取ったときの感覚や耐久性も含めて評価されるため、連量の知識を活かした細やかな調整が長期的な信頼獲得につながるのです。
連量を理解して印刷物の品質と仕上がりを高めるために

印刷物の仕上がりや品質を左右する要素は数多くありますが、その中でも連量はとても重要な指標です。単に紙の重さを示す数値というだけでなく、厚みや質感、耐久性、そして印刷適性までを左右するため、発注や制作の段階でしっかりと理解しておくことが求められます。
連量の概念を正しく知ることで、印刷物の用途や目的に合わせた最適な紙選びが可能になります。薄く軽い連量は大量配布や郵送に向き、コスト面でのメリットがありますが、耐久性や高級感の面ではやや劣ります。一方で、厚く重い連量は存在感や印象を高める効果があり、長期保存や高品質を求める印刷物に適しています。ただし重量増による送料や加工上の制約もあるため、全体のバランスを見極めることが欠かせません。
また、同じ連量でも紙の種類や基準寸法によって厚みや質感が異なる点にも注意が必要です。四六判と菊判では紙1枚の面積が違うため、同じ連量でも仕上がりの印象が変わります。さらに、コート紙、マットコート紙、上質紙などの種類によって発色や手触りが異なり、連量の数値だけでは判断できない要素も多く存在します。
実際の制作現場では、サンプルや試し刷りを活用して、仕上がりや色の再現性、加工適性を確認することが理想的です。数字だけでなく、手に取ったときの感覚や見た目の印象を確かめることで、より確実な用紙選びが可能になります。また、用途やデザインに応じた連量の基準を社内で共有しておくと、品質のばらつきを防ぎ、発注の効率化にもつながります。
さらに、コストや納期の観点からも連量の選定は重要です。厚い紙は材料費や加工費、輸送費を押し上げる可能性があり、薄い紙は耐久性や印象面で不利になることがあります。そのため、目的と予算を明確にしたうえで、必要な部分に最適な連量を配分する工夫が効果的です。例えば、冊子の表紙だけ厚めの紙を使い、中面は軽めの紙にすることで、品質とコストの両立が図れます。
最終的に、連量を理解することは、印刷物の完成度を高めるための基礎となります。紙の厚みや重さは目に見える部分だけでなく、手に取った瞬間の感覚や信頼感にも影響します。数字の背景にある特性を知り、デザイン、用途、コストのすべてを考慮して選ぶことで、見た目も使い勝手も満足度の高い印刷物が実現できるでしょう。
まとめ
連量は印刷用紙の厚さや重さを示す重要な指標であり、印刷物の用途や仕上がりに大きく関わります。これは基準寸法の紙1,000枚分の重さをキログラムで表したもので、数値が小さいほど薄く軽く、大きいほど厚く重くなります。単なる重量の情報にとどまらず、紙の質感や耐久性、発色、加工のしやすさなど、多くの要素に影響を与えるため、制作の段階から意識して選定することが求められます。
同じ連量でも、四六判や菊判といった基準寸法によって紙1枚あたりの厚みや重量感が異なります。また、コート紙、マットコート紙、上質紙などの種類によっても質感や印刷適性は大きく変わります。用途に応じて、軽い連量は大量配布や郵送物、重い連量は高級感や保存性を求める印刷物に向いていますが、それぞれにコストや加工上の注意点があるため、目的や予算とのバランスを取ることが重要です。
さらに、実務ではサンプルや試し刷りで仕上がりや色味を確認し、加工適性や耐久性を見極めることが欠かせません。保管環境や加工工程の工夫によっても品質は安定させることができ、社内で用途ごとの連量基準を共有すれば、品質のばらつきを防ぎやすくなります。
連量の理解は、印刷物の完成度を高め、見た目や手触り、機能性、コストのすべてを満たすための基礎です。数字の意味や背景にある特性を踏まえて選定することで、受け取った人に良い印象を与え、長く活用できる印刷物を作り上げることができるでしょう。
よくある質問Q&A
-
連量とは何ですか?
-
連量とは、特定の基準寸法の紙を1,000枚積み重ねたときの重さをキログラムで表したものです。例えば「コート90kg」とあれば、規定サイズのコート紙1,000枚で90kgの重さがあることを意味します。
-
連量が大きいと何が変わりますか?
-
連量が大きいほど紙は厚く重くなり、しっかりとした質感や存在感が増します。ただし、加工や郵送にかかる負担やコストも上がるため、用途に合わせて選ぶことが重要です。
-
同じ連量でも紙によって厚さが違うのはなぜですか?
-
同じ連量でも基準寸法や紙の種類によって厚さや質感が異なります。四六判と菊判では紙1枚の面積が違い、またコート紙と上質紙では製造方法や繊維の密度が異なるためです。
-
四六判と菊判の違いは何ですか?
-
四六判は788mm×1,091mm、菊判は636mm×939mmの寸法です。四六判の方が面積が大きく、同じ連量でも薄く感じられることがあります。
-
コート紙と上質紙の連量の違いはどう活かしますか?
-
コート紙は光沢があり発色が良く、上質紙は自然な風合いと筆記性に優れています。同じ連量でも質感が異なるため、目的や印刷内容に合わせて使い分けます。
-
軽い連量はどんな用途に向いていますか?
-
軽い連量(55〜64kg程度)は、大量配布するチラシや新聞折込に適しています。軽量で配布や郵送がしやすく、コストも抑えられます。
-
重い連量はどんな用途に適していますか?
-
重い連量(135kg以上)は、ポストカードや高級感のあるパンフレット、DMなどに向いています。しっかりとした質感で印象を強めますが、加工や送料への影響も考慮が必要です。
-
同じ連量でもメーカーによって違いはありますか?
-
あります。製造工程や原材料の違いにより、厚みや手触り、発色の傾向が変わります。大量発注の前にはサンプル確認をおすすめします。
-
連量を決めるときのポイントは何ですか?
-
用途、デザイン内容、印刷方法、予算、配送条件を総合的に考えることです。数字だけでなく、実際のサンプルを手に取って判断することが重要です。
-
連量は印刷コストにどのくらい影響しますか?
-
連量が高いほど材料費や輸送費、加工費が上がります。特に大量印刷では数万円単位で差が出ることもあり、予算計画に大きく関わります。
-
連量が印刷工程に影響することはありますか?
-
あります。厚い紙は印刷機に負荷がかかり、設定変更や給紙速度の調整が必要になります。薄い紙は通紙しやすいですが、シワや紙詰まりが発生しやすくなることもあります。
-
郵送物の連量選びで注意する点は?
-
郵便規格の重量制限に注意が必要です。連量が高すぎると料金区分が上がる場合があります。耐久性とコストのバランスを取ることが大切です。
-
連量はデザインにも影響しますか?
-
はい。厚い紙は高級感を出せますが、ページ数が多い冊子では重くなります。薄い紙は軽快な印象を与えますが、透けや裏移りに注意が必要です。
-
試し刷りは必ず必要ですか?
-
可能であれば行ったほうが良いです。試し刷りをすると発色や手触り、加工適性を事前に確認でき、完成後のイメージ違いを防げます。
-
連量と斤量は同じ意味ですか?
-
ほぼ同じ意味です。どちらも基準寸法の紙1,000枚分の重さを示しますが、呼び方が異なるだけです。
-
連量選びで失敗しないためには?
-
サンプル確認、用途に合った厚さの把握、加工や輸送条件の確認がポイントです。数字だけで決めず、実際に触れて判断することが効果的です。
-
連量を変えると納期に影響しますか?
-
厚い紙は加工に時間がかかるため、納期が延びる可能性があります。薄い紙は比較的スムーズですが、短納期案件では印刷所と事前に相談すると安心です。
-
環境に配慮した連量の選び方はありますか?
-
軽い連量を選ぶことで紙の使用量を減らし、輸送時のCO₂排出も抑えられます。また、再生紙やFSC認証紙など環境配慮型の用紙を選ぶ方法もあります。
-
連量と紙の坪量は違うものですか?
-
違います。坪量は1平方メートルあたりの紙の重さを表しますが、連量は規定サイズの1,000枚分の重さを指します。計算基準が異なります。
-
印刷所に連量を相談する際のコツは?
-
用途や希望する質感、予算、納期を具体的に伝えることです。実物サンプルを見ながら相談すれば、より適切な提案を受けられます。







