印刷会社も採用 封筒口糊スラットとテープスチックの違い徹底比較!
2025.09.03
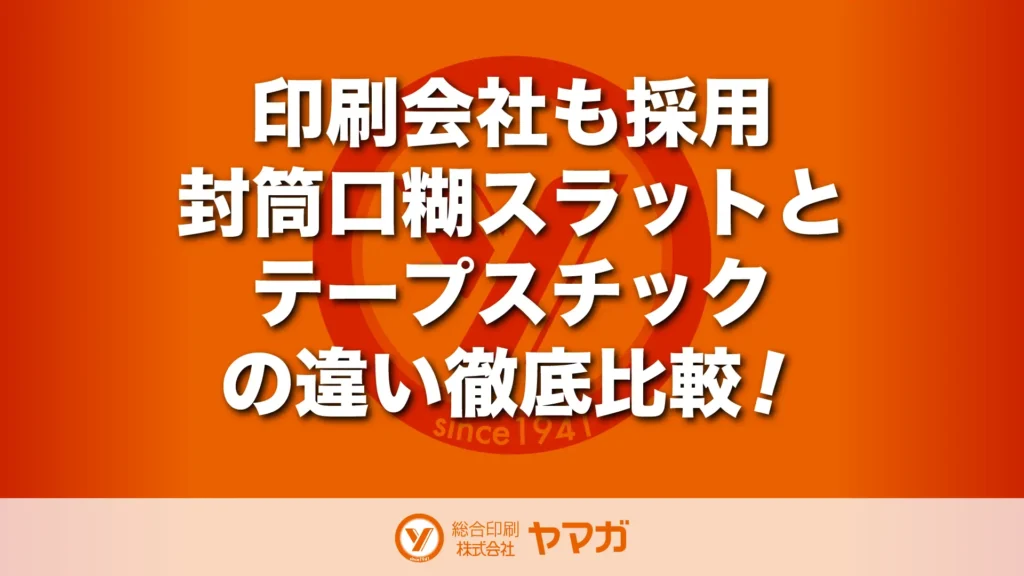
ビジネスの現場では日々さまざまな書類がやり取りされますが、それらを安全かつ確実に届けるために欠かせない存在が「封筒」です。中でも、封筒の口に施される糊加工は見落とされがちなポイントながら、実は使い勝手や信頼性、作業効率に大きな影響を与える重要な要素となっています。この記事では、印刷会社の視点から、スラット加工やテープスチック加工といった封筒の粘着仕様に注目し、それぞれの構造や特徴、用途ごとの使い分け、さらには加工方法と印刷の関係性までを丁寧に解説しています。
スラット加工は、作業の簡便さとスピード感を重視する業務に適しており、短時間で大量の封筒を処理したい現場にとっては大きな味方となります。一方で、より高い密着性とセキュリティ性を求める場合には、テープスチック加工が適しており、長期保存や改ざん防止といった観点からも安心できる選択肢です。それぞれの加工は、封筒のサイズや紙質、印刷の仕様とも深く関係しており、単に「どちらを選ぶか」だけではなく、「どのような組み合わせで設計するか」が求められるようになっています。
印刷会社では、こうした加工の違いを理解したうえで、使用環境や封入物の内容、発送手順などを考慮し、最適な封筒の形をご提案しています。加工後の仕上がりや保管条件、開封のしやすさなど、細かな点に目を向けながら製造することで、企業の業務に寄り添う封筒づくりが実現します。また、近年では非対面でのやり取りや郵送書類の重要性が増しており、封筒に求められる役割も大きく変わってきています。単に書類を包むものではなく、情報を守り、信頼を伝えるツールとしての封筒の価値が見直されているのです。
この記事では、スラット加工とテープスチック加工の違いや選び方、サイズや紙との相性、実務での判断ポイント、さらには今後の封筒需要の変化まで、実務者にとって役立つ情報を網羅しています。封筒の選定でお悩みの方、粘着加工の違いを詳しく知りたい方、または印刷会社に相談する際のポイントを整理したい方にとって、実用的な視点を提供する内容となっています。封筒は「ただの容れ物」ではなく、使う人の工夫と想いが詰まった道具です。その背景にある考え方や技術を、ぜひこの機会に知ってみてください。
- 印刷会社が扱う封筒にはどのような口糊加工の種類があるのか
- 封筒のスラット加工とはどのような構造でどんな特徴があるのかを印刷会社の視点で解説
- 封筒のテープスチック加工がどのような用途に適しているのか
- スラット加工とテープスチック加工の違いを密着性・使いやすさ・保管性の比較
- 封筒の口に使用される粘着加工が郵送物の安全性にどのように関係しているのか解説
- 印刷会社が長期保存を前提とした封筒製造でスラット加工やテープスチックをどう選んでいるか
- 封筒にスラット加工やテープスチックを選ぶ際に知っておきたいサイズや紙質との相性
- スラット加工やテープスチック加工の封筒に適した印刷方法や加工のポイント
- 実務で封筒を扱う企業がスラット加工やテープスチック封筒を選ぶ際の判断基準と注意点
- スラット加工やテープスチック加工の封筒が今後さらに求められると予測される背景
- まとめ
- よくある質問Q&A
印刷会社が扱う封筒にはどのような口糊加工の種類があるのか
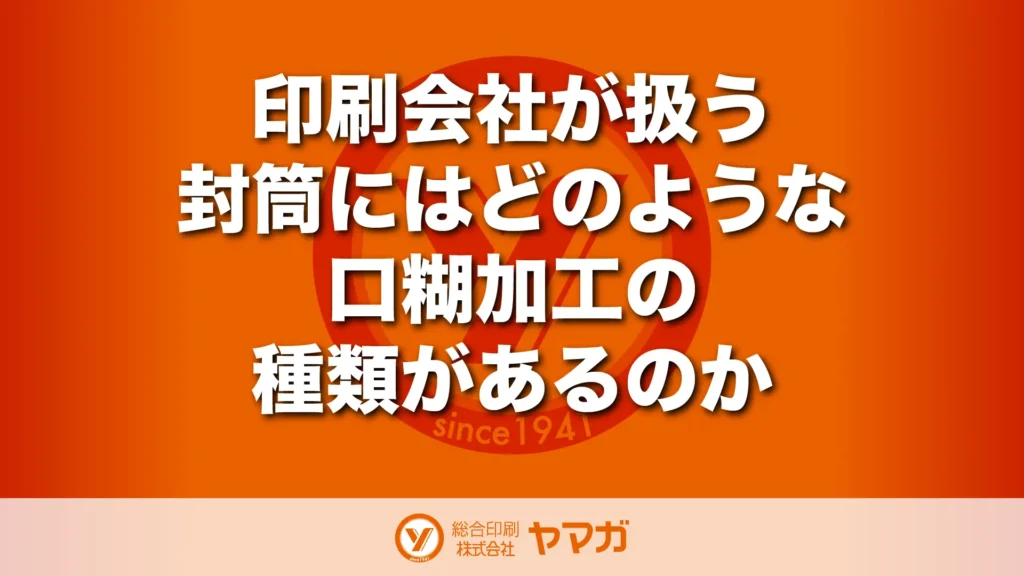
封筒というと、一般的には手紙や書類を入れるための紙製の入れ物として広く知られていますが、その構造や機能には多くの工夫が施されています。特に、封筒の「口」部分に施される加工は、実際の使用シーンや保管期間、用途に大きく関係してくる重要な要素です。印刷会社では、お客様の目的や使い方に合わせて最適な封筒を提案するために、さまざまな口糊加工の種類を取り扱っています。封筒を選ぶ際には中に入れるものだけでなく、封の仕方、保管のしやすさ、開封のしやすさなどにも目を向ける必要があるため、ここではその「口糊加工」について基本から丁寧にご紹介します。
まず、「口糊加工」という言葉にあまり馴染みがない方のために簡単に説明すると、これは封筒のベロ(ふた)の部分に、封を閉じるための糊や粘着テープをあらかじめ施しておく加工のことを指します。用途に応じて封筒に糊をつける作業を省略できることや、接着力の安定性、作業の効率化につながるため、ビジネスや大量発送を行う現場では欠かせない機能となっています。
代表的な口糊加工の種類として、まず「アドヘア糊」が挙げられます。これは、封筒の口の両側に水溶性の接着剤があらかじめ塗られており、封をする際には水を含ませて貼り合わせるタイプです。昔ながらの封筒に多く見られる方式で、コストは比較的安価ですが、水を使う必要があるため作業にひと手間かかるという特徴があります。大量発送やスピードが求められる業務用途にはあまり向いていない場合もあります。
次に、使用頻度が高い加工として「スラット糊加工」があります。こちらはベロの部分に粘着剤とセパレーター(剥離紙)が付いていて、封を閉じる直前にこの紙を剥がすことで粘着面が露出し、簡単に封ができる仕組みです。剥離紙をはがすだけでしっかりと封ができるため、水を使う必要がなく、非常に簡便です。印刷会社では、社内での封入作業が多い企業や、効率化を求めるお客様に広く提案されている加工です。また、ベロの粘着部分が封筒内部の紙面と接触しない構造であるため、文書や印刷物を入れる際にも安心感があります。
続いて「テープスチック加工」について説明します。テープスチックもスラット加工と同じように、ベロに両面テープがついている封筒です。テープの片側が封筒に接着されていて、使用する直前にもう一方の剥離紙をはがして粘着面を露出し、封をする形式となっています。特徴的なのはその粘着力の強さで、しっかりと密閉できるため長期保管が前提となる書類や契約書などの郵送にも向いています。また、しばらく使わずに保管しておいても粘着力が劣化しにくく、使いたいときにすぐ封ができるのも大きな魅力です。スラットよりもややしっかりとした作りで、使用後の開封が困難なことからセキュリティを重視する場合にも活用されています。
他にも「スチック糊」や「ピール&シール」などと呼ばれる形式もありますが、基本的な仕組みはスラットやテープスチックと似ており、名称は業界やメーカーによって異なる場合があります。印刷会社では、それぞれの加工方式の特性を理解したうえで、予算、用途、発送件数、封入方法などに応じた提案を行っています。
このように、封筒の口糊加工にはいくつかのバリエーションがあり、それぞれに向いている場面や使い方があります。アドヘア糊はコスト重視の方向け、スラットは作業効率と安全性のバランスが良く、テープスチックは信頼性と長期保管に対応できる高粘着性が魅力です。封筒を選ぶ際には、単にサイズやデザインだけでなく、こうした封のしやすさや目的に応じた加工の種類にも目を向けることで、日々の業務効率がぐっと高まるでしょう。
印刷会社では、お客様から「どの糊加工を選べばいいかわからない」「どれがコストに合うのか知りたい」といった相談を多くいただきます。そのため、現場では使用環境や封入する書類の種類、保管期間、封入方法のフローなど、細かな点までヒアリングし、最適な封筒を提案しています。とくに最近では、セキュリティ面への意識が高まっていることや、業務の効率化が求められている背景から、手間をかけずに確実に封ができるスラットやテープスチックの需要が増えています。こうした動きを受けて、封筒の製造ラインでもこれらの加工を前提とした製品開発が進んでいることから、印刷会社にとってもこれらの糊加工を理解しておくことは非常に重要です。
以上が、印刷会社が扱う封筒における口糊加工の基本的な種類とその特徴についてのご紹介でした。次のブロックでは、これらの中でも「スラット加工」に焦点を当てて、その構造や利便性について詳しく解説していきます。
封筒のスラット加工とはどのような構造でどんな特徴があるのかを印刷会社の視点で解説
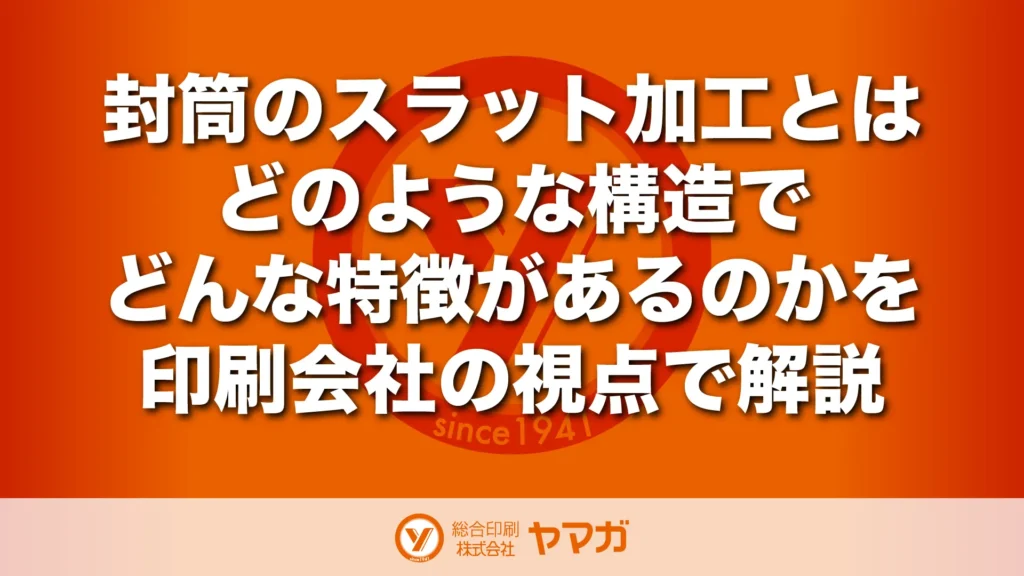
封筒の口を閉じる方法として、スラット加工は近年ますます注目されるようになっています。とくに大量の書類を扱う業務や、短時間での封入作業が求められる現場では、その使いやすさと効率の良さから多く採用されるようになってきました。印刷会社では、このスラット加工がどのような構造を持ち、なぜ多くの現場で支持されているのかを把握したうえで、お客様に適した封筒を提案しています。
スラット加工の構造についてご説明すると、封筒のベロ(蓋)部分にあらかじめ粘着剤が塗布されており、その粘着面の上にセパレーターと呼ばれる剥離紙が貼られている仕組みになっています。使用する際には、この剥離紙を手ではがすだけで粘着面が現れ、封筒を簡単に閉じることができます。この手順が非常にシンプルであるため、従来の水糊のようにスポンジで水を含ませたり、スティック糊を使ったりする手間が一切必要ありません。特に手袋を着けて作業するような現場では、このワンタッチの構造が大きな利点となります。
スラット加工の封筒は、発送業務の現場での作業効率を高めるうえで非常に優れた性質を持っています。たとえば、一日に何百通、何千通もの書類を封入・封緘するような業務では、わずか1〜2秒でも作業時間を短縮できることが全体の効率に大きく影響します。スラット加工の封筒は、封をする動作が極めてスムーズでスピーディなため、人手による封緘作業でもスムーズに進みますし、自動封入機との相性も良いとされています。
さらに、このスラット加工にはもうひとつ大きな特徴があります。それは、封緘の際に使う粘着剤がしっかりとした粘着力を保っている点です。開封されない限りは口が自然に開いてしまうことがなく、安心して封書を送ることができます。一方で、粘着剤が時間の経過によって劣化してしまうこともありますので、印刷会社ではスラット封筒の使用期限や保管方法についても丁寧に説明するよう心がけています。基本的には製造から半年から1年以内の使用を推奨しており、直射日光や高温多湿を避けた保存が望ましいとされています。
スラット加工はまた、剥離紙がついているという点で、セキュリティ面にも配慮された設計となっています。剥離紙が残っていれば未使用であることが一目で分かりますし、逆に剥離紙が剥がされていれば、誰かが封を開けた可能性があるという判断もできます。このような目に見える安全性は、社外秘の資料や個人情報を含む書類を送る際に大きな安心材料となります。加えて、封緘後は比較的強固に閉じるため、輸送中に封が外れてしまうリスクも軽減されます。
ただし、スラット加工にも留意点はあります。たとえば、剥離紙のごみが大量に出るという点です。多くの枚数を使用する場合、その分剥がされた剥離紙も多くなり、作業後にはゴミの回収や分別が必要となります。また、一度封をしてしまうと基本的には再利用ができず、開封時には紙が破れてしまうことが多いため、封入物の再確認が難しくなるという面もあります。印刷会社ではこうした特性を踏まえ、封筒の使い切りを前提とした一方通行の書類送付に適した加工であることを説明しています。
スラット加工は、作業効率を高めたい業務現場にとって、非常に魅力的な加工方法のひとつです。そのシンプルな使い勝手、安心感、スピーディな作業性により、今後も多くの印刷会社が標準仕様として提案し続けることが予想されます。とくに大量発送や短期間での書類処理が求められる業界では、封筒選びの段階でスラット加工を指定されるケースも増えており、それに応えるべく、製造現場でも品質安定化への取り組みが日々進んでいます。
封筒はただの「入れ物」ではなく、使う人の負担を減らし、送り先に確実に届けるための道具です。その中でもスラット加工は、多くの用途に対応できる柔軟な選択肢として、今後も幅広く使われていくことでしょう。次のブロックでは、スラットと並んでよく利用されている「テープスチック加工」に焦点を当て、その構造や活用方法について解説していきます。
封筒のテープスチック加工がどのような用途に適しているのか
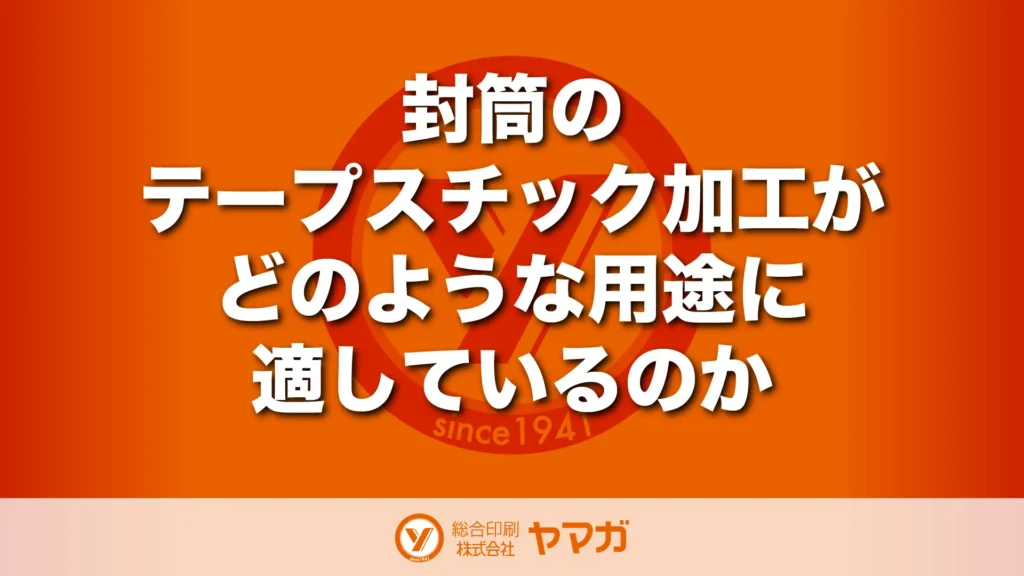
封筒の口を閉じる加工方法の中でも、粘着力の強さと長期保存への適性が評価されているのがテープスチック加工です。印刷会社では、この加工が必要とされる業種や書類の種類を熟知し、それぞれの使用目的に応じた封筒の選定をサポートしています。ここでは、テープスチック加工がどのような仕組みで成り立ち、どのような場面に適しているのかを詳しくご紹介します。
まず、テープスチック加工とはどのような構造になっているのかをご説明します。封筒のベロ部分に、あらかじめ強粘着の両面テープが貼り付けられており、その上に剥離紙がセットされています。使用時には、この剥離紙をはがすことで粘着面が現れ、封筒本体にしっかりと密着させることができるようになっています。構造自体はスラット加工と似ていますが、最大の違いは使用されているテープの粘着力と接着の安定性にあります。テープスチックに使われる粘着剤は、時間が経っても劣化しにくく、長期間経ってから封をしても確実に密閉できるように設計されています。
このような特性から、テープスチック加工の封筒は「長期保管を前提とした書類」や「改ざんを避けたい重要書類」の封入に向いています。たとえば、契約書や財務関係の書類、医療記録、学術的な資料など、年月を経ても原本として価値がある書類を保管する場合には、外部からの影響を受けにくく、自然には開かないしっかりとした封が求められます。テープスチックの封筒は、このような用途に対して非常に高い信頼を得ています。
さらに、テープスチック加工が活躍する場面として、印刷後から実際に使用されるまでに長い時間が空くケースがあります。通常のスラット加工では、粘着剤の性質上、保存状態によっては粘着力が低下してしまうこともありますが、テープスチックはその点で安心です。一定の保存環境を守っていれば、数ヶ月から1年程度は問題なく保管でき、必要なときにいつでも確実に封をすることができます。これにより、印刷会社では事前にまとめて印刷・加工しておき、必要に応じて使用するスタイルも可能になります。
また、セキュリティ面での信頼性もテープスチックの大きな強みです。貼り合わせたあとの粘着力が非常に高いため、一度封をしてしまうと、封筒を開封するには明確な破損が発生します。つまり、誰かが中身を確認するために一度開封した場合、再び元の状態に戻すことができないという特性があります。このような仕様は、重要書類を郵送する企業や、個人情報を取り扱う部署での利用において、受け取り手に対しても安心感を提供します。
印刷会社の視点から見ると、テープスチック封筒は企業のブランディングの一部としても活用されています。たとえば、重厚感や信頼感を重視する企業が顧客に書類を送る場合、しっかりとした作りのテープスチック封筒を選ぶことで、書類の中身だけでなく「届け方」そのものに対しても誠実な姿勢を伝えることができます。表面に高品質な印刷や加工を施すことで、デザイン性にもこだわった封筒づくりが可能となり、封筒そのものが企業のイメージ向上につながることもあります。
ただし、テープスチック封筒には注意点もあります。それは、一般的なスラット封筒に比べてコストがやや高くなる傾向にあるという点です。また、封を一度したら開けることができないため、封入作業の際には中身の確認を十分に行う必要があります。作業後に「あ、間違って入れた」と気づいても、貼り直しができないため、丁寧なチェック体制が求められます。印刷会社では、こうした特性を踏まえて、用途や封入内容に合わせた注意喚起を行いながら、テープスチックの提案をしています。
テープスチック加工は、その高い粘着性、耐久性、安心感から、書類の品質を保ちたいというニーズに応える封筒として、ますます採用される場面が増えてきています。長期保存、改ざん防止、企業の信頼感の演出など、用途は多岐にわたります。印刷会社では、この加工がもたらす多くのメリットと同時に、その使いどころや注意点を丁寧に説明することが、封筒選びのサポートとしてとても大切な役割となっています。
次のブロックでは、これまで紹介したスラット加工とテープスチック加工を比較し、それぞれの強みや使い分けについて詳しく解説していきます。
スラット加工とテープスチック加工の違いを密着性・使いやすさ・保管性の比較
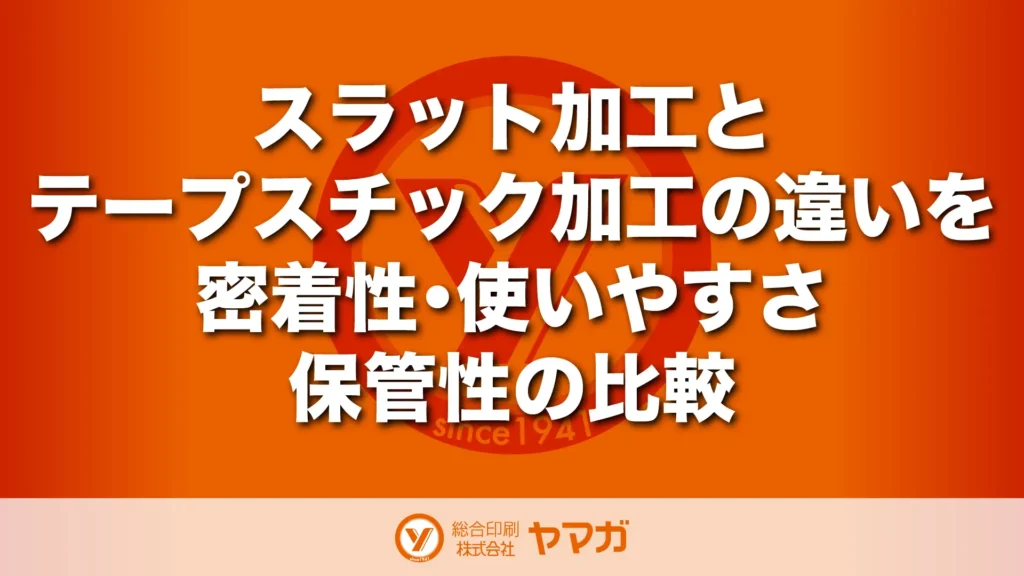
封筒の口を閉じる加工として、スラット加工とテープスチック加工はどちらも高い人気がありますが、それぞれに異なる特徴があり、使用目的や運用環境に応じた使い分けが求められます。印刷会社ではお客様の用途を丁寧にヒアリングしながら、どちらの加工が適しているのかを判断するお手伝いをしています。このブロックでは、スラットとテープスチックという二つの口糊加工を、密着性、使いやすさ、保管性という三つの観点から比較しながら詳しくご説明します。
まず「密着性」についてですが、封筒を封緘したあとの粘着力や、密閉状態の保持に関する性能を指します。スラット加工では、剥離紙をはがしたあとの粘着面が比較的柔らかく、貼り直しが多少できる場合もあります。ただし、その分だけ完全に密着させるためには、ベロ部分をきちんと押し込むなどの操作が必要になります。一方、テープスチック加工では、粘着剤がテープ状にしっかりと加工されており、貼り合わせるとすぐに強く接着します。このため、封緘後に開封されることが少なく、長期間の密閉性を維持できます。改ざん防止や重要書類の郵送では、この密着性の違いが大きな判断材料となります。
次に「使いやすさ」の視点で比べてみましょう。スラット加工の封筒は、剥離紙を軽くはがすだけで封緘が可能なため、多くの現場で導入されています。手が汚れにくく、乾くのを待つ必要もなく、封をする作業がスムーズに進みます。また、貼り付ける位置を少し調整する余地があるため、初めて使う人でも扱いやすい点が特徴です。対してテープスチック加工は、剥離紙をはがすとすぐに強粘着のテープが露出するため、一度貼ってしまうと再調整が難しくなります。このため、封をする前に封入物の確認をしっかり行っておくことが求められます。ただし、貼る動作自体は非常にシンプルで、一度の動きでしっかり封ができるため、慣れた人にはかえって時短につながることもあります。
そして三つ目の「保管性」についてですが、これは加工された封筒を長期的に保管した際に粘着力がどれだけ持続するか、また封筒の品質が変わらず維持されるかという観点です。スラット加工の場合、封筒に加工された粘着剤が湿気や温度に影響を受けやすく、保管期間が長くなると粘着力が落ちてしまうリスクがあるため、印刷会社では半年〜1年以内の使用を推奨しています。特に高温多湿な環境では、粘着面が乾いてしまったり、逆にベタついてしまったりすることもあるため、保存場所にも注意が必要です。
一方でテープスチック加工の封筒は、使用されている両面テープの粘着力が強力で、しかも変質しにくい素材で構成されていることが多いため、長期間の保管にも耐えることができます。たとえば、年度ごとにまとめて封筒を作成しておき、必要なときに1枚ずつ取り出して使うといった運用にも適しています。また、印刷会社ではあらかじめ「長期保存対応」として設計されたテープスチック封筒をラインナップしており、契約関連や法的文書、証明書類などに利用されるケースが増えています。
これらの比較からわかるように、スラット加工とテープスチック加工は、どちらが優れているかというよりも、それぞれの特性をどう活かすかがポイントになります。スラット加工は作業効率を重視しながらも、封筒の在庫回転が早い現場に適しており、比較的短期間で封入作業を完了させる業務に向いています。逆に、テープスチック加工は保管性や封緘の堅牢さが求められる現場、またはお客様へ信頼感のある封書を送りたいという意図のある場合に適しています。
印刷会社では、お客様の声を反映しながら、これらの加工を使い分けることで最適な封筒のご提案を行っています。たとえば、資料請求用の返信用封筒にはスラット加工を採用し、返信されてくる際の手間を減らす工夫をしたり、一方で重要契約書類の送付にはテープスチック加工を使い、情報漏洩リスクを抑える形で使用されることがあります。
このように、スラットとテープスチックはどちらも非常に機能的な封緘方法ですが、目的や業務の流れをしっかりと理解したうえで選ぶことで、より使いやすく、より安心できる封筒活用が実現します。次のブロックでは、こうした封筒の加工方法が、郵送物の安全性や機密性とどのように関係しているのかについて、もう少し踏み込んで解説していきます。
封筒の口に使用される粘着加工が郵送物の安全性にどのように関係しているのか解説
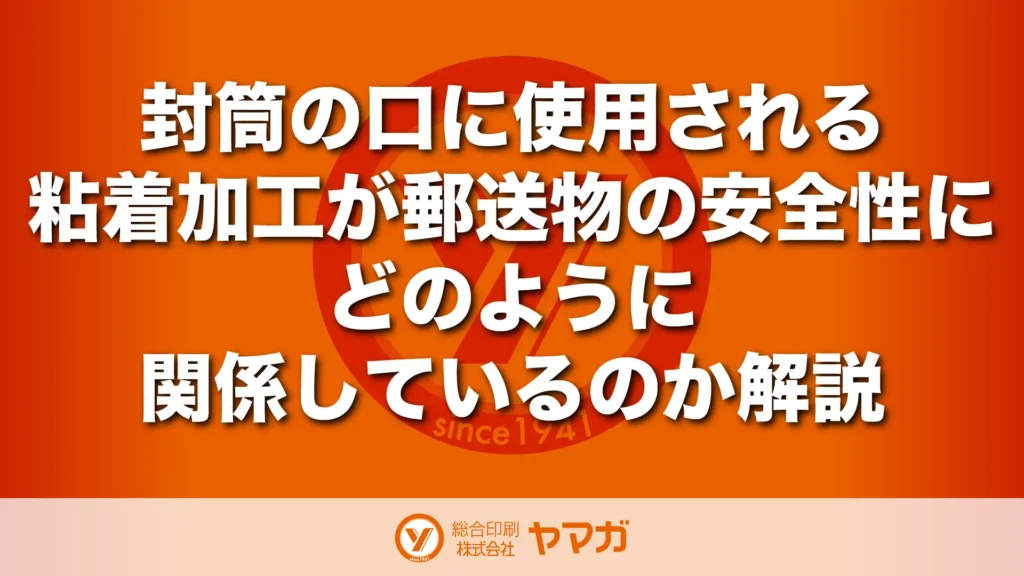
封筒の「封をする」という行為は、単に口を閉じるための手段ではありません。それは、送り手の想いや意図を安全かつ確実に届けるための、大切なプロセスでもあります。特にビジネスシーンにおいては、封筒の中に入っている書類が契約書、請求書、個人情報、あるいは商品サンプルであったりすることも多く、その中身の重要性に応じて「封がしっかりされているかどうか」は、送り手の誠実さや信用力を表すひとつの基準にもなり得ます。
このように郵送物の安全性を考えるうえで、封筒の口に使用される粘着加工の選択は、とても大きな意味を持っています。印刷会社では、粘着加工がどのようにして郵送物のセキュリティ性に影響を及ぼすのかを理解し、お客様にとって最も安心できる仕様を提案することが日常業務の一部となっています。
まず、安全性の面で注目すべきは「開封されにくさ」です。たとえば、アドヘア糊や水糊タイプでは、時間の経過や環境の変化によって粘着力が弱まることがあり、輸送中の振動や湿度の変化で自然に開いてしまうこともゼロではありません。それに対してスラット加工やテープスチック加工は、製造段階で安定した接着力を持つ粘着剤が使われており、封をしたあとにしっかりと密着するため、輸送中に封が緩むことはほとんどありません。特にテープスチック加工は強力な両面テープを使用しているため、一度貼り付けたあとに自然に剥がれることはまずありません。
さらに、安全性という観点では「改ざん防止」の機能も見逃せません。封筒に加工されている粘着剤がしっかりとしていれば、誰かが一度開封した場合、その痕跡がはっきりと残るようになります。スラット加工でも、いったん剥離紙をはがして封をしたあとに再び開けると、ベロ部分に折れやシワが残るため開封の痕がわかりやすくなります。一方テープスチック加工の場合は、粘着力が非常に強く、一度封をしてしまうとほぼ確実に封筒が破れてしまいます。そのため、途中でこっそり開けて中身を確認し、また封をし直すといった不正な行為が極めて困難になります。
この「開けたらわかる」という仕組みは、送り手と受け手の双方にとって非常に大きな安心材料となります。例えば、企業が取引先に契約書を送る場合、途中で内容を改ざんされたり、第三者に読まれたりしてしまうリスクを最小限に抑えるためには、封筒そのものがしっかりとしたセキュリティ機能を備えていることが求められます。テープスチック加工は、そういった要望に応えられる実用的な仕様として非常に信頼されています。
また、郵送時における水濡れや衝撃、荷重といった外的要因にも注目する必要があります。スラット加工やテープスチック加工は、加工面がしっかりと接着されることで密閉性が高まり、ちょっとした湿気や衝撃では封が開かない構造となっています。こうした粘着力の安定性は、特に梅雨時や台風シーズンなど、輸送時の気候リスクが高まる季節において、郵送物の信頼性を大きく高めてくれます。印刷会社では、使用する時期や気候条件までを考慮して封筒の加工方法を提案することも少なくありません。
さらに、封筒に貼られるラベルや差出人情報などが剥がれてしまうこともありますが、しっかり封をされた封筒であれば、封の状態だけで荷物の安全性をある程度判断することができます。つまり、「ちゃんと閉じられているか」は、外見上の信頼感にもつながるのです。これは企業が顧客に何かを送る際にも非常に大切で、たとえば入社案内や商談資料などを送る場合でも、丁寧に封がされた封筒であれば、その会社がどれほど細やかに気を配っているかが相手に伝わります。
このように、封筒の口に使われる粘着加工は、単なる作業効率の向上だけでなく、郵送物の安全性や信頼性を守るための基本であり、非常に重要な役割を果たしています。印刷会社では封筒を製造する際、粘着剤の選定から貼り付け方法、テスト封緘の確認までを行い、安全性に十分な配慮を重ねたうえで出荷を行っています。お客様にとっては見えない部分かもしれませんが、こうした裏側の工夫があるからこそ、安心して封筒を使うことができるのです。
次のブロックでは、さらに踏み込んで、長期保存を前提とした書類送付において、印刷会社がどのようにスラット加工やテープスチックを使い分けているのかをご紹介していきます。
印刷会社が長期保存を前提とした封筒製造でスラット加工やテープスチックをどう選んでいるか
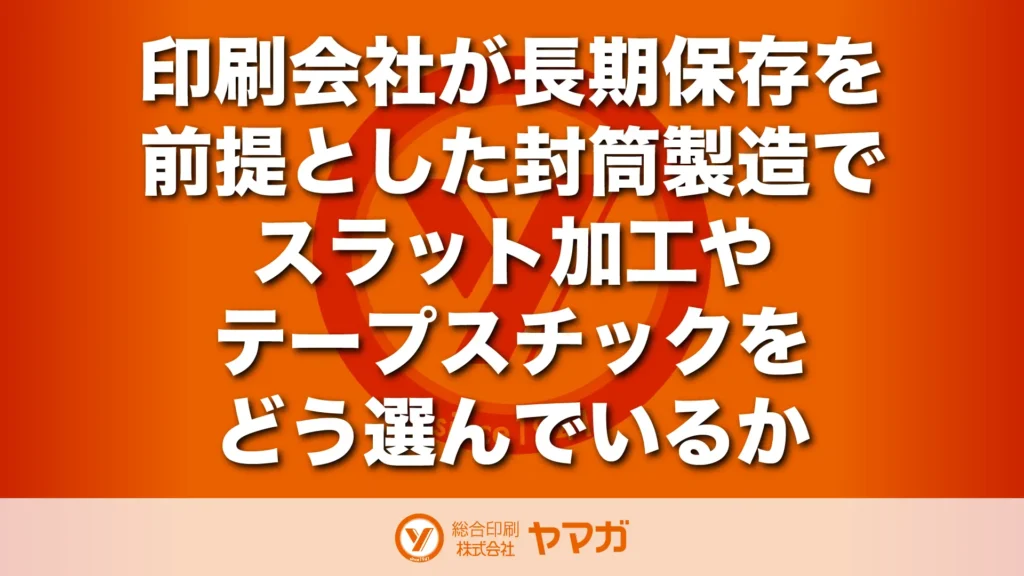
書類や資料を封入した封筒を、すぐに開封せず長期間にわたって保管しておきたいというニーズは、多くの企業や団体で見られます。たとえば、契約関連の書類、証明書、医療記録、行政文書など、何年にもわたって保管が必要な郵送物では、封筒自体の劣化を防ぎながら、中身を守る役割が求められます。印刷会社では、そうした用途に対応するために、封筒の構造や紙質だけでなく、「口の閉じ方」に使う糊やテープの選択にも特別な配慮を行っています。
長期保存を前提とした封筒製造では、まず最初に考えるのが「封緘後の安定性」です。どれほどしっかりと封がされているか、時間が経っても粘着力が弱まらないか、外気や湿気の影響を受けて剥がれてしまう可能性がないか、という点は非常に重要です。そのため、印刷会社では通常の短期発送向けとは異なる素材や加工方法を使い分け、封筒が数年単位で保存されることを想定した品質設計を行っています。
このとき、もっとも多く採用されるのがテープスチック加工です。テープスチックは、ベロ部分に貼られた両面テープによって強力に封をすることができ、長時間の保管にも耐えうる粘着性能を備えています。この加工は、しっかりとした接着力がありながら、保存環境の湿度や温度による変化にも強く、使用前に封筒が劣化する心配も少ないのが特徴です。さらに、開封時には封筒そのものが破損するような構造になっているため、セキュリティ性にも優れており、未開封の証拠としても機能します。
一方で、スラット加工も条件によっては長期保存に向いている場合があります。スラットはテープスチックに比べて粘着力はやや穏やかですが、使用時の作業性に優れていることや、用途によっては1〜2年程度の保管にも問題なく対応できることがあります。ただし、その場合は保管環境に対する配慮が必要で、特に高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管することが推奨されます。また、印刷会社ではスラット加工に使う粘着剤の品質にも差があるため、長期保存を希望される場合には、より耐久性の高い仕様で製造されるスラットタイプを用意することもあります。
封筒製造の現場では、使用される紙の厚みやコートの有無、印刷内容との兼ね合いなども含めて、封筒がどのように保管されるかをイメージしながら加工の選定を行います。たとえば、役所や病院などで使用される封筒の場合、中に重要な情報が含まれることが多く、かつファイルや書庫で物理的に長期保管されるため、テープスチック加工が好まれます。逆に、季節の案内状や期間限定の通知といった、一時的な保存で済む郵送物であれば、スラット加工で十分なケースもあります。
また、封をするタイミングが印刷から長く空く場合にも注目が必要です。スラット加工は粘着剤が露出しておらず、剥離紙で覆われているため、比較的劣化しにくいとはいえ、保管環境に左右されやすい一面があります。一方で、テープスチックのほうが、剥離紙と強粘着の組み合わせによって、より確実に品質を維持できる構造になっているため、「しばらく封筒を使わず保管しておきたいが、いつか封をする時に問題があっては困る」という状況には非常に適しています。
印刷会社では、こうしたニーズを把握するために、封筒を使用する時期や期間、保管する場所、使用者の運用体制などを事前に丁寧にヒアリングすることを大切にしています。そのうえで、例えば「高温になる倉庫で保管されることが多い」といった条件がある場合には、粘着剤の耐熱性にも配慮したテープスチック封筒を提案したり、パッケージ単位で使用期限の目安を記載したりといった工夫も行っています。
このように、長期保存を前提とした封筒づくりにおいては、単に加工方法の選択にとどまらず、どのように使われ、どのように保管されるのかまでを想定した設計が不可欠です。スラット加工もテープスチック加工も、それぞれに長所があり、封筒の目的や使用環境によって最適な使い分けが可能です。印刷会社は、こうした細やかなニーズに対応しながら、必要な場面で必要な品質を確保するために、常に封筒づくりの工夫を重ねています。
次のブロックでは、封筒にスラット加工やテープスチックを採用する際に知っておきたい、サイズや紙質との相性について詳しくご紹介していきます。
封筒にスラット加工やテープスチックを選ぶ際に知っておきたいサイズや紙質との相性
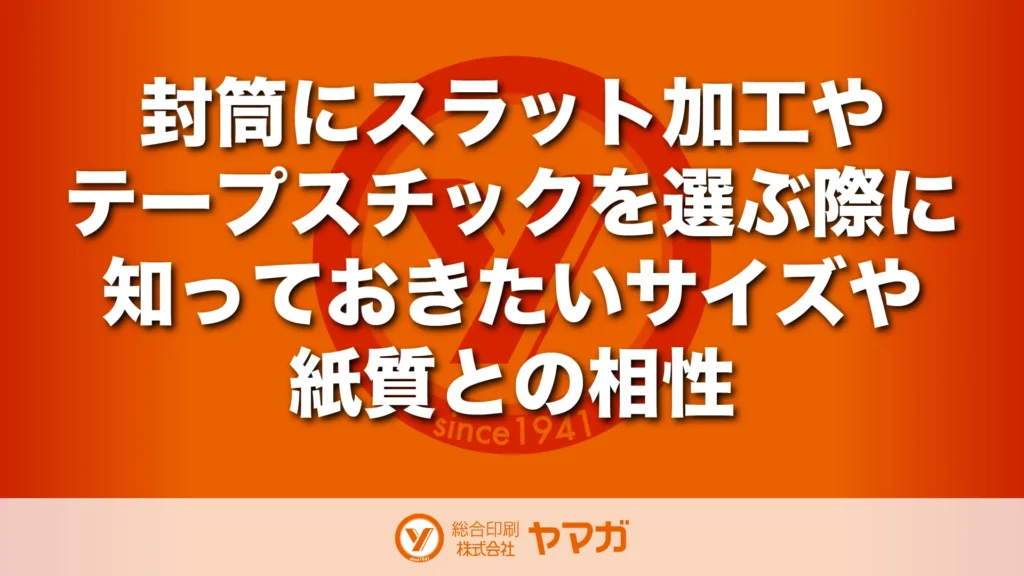
封筒にスラット加工やテープスチック加工を施す際、見落とされがちなのが、封筒のサイズや紙質との相性です。加工方法そのものに注目が集まりがちですが、実際にはその封筒の大きさや使われている紙の素材、厚さなどとの組み合わせによって、封のしやすさや耐久性が大きく変わってくるのです。印刷会社では、こうした相性を踏まえて、単に加工方法だけでなく、トータルな仕様として最適な封筒を提案することが求められています。
まずサイズとの関係を見てみましょう。スラット加工もテープスチック加工も、どちらも一般的な長形3号や洋形2号、角形2号など、さまざまなサイズの封筒に対応できますが、サイズが大きくなるにつれて加工の意味合いや効果にも違いが出てきます。たとえば、角形2号や角形A4といった大判サイズの場合、封筒のベロも大きくなるため、その分だけ封緘時にかかる力や接着面積も広がります。このとき、粘着剤の接着力が弱いと、封をしてから時間が経った際に徐々に開いてしまう可能性があるため、テープスチックのように強粘着タイプの加工がより適しています。特に厚手の冊子や重みのある書類を封入するケースでは、密着力の高さがそのまま封筒の安心感につながります。
反対に、定形サイズの長形3号や洋形4号のような小型封筒では、封をする面積が限られているため、スラット加工でも十分に密着性を確保できます。小さめの封筒にテープスチックを使うことももちろん可能ですが、コストや加工時のバランスを考えると、スラットのほうが使い勝手がよく、作業効率の面でもメリットがあると感じる方が多いようです。印刷会社では、このようなサイズごとの特性に応じて、最適な加工方法を組み合わせることが一般的です。
次に、紙質との相性についても見ていきましょう。封筒に使われる紙は、上質紙やクラフト紙、コート紙などさまざまな種類がありますが、それぞれの紙が持つ表面の質感や厚みによって、粘着加工の効果も異なってきます。たとえば、ツルツルとした表面を持つコート紙は、粘着剤がなじみにくく、封緘後の接着力に不安が残ることがあります。こういった場合は、粘着剤の種類を変えたり、テープスチックのように確実に貼りつく仕様を選んだりすることで、品質を担保する必要があります。
また、紙が厚すぎる場合には、ベロを折り返す際に反発力が働きやすくなり、接着した直後に開いてしまうリスクも生じます。こうしたケースでは、より強力な粘着力を持つテープスチックを選ぶか、封をしたあとに一定の圧力を加えるような運用方法を加えることで、安定した封緘が可能になります。印刷会社では、実際の紙サンプルを使ってテスト封緘を行い、使用する紙と加工方法の組み合わせが十分に機能するかを事前に確認することが多くあります。
逆に、やわらかく吸水性のある紙質を使用する場合には、スラット加工でも十分な粘着力が得られることがあります。こうした紙は粘着剤がしっかりと浸透し、短時間で安定した接着が得られるため、軽量書類や郵便物の発送に適しています。ただし、紙の表面が粗すぎると粘着剤が均等に広がらない可能性もあるため、封筒の材質選びと加工のバランスは常に検討が必要です。
さらに、印刷内容との関係も見逃せません。封筒に濃い色のインクを広範囲に使用する場合、ベロの裏側にもインクが回ってしまい、粘着加工の際に影響が出ることもあります。特にスラット加工の場合、インクの成分が粘着剤と干渉することで、接着力が弱まる可能性もあるため、印刷設計の段階でベロ部分にはインクが重ならないように配慮する必要があります。印刷会社ではこの点も見越して、版下の段階から細やかな調整を行っています。
このように、封筒にスラット加工やテープスチック加工を選ぶ際には、ただ加工方法を決めるだけでなく、その封筒のサイズや紙の種類、印刷の内容など、さまざまな要素を考慮して最適な組み合わせを見つけることが大切です。印刷会社では、加工方法の技術的な知識だけでなく、素材や用途の理解を深めることで、お客様にとって最も信頼できる製品を提供できるよう努めています。
次のブロックでは、こうした封筒への加工を施す際に適した印刷方法や、加工工程で注意すべきポイントについて詳しくご紹介します。
スラット加工やテープスチック加工の封筒に適した印刷方法や加工のポイント
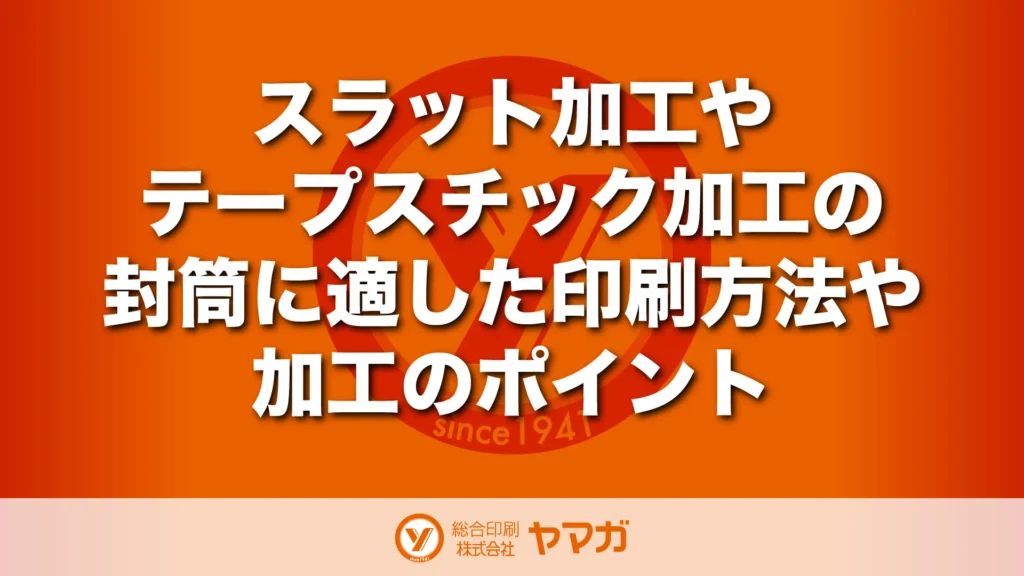
封筒にスラット加工やテープスチック加工を施す際、加工そのものの仕組みや使い方だけでなく、その封筒にどのような印刷を施すかという点も非常に重要です。印刷と加工の相性が悪ければ、粘着剤の機能が正しく働かなくなることもあるため、印刷会社では加工方法に応じて最適な印刷設計を行うことを基本としています。このブロックでは、スラット加工やテープスチック加工の封筒において注意したい印刷方法や、加工時の大切なポイントについて詳しくご紹介します。
まず、封筒のベロ部分、つまり封を閉じるために折り返すふたの部分は、粘着剤や両面テープを貼るためのスペースとして設計されています。ここに印刷が乗ってしまうと、インクの成分が粘着剤と反応して接着力が弱まったり、インクの油分によって粘着が不安定になったりすることがあります。そのため、スラット加工やテープスチック加工を施す予定の封筒では、あらかじめ「印刷禁止エリア」としてベロ部分に印刷がかからないようにデータを設計します。印刷会社では、この部分を避けるためにガイドラインを作成し、デザイナーにも共有しながら正確な版下作成を行っています。
特に注意が必要なのは、ベタ印刷や濃色インキを使用するデザインです。スラット加工の場合、接着剤が紙の繊維に浸透してしっかりと粘着力を発揮する構造になっていますが、印刷インキが紙の表面を覆ってしまうと、粘着剤が十分に浸透できなくなることがあります。また、テープスチック加工の場合でも、テープが貼られる部分に印刷インキがかかっていると、剥離紙との密着が不安定になり、はがした際に粘着面がきれいに出ないといったトラブルにつながる可能性があります。
こうしたリスクを防ぐためには、封筒全体のデザインと印刷仕様を、加工工程にあわせて設計する必要があります。印刷会社では、加工を前提とした設計段階からのサポートを行い、「どこまで印刷をかけてよいか」「加工部分をどう残すべきか」といった技術的なアドバイスを行います。また、特殊な紙を使用する場合には、インキののり具合や粘着剤の定着性も含めたテスト印刷を行い、実際の使用環境を再現しながら確認を進めることもあります。
印刷方式にも相性があります。たとえば、オフセット印刷では紙へのインキの定着が安定しやすく、細かなデザインの再現性にも優れています。一方、オンデマンド印刷やレーザープリントでは、トナーの熱によって紙の表面がわずかに変化することがあり、加工後の粘着剤との相性に影響することもあります。こうした点を踏まえ、封筒の最終的な仕様や使われるプリンターの種類まで確認することで、トラブルのない製品づくりが可能となります。
また、スラット加工やテープスチック加工の封筒では、封を閉じたときにどの程度の力がかかるか、封緘後に紙が波打ったりしないかといった点も重要です。たとえば、紙の厚さやサイズ、封筒の折り方によっては、貼り合わせたときにわずかなズレや引きつれが生じ、封筒全体の見た目や仕上がりに影響を及ぼすことがあります。印刷会社では、あらかじめ紙の伸縮性や形状を把握したうえで、ベロの長さや粘着範囲を調整し、最終製品が美しく使いやすいものになるよう設計しています。
加工後の仕上げにも注意が必要です。スラットやテープスチック加工を施したあとに断裁や折り加工を行う場合、機械の圧力や刃の当たり具合によって粘着剤がにじみ出たり、剥離紙が部分的に浮いたりすることがあります。そのため、加工は必ず専用の工程で行い、粘着面に過剰な圧力がかからないよう調整します。さらに、完成品を出荷する際にも、封筒同士がくっつかないよう仕切り紙を挟んだり、外装袋に滑りやすい素材を使用したりと、細やかな配慮が求められます。
印刷会社では、封筒の加工と印刷を一体で行う体制を整えていることが多く、最初のデータ作成から製品の出荷まで、一貫して品質を管理できるのが強みです。お客様が求める封筒の機能や見た目を実現するために、デザイン、印刷、加工のすべてを連携させながら、最適な形を提案しています。
次のブロックでは、実際にスラット加工やテープスチック加工の封筒を選ぶ際、企業が判断するために注目しているポイントや、印刷会社がそれにどう応えているかをご紹介していきます。
実務で封筒を扱う企業がスラット加工やテープスチック封筒を選ぶ際の判断基準と注意点
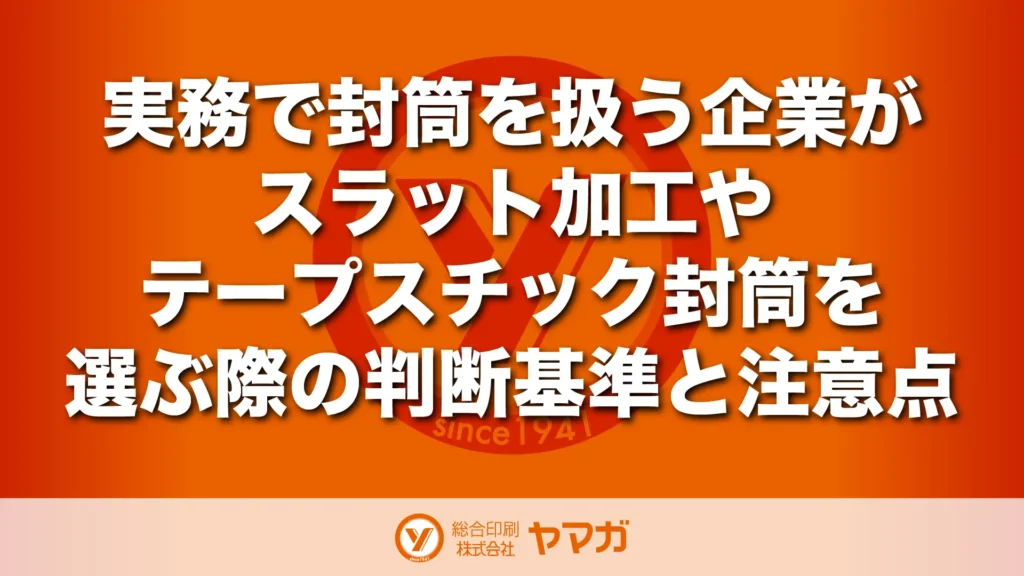
企業が日常業務の中で使用する封筒を選定する際には、単なる見た目や価格だけでなく、業務の流れや作業効率、保管環境、顧客との信頼構築といったさまざまな観点から判断されます。特にスラット加工やテープスチック加工といった口糊の仕様については、その違いが使い勝手や品質に直結するため、企業の担当者は慎重に選んでいます。印刷会社では、こうした判断が円滑に進むよう、用途に合わせた情報提供や提案を行う役割を担っています。
まず、企業が封筒を選ぶ際に重視するポイントの一つが「封緘作業のしやすさ」です。日々大量の書類を封入し発送する業務では、封を閉じる動作にかかる時間や手間は無視できないコストとされます。この観点からスラット加工は高く評価されています。剥離紙をはがして貼り付けるだけというシンプルな動作で済むため、封入作業がスムーズになり、作業者への負担も軽減できます。加えて、貼る位置を微調整できる点も、作業の安心感につながっています。
一方で「完全封緘が求められる業務」では、テープスチック加工が好まれる傾向があります。たとえば、金融機関や医療機関、法律事務所など、情報漏洩のリスクを極力抑えたい業種では、封をしたあとの開封痕が確実に残る仕様が望まれます。テープスチック加工は一度貼ると剥がすのが困難なため、開封した事実がすぐにわかり、改ざん防止の視点でも安心感があります。加えて、保管期間が長くなる文書の封入にも適しているため、保存用として使われるケースが多く見られます。
次に「保管環境」も大きな判断材料となります。例えば、倉庫や事務所の書棚で一定期間保管するだけであれば、スラット加工でも問題はありませんが、高温や湿気の多い場所に保管される場合は、粘着剤の劣化が心配されます。テープスチック加工の封筒は、そうした環境でも粘着性能を維持しやすいため、より安心して使用できると判断されます。印刷会社では、こうした使用環境についてもヒアリングを行い、粘着剤の種類や加工方法を最適化するよう対応しています。
もう一つのポイントとして「封入物の重さや量」も挙げられます。封筒に入れる書類が多かったり厚かったりすると、封緘後に封筒の口にテンションがかかりやすくなります。このとき、粘着力が不十分だと、郵送途中で封が開いてしまうリスクがあります。スラット加工は軽量〜中程度の封入物に適しており、逆に重量物や厚みのある書類には、より高い接着力を持つテープスチック加工の方が適しています。印刷会社では封入物の構成まで確認し、仕様に応じた封筒を設計・提供することも一般的です。
封筒選びにおいて、実は「誤封や封入ミスのリスク管理」も見落とせない視点です。スラット加工は一度貼っても比較的やわらかい粘着性で、貼り直しができる余地があります。作業中に間違いに気づいた場合、いったん封を開けて入れ直すという対応が可能な場合もあります。一方でテープスチック加工では、貼り直しが困難なため、ミスがあると封筒を一からやり直さなければならないというデメリットもあります。このため、作業工程において十分な確認フローがある企業であればテープスチックでも安心ですが、ヒューマンエラーが起こりやすい環境であれば、扱いやすいスラット加工の方が実務的といえます。
最後に「コストとのバランス」も企業の選択に大きく関わります。テープスチック加工はその機能性ゆえに、加工費がやや高くなる傾向があります。対してスラット加工は比較的コストを抑えられ、予算内でより多くの封筒を準備したいというニーズに応えやすい仕様です。印刷会社では、必要な封筒の機能と使用量、保管期間、使用シーンを総合的に判断しながら、どちらの加工が適しているかをわかりやすく説明し、コスト面でも納得できる提案を行います。
このように、スラット加工とテープスチック加工にはそれぞれの強みと注意点があり、企業がどのような用途で封筒を使うのかによって最適な選択肢が変わってきます。印刷会社では、お客様の業務フローや封入物の種類、予算、セキュリティへの意識までを丁寧に伺いながら、単なる封筒製造ではなく、業務全体の効率や安心感に貢献できる製品づくりを心がけています。
次のブロックでは、スラット加工やテープスチック加工の封筒が今後さらに求められると予測される背景や、印刷会社の視点で考えるニーズの変化について解説していきます。
スラット加工やテープスチック加工の封筒が今後さらに求められると予測される背景
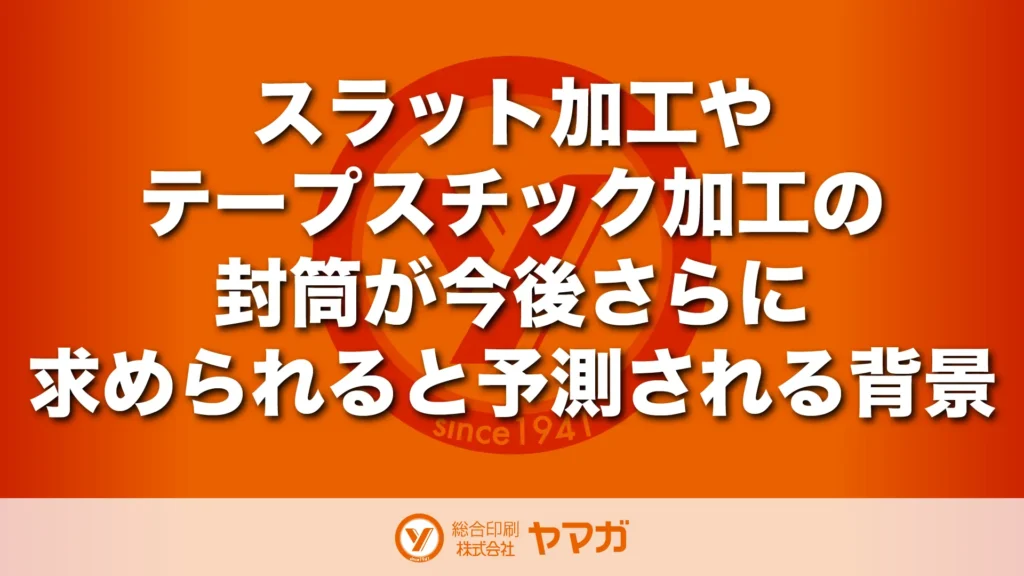
スラット加工やテープスチック加工を施した封筒は、これまでも業務効率化や封入作業の省力化に貢献してきましたが、ここ数年でその需要はさらに広がりを見せています。印刷会社の現場では、依頼される封筒の仕様の中に、こうした粘着加工を含むものが確実に増加しているという実感があります。そしてその背景には、単なる封緘方法としての利便性を超えた、社会全体の業務の変化や意識の変化が見え隠れしています。
まず大きな流れとして挙げられるのが、非対面コミュニケーションの定着です。かつては書類の手渡しや、対面での確認が主流だったビジネスの現場でも、現在では郵送によるやり取りやオンライン契約の一部として原本を郵送するケースが増えています。その際に使われる封筒には、しっかりと封ができて、改ざんや情報漏洩のリスクが少ないことが求められます。スラット加工やテープスチック加工の封筒は、こうしたニーズに応えやすい構造であるため、導入する企業が増えているのです。
また、労働環境の見直しが進む中で、作業の効率化や人件費の削減といったテーマも重要視されています。封入作業に時間を取られてしまう業務フローは見直される傾向にあり、「できるだけ早く、確実に、簡単に封ができる」加工が求められています。この観点ではスラット加工が特に注目されており、短時間で多くの封筒を封緘できることから、発送業務の現場においては高い評価を受けています。加えて、非熟練の作業者でも簡単に封緘できるという点は、人材の多様化が進む中でますます大きな利点となっていくでしょう。
テープスチック加工については、社会的なコンプライアンス意識の高まりとともに、重要書類の送付に対して一層の信頼性が求められる中での需要増加が見込まれます。とくに個人情報や機密文書の取り扱いが厳格化されるなかで、封筒がしっかりと封緘されていて、かつ誰が見ても未開封であると分かる構造が望まれています。テープスチックの封筒はまさにその条件を満たすものであり、印刷会社でも「安心して使える封筒」としての位置付けが定着しています。
加えて、封筒そのものをブランディングの一環として活用する動きも見逃せません。たとえば、開封時の手触りや印象までをデザインとして設計し、送る相手に安心感や信頼感を与える工夫をする企業が増えています。そのため、封のしっかりした加工を選ぶことは、単なる実用性の追求にとどまらず、企業の姿勢を示す手段とも言えるようになってきました。封筒はただの容れ物ではなく、第一印象を伝える重要なメッセージツールになってきているのです。
印刷会社の視点から見ても、こうした社会や業務の変化に呼応して封筒への要望はより高度かつ多様になってきており、それに対応するための提案力や製造技術の更新が必要不可欠になっています。スラット加工やテープスチック加工の選定ひとつにしても、コスト、作業効率、安全性、保管性、ブランドイメージなど複数の要素が絡み合ってくるため、それぞれの企業に合わせた柔軟な設計が求められています。印刷会社では、それぞれの加工方法の機能だけでなく、どんな背景で使われ、どう役立てられるのかという部分まで視野に入れた提案がこれからますます大切になっていくと考えています。
今後、業務のペーパーレス化がさらに進んでいく中でも、すべてが電子化されるわけではなく、物理的な書類を必要とする場面は依然として存在し続けます。だからこそ、その「紙で届ける」という行為に、より意味や価値を持たせることが必要になってきます。スラット加工やテープスチック加工の封筒は、その過程で欠かせない存在として、これからも進化を続けながら活用されていくことが期待されます。
まとめ
封筒の口に施されるスラット加工やテープスチック加工は、日常的に使うものの中でも意識されにくい存在かもしれませんが、実際には封筒そのものの使いやすさや信頼性を大きく左右する重要な要素です。印刷会社の現場では、ただ紙に糊をつけるだけではない、使用環境や保管期間、封入する書類の内容に応じた最適な加工方法の選定が求められており、その背景には、企業ごとの業務フローや社会全体のニーズの変化があります。
スラット加工は、作業効率や封緘のしやすさという面で優れており、日々の発送業務や大量封入が求められる現場で活躍しています。一方でテープスチック加工は、強粘着でしっかりとした封緘が可能で、長期保存やセキュリティが必要とされる重要書類の送付に非常に適しており、どちらもそれぞれの用途に応じて使い分けられています。
封筒のサイズや紙質、印刷の仕様によっても粘着加工との相性は異なり、たとえ加工方法が優れていても、全体のバランスがとれていなければ使用感や耐久性に差が出てしまいます。そのため印刷会社では、単に加工を施すだけではなく、全体設計の中での調整や確認を大切にしています。印刷方式やインキの選定、デザインレイアウト、仕上げの品質管理までを含めた一連の工程が、高品質な封筒を実現するために欠かせない工程です。
また、封筒を扱う企業側にとっては、封緘作業のしやすさや誤封のリスク、保管期間と環境、予算など、さまざまな観点から適切な封筒を選ぶことが業務全体の流れに直結するため、封筒選びそのものが業務改善の一部ともなり得ます。印刷会社がその判断に寄り添い、細やかな提案を行うことで、より安心して業務を進められる環境が整っていきます。
そして今後、書類の取り扱いがますます厳格になる社会的流れや、非対面でのやり取りが一般化する中で、封筒に求められる役割もより高度なものへと変わっていきます。スラット加工やテープスチック加工といった粘着仕様は、そうした変化に対応する有効な手段として、今後も幅広い場面で必要とされることでしょう。
印刷会社としては、それぞれの加工方法が持つ特性を理解し、お客様の業務の背景や運用環境に即した製品を提供することが、封筒づくりの中でも特に大切な姿勢であると考えています。見えない部分にこそ丁寧さが宿る、そんな視点で加工された封筒が、送り手と受け手の信頼をつなぎ続ける一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
よくある質問Q&A
-
スラット加工とはどのような封筒加工方法ですか?
-
スラット加工とは、封筒のベロ部分にあらかじめ粘着剤が塗布され、その上に剥離紙(セパレーター)が貼られている加工方法です。使用時にはこの剥離紙をはがすだけで粘着面が露出し、簡単に封をすることができます。水や別の道具を使う必要がなく、手軽に封緘ができるため、大量発送や業務用の封筒として多くの企業で利用されています。接着力も比較的安定しており、作業効率を重視する現場に向いています。
-
テープスチック加工とはどのような特徴を持つ加工方法ですか?
-
テープスチック加工は、封筒のベロに両面テープがあらかじめ取り付けられており、使用時に剥離紙をはがすことで強力な粘着力を発揮する封緘方法です。この加工はスラット加工と似ていますが、テープ自体の密着力が非常に高く、長期間にわたって接着力を維持できる点が特徴です。契約書や医療記録などの重要書類の送付や保管に向いており、セキュリティを重視する場面でよく利用されます。
-
スラット加工とテープスチック加工の違いは何ですか?
-
両者の違いは主に粘着力と使用場面にあります。スラット加工は比較的穏やかな粘着性を持ち、貼り直しも可能な場合がありますが、長期保管や密閉性にはやや弱い傾向があります。一方で、テープスチック加工は非常に高い接着力を誇り、一度貼ると剥がすのが難しく、開封の痕跡も残ります。そのため、セキュリティ性や長期保存を重視する用途にはテープスチックが適しています。
-
スラット加工はどのような用途に向いていますか?
-
スラット加工は、日常的な書類の郵送やDM発送、大量の書類処理を短時間で行う業務に適しています。剥離紙をはがすだけで封緘できるため、封入作業が効率的に行えるのが利点です。作業のしやすさとコストのバランスが良いため、書類の回転が早い現場や、一時的な保存で済む資料の封入などに向いています。
-
テープスチック加工はどのような業種で利用されていますか?
-
テープスチック加工は、セキュリティ性や長期保存が求められる業種で広く使われています。たとえば、金融機関や医療機関、法律事務所、自治体などでは、個人情報や機密書類を扱う機会が多く、封筒の密閉性が重視されるため、テープスチック加工が採用されています。開封の痕跡が明確に残る点でも信頼があり、安心して使える封筒として評価されています。
-
封筒のサイズと加工方法に相性はありますか?
-
あります。封筒が大きくなるとベロの面積も広がるため、封緘時の力が強くかかり、密着性がより重要になります。そのため、大型封筒ではテープスチックのように強粘着性を持つ加工が適しています。一方、長形3号などの定形サイズであれば、スラット加工でも十分な封緘が可能で、コストや作業性の面からも好まれます。サイズによって加工方法を使い分けることが推奨されます。
-
封筒の紙質は加工方法の選定に影響しますか?
-
はい、大きく影響します。紙質が滑らかすぎると粘着剤が定着しにくくなり、粘着不良の原因になります。逆に粗すぎる紙は粘着剤の浸透が不均一になることもあります。スラット加工ではインキの油分や紙の表面性状が接着力に影響することもあるため、紙質に応じて粘着剤を選ぶ必要があります。テープスチックは紙質に対する許容範囲がやや広く、安定した接着を得やすい傾向があります。
-
加工された封筒の印刷時に注意することはありますか?
-
はい、特にベロ部分には注意が必要です。粘着剤が塗布される位置には印刷を避ける必要があり、インキが粘着剤の接着を妨げる場合があるからです。特に濃色インキやベタ塗りは影響が大きく、加工不良や封緘不良の原因となります。印刷会社では、あらかじめ印刷禁止エリアを設け、デザイン段階から加工と干渉しないよう設計することが推奨されています。
-
スラット加工封筒の保管期限はありますか?
-
あります。スラット加工封筒に使われている粘着剤は時間とともに粘着力が弱まることがあるため、製造から半年〜1年以内での使用が推奨されています。直射日光や高温多湿を避け、風通しのよい場所で保管することが品質を保つポイントとなります。印刷会社では納品時に使用期限の目安を伝えることも一般的です。
-
テープスチック加工封筒の保管性はどうですか?
-
テープスチック加工は粘着剤の劣化が少なく、長期保管に強い加工方法とされています。適切な保管環境であれば1年以上保管しても粘着力が落ちにくいため、事前に大量に製造し必要に応じて順次使用するような運用にも適しています。特に長期保存が前提の文書や、保管期限の長い書類送付に向いているとされています。
-
開封の痕跡が残る封筒にはどちらの加工が適していますか?
-
開封の痕跡を残すことでセキュリティ性を高めたい場合は、テープスチック加工が適しています。この加工は一度封をすると簡単には開けられず、開けようとすると封筒が破損する構造になっているため、途中開封があった場合でも目視で確認しやすくなります。未開封であることを証明する手段としても活用されており、信頼感のある発送が求められるシーンに最適です。
-
企業が封筒の粘着加工を選ぶときの判断材料は何ですか?
-
企業は封緘作業の効率、封入物の重さ、封緘の確実性、保管期間、予算などを総合的に判断して加工方法を選定します。たとえば大量発送を短時間で行う業務ではスラット加工が好まれ、情報漏洩のリスクを避けたい場合はテープスチックが選ばれます。印刷会社では用途や運用にあわせた仕様を提案し、最適な封筒を設計することが重要となっています。
-
粘着加工が郵送物の安全性に与える影響はどのようなものですか?
-
粘着加工の種類によって、輸送中の封の保持力や改ざん防止効果が異なります。粘着力が弱ければ輸送中に封が外れてしまう恐れがありますが、スラットやテープスチック加工では高い密着性を維持できるため、安心して発送できます。特にテープスチックは改ざんや無断開封の防止にも強く、信頼性を重視する企業の間で高く評価されています。
-
テープスチック加工のコストはスラット加工より高いのですか?
-
一般的に、テープスチック加工のほうが加工費が高くなる傾向があります。使用する粘着材や製造工程が複雑であることが主な理由です。そのため、封筒の使用量が多い場合や予算が限られている場合は、コストとのバランスを考慮してスラット加工を選択するケースもあります。印刷会社では用途に応じた最適なコスト提案も含めたサポートを行っています。
-
スラット加工とテープスチック加工の今後の需要はどうなると予想されていますか?
-
非対面での業務や個人情報の取扱いが重視される現在、封筒に求められる機能はより高度になっています。その中で、スラット加工は作業の効率化に貢献する加工として、テープスチック加工は信頼性の高い封緘手段として、それぞれの用途で需要が高まると予測されています。印刷会社でも、より多様なニーズに対応できるように加工技術の向上と提案力の強化が進められています。







