線数とは何か?印刷物の網点のきめ細かさを理解し最適な線数を選ぶための徹底解説
2025.10.24
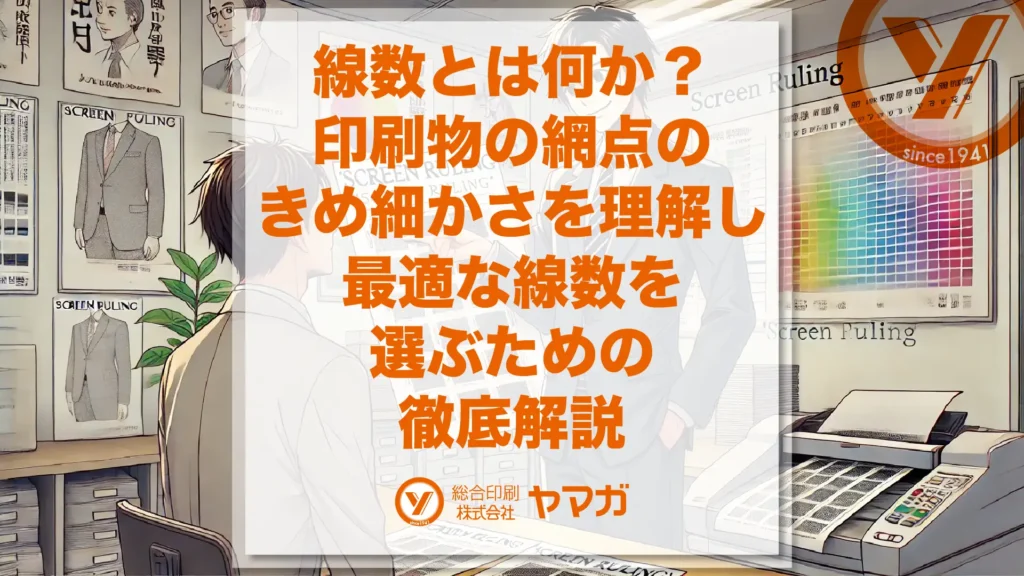
印刷物を手に取ったとき、「このカタログは写真がとてもきれいだな」と感じたり、「このチラシは少し粗い印象があるな」と思ったことはありませんか。その違いを生み出している要素のひとつが「線数」です。線数とは、印刷物に使われる網点の細かさを示す数値で、1インチあたりに並ぶ網点の数を意味します。たとえば175lpiという場合、1インチに175個の網点が入っていることになり、その分だけきめ細やかな表現が可能になります。線数は印刷の美しさを左右するだけでなく、コストや印刷方法、用紙の種類とも深く関わっており、理解しておくことで印刷物の完成度を大きく高めることができます。
線数が高いほど写真やグラデーションは滑らかに再現され、特に高級カタログや写真集では175lpiや200lpiといった高精細な線数が用いられます。一方で、チラシやパンフレットなど実用性を重視する印刷物では133lpiが多く採用されており、新聞のようにスピードと効率を求める場合には85lpiから100lpiといった低めの線数が選ばれます。このように線数の選び方は印刷物の目的や紙の種類によって大きく変わり、ただ数値を高くすればよいというものではありません。
また、線数は印刷方式によっても考え方が異なります。オフセット印刷では133lpiや175lpiといった具体的な基準が存在しますが、デジタル印刷ではdpi(解像度)という概念で品質が語られることが多くなっています。さらに、FMスクリーンという新しい技術も登場し、従来の網点配置にとらわれない表現が可能になりつつあります。こうした進化によって、線数の概念は従来以上に柔軟に活用できるようになっています。
もちろん、線数を選ぶ際にはコストの問題も無視できません。高い線数を使えば美しい印刷が可能になりますが、その分だけ印刷の難易度が上がり、調整や用紙の選択によって費用が増えることもあります。逆に線数を抑えれば効率的で安価に印刷できますが、仕上がりの繊細さは劣る場合があります。そのため、企業担当者にとって線数の知識は「コストを抑える工夫」と「効果的な投資」を見極める判断基準となります。
さらに、印刷データを作成する段階でも線数を意識することが大切です。画像解像度を線数に合わせて設定する、RGBからCMYKに変換しておく、フォントをアウトライン化するなど、入稿前の基本的な準備を整えることで、線数を活かした仕上がりを実現できます。そして、最終的な印刷前には校正刷りを確認することで、網点の見え方や質感が期待通りかどうかをしっかりとチェックすることも重要です。
線数という言葉は少し専門的に聞こえるかもしれませんが、その理解があるかないかで印刷物の仕上がりは大きく変わります。印刷会社とのやり取りをスムーズにし、データ制作の精度を高め、コストと品質のバランスを取りながら目的に合った印刷物を作り上げるために、線数の知識は必ず役立ちます。本記事では、その基本から実務への応用までをわかりやすく解説し、一般の読者でもすぐに活かせる知識をまとめてご紹介していきます。
- 線数とは何かを初心者にもわかりやすく解説、印刷に欠かせない基本!
- 線数の単位 lpiが示す意味と網点の数値が印刷物にどのような影響を与えるか
- 線数と網点の見え方の関係、仕上がりの美しさとの違い!
- 代表的な線数175lpiや133lpiなどの数値が実際にどのように使われるのか
- 線数が高すぎると網点がつぶれるリスクがある理由と避けるための工夫
- 用紙の種類ごとに最適な線数の選び方、印刷物の仕上がりを高める方法!
- オフセット印刷やデジタル印刷における線数の考え方と印刷方式による違い
- 線数と印刷コストの関係をわかりやすく説明
- 線数を選ぶときに考慮すべき印刷データ作成や入稿時の注意点
- 線数を理解することで印刷物をより魅力的に仕上げるための知識
- まとめ
- よくある質問Q&A
線数とは何かを初心者にもわかりやすく解説、印刷に欠かせない基本!
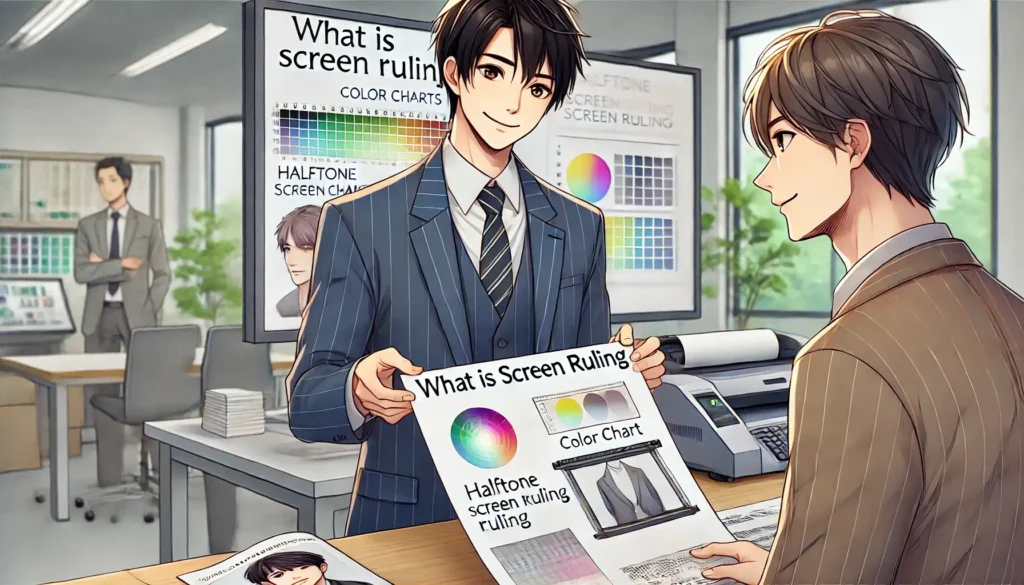
印刷という言葉を耳にすると、多くの人は本やチラシ、雑誌やポスターなど身近な紙媒体を思い浮かべるかと思います。普段から目にしている印刷物には、それぞれに特有の美しさや質感があります。その見え方を大きく左右する要素のひとつが「線数」と呼ばれるものです。線数は、印刷において網点の細かさを示す指標であり、仕上がりの印象や質感に深く関わっています。しかし、専門的な用語のため一般の人にはなじみが薄く、どういう意味を持っているのか分かりにくい部分でもあります。そこでここでは、初心者でも理解できるように、線数という言葉の意味や役割をやさしく解説していきます。
まず、印刷物がどのように作られているかを簡単に振り返ってみましょう。フルカラー印刷の場合、人間の目に見える色を再現するために「CMYK」と呼ばれる4色のインキを使っています。シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)の組み合わせで色を再現するのですが、インキは液体なので、ただ塗るだけでは微妙な色の濃淡やグラデーションを表現できません。そこで考え出されたのが「網点」という仕組みです。網点とは、色を小さな点の集まりとして表現し、その点の大きさや密度によって濃淡を表す技法です。たとえば淡い色を出したいときは小さな点をまばらに配置し、濃い色を表現したいときは大きな点を密集させて並べます。この点の集まりが人の目には自然な濃淡に見えるため、写真やイラストを美しく印刷できるわけです。
ここで重要になるのが線数という考え方です。線数とは、1インチ(25.4mm)の幅の中に並んでいる網点の数を表す数値で、通常は「lpi(line per inch)」という単位で表されます。たとえば「175lpi」と表記されている場合、1インチの幅に175個の網点が並んでいるということを意味します。つまり、線数の値が大きいほど網点は細かくなり、人の目には点が目立ちにくくなって、より滑らかで精細な仕上がりになります。逆に線数が低いと点の粒が大きく見え、粗い印象になってしまいます。このことから、線数は印刷物の美しさや読みやすさを決める非常に大切な要素だと言えます。
ただし、線数が高ければ高いほど良いという単純なものではありません。線数を上げすぎると、網点同士が近くなりすぎてインキが紙に広がった際につぶれてしまい、かえって絵柄がつぶれたように見えることがあります。これを「ドットゲイン」や「網点のつぶれ」と呼び、印刷現場では避けるべき問題のひとつとされています。そのため、どのくらいの線数を選ぶべきかは、印刷物の種類や用途、そして使用する用紙の特性によって変わってくるのです。
たとえば、美術書や写真集のように非常に細かい表現や繊細な色合いを求められる印刷物では、175lpiや200lpiといった高い線数が使われることがあります。これにより、写真の質感や微妙な陰影が滑らかに表現され、作品の魅力を引き出すことができます。一方で、新聞や大量に印刷されるチラシなどは、コストやスピードを重視するために線数を下げる場合があります。新聞などでは一般的に85lpiや100lpi程度が使われており、多少粗さがあっても情報を伝える目的には十分だからです。このように、印刷物の目的や用途に応じて適切な線数を選択することがとても大切になります。
また、用紙の違いも線数の選択に大きな影響を与えます。表面が滑らかで光沢のあるコート紙では細かい網点がきれいに再現できるため、高い線数を用いることができます。反対に、ざらつきのある上質紙や新聞紙のような非塗工紙ではインキが滲みやすいため、あまり高い線数を使うと網点がつぶれてしまうリスクがあります。そのため、こうした紙では低めの線数が選ばれるのです。このように、線数の選択には印刷方式や紙質といった複数の要因が絡み合っています。
初心者にとっては「線数」という言葉が難しく聞こえるかもしれませんが、身近な例を挙げると理解しやすくなります。たとえばデジタル画像の「解像度」に似た考え方だと思うとわかりやすいでしょう。スマートフォンで撮った写真の解像度が高いほど画面に表示したときに細かい部分まできれいに見えるように、印刷物においても線数が高いほど網点が細かくなり、きれいに見えるというイメージです。ただし、先ほど説明したように解像度と違って、紙の種類やインキの性質も関わってくるため、一概に「高い線数が良い」とは言えないところが大きな違いです。
線数という概念を知ることで、私たちは普段目にしている印刷物を新しい視点で見ることができるようになります。たとえば、同じチラシでも線数が高いものは写真の色や質感がより鮮やかに見え、低い線数のものはシンプルで印刷コストが抑えられていることがわかるかもしれません。印刷物を企画したり、印刷会社に依頼したりする際にも、この知識を持っていることで、目的に合わせた判断がしやすくなるのです。
このように、線数は印刷物における基本的かつ欠かせない概念であり、網点のきめ細かさを左右する大切な指標です。初めて聞く方にとっては少し難しく感じられるかもしれませんが、網点が点の集まりであること、線数がその密度を表す数値であることを理解すれば、印刷物の仕組みや仕上がりの見え方を身近に感じられるはずです。これから先、さらに具体的な数値の意味や、実際にどのような印刷物にどの線数が使われているのかを知ることで、より実務的に役立つ知識へとつながっていきます。
線数の単位 lpiが示す意味と網点の数値が印刷物にどのような影響を与えるか

線数という言葉を理解する上で欠かせないのが、「lpi」という単位です。lpiは「line per inch」の略で、日本語では「1インチあたりの線数」と表現されます。1インチは25.4ミリメートルですから、その幅の中にどれくらいの網点が並んでいるかを数値で表したものが線数です。この数値を知ることで、印刷物の網点の細かさや仕上がりの印象をイメージしやすくなります。
たとえば「175lpi」という表記を見たとしましょう。これは1インチの幅に175個の網点が規則正しく並んでいるという意味になります。つまり、数値が高ければ高いほど網点は細かく配置されることになり、人の目には粒が見えにくくなって滑らかな印象を与えます。逆に「85lpi」のように数値が低ければ、点の粒が大きくなり、肉眼でもはっきりと確認できる粗い仕上がりになります。このように、lpiの数値は印刷物の質感や見え方を左右する、とても重要な指標なのです。
数値の違いによって印刷物にどのような変化が現れるのか、もう少し具体的に考えてみましょう。まず、線数が高い場合には写真やイラストの再現度が上がり、繊細な色合いや細部まで美しく表現されます。写真集やカタログなど、ビジュアルを重視する媒体では高めの線数が採用されることが多くなります。逆に、線数が低い場合には粒状感が強く出るため、細かい階調表現には不向きです。しかし、線数を抑えることで印刷の安定性が増し、スピードやコストを重視する新聞やチラシには適しているという利点があります。つまり、線数の高低には一長一短があり、用途や目的によって適切に選ぶことが大切なのです。
また、lpiという数値は印刷の見た目だけでなく、印刷機や用紙との相性とも関わっています。光沢のあるコート紙やアート紙のように表面が滑らかな紙は、インキがにじみにくいため高い線数を使っても網点がきれいに再現されます。そのため200lpiや250lpiといった非常に細かい線数を適用できる場合もあります。一方、新聞紙や上質紙のように表面がざらついている紙では、インキが紙の繊維に広がりやすいため、細かすぎる線数を使うと点がつぶれてしまいます。そのため100lpi前後に抑えるなど、用紙に合わせた線数選びが必要になります。
さらに、lpiの数値は印刷物の雰囲気を変える役割も果たしています。高い線数では滑らかで繊細な表現が可能ですが、場合によっては硬い印象になりがちです。逆に低い線数は粗さが強調されますが、独特の力強さや勢いを感じさせる仕上がりにもなります。そのため、デザインやコンセプトによっては意図的に低い線数を選ぶケースもあります。たとえばポスターやビジュアルアートなどでは、粒の大きさをあえて見せることでインパクトを与える表現手法として活用されることもあります。
このように、lpiの数値は単に「細かいか粗いか」を示すだけではなく、印刷物の仕上がり全体に深く関わっています。線数が高ければ必ず良いというものではなく、印刷の目的、紙の種類、仕上がりのイメージなどを考慮して最適な数値を選ぶ必要があります。もし一般の人が印刷会社にチラシやパンフレットを依頼する際にも、このlpiという数値を理解しておくと、印刷会社との打ち合わせがスムーズになります。「高級感を出したいので175lpi程度でお願いしたい」や「コストを抑えたいので133lpiで十分です」といった具体的な相談ができるようになるからです。
また、印刷データを作成するデザイナーにとってもlpiの理解は欠かせません。デジタルデータの解像度と線数の関係を考えながらデータを作らないと、印刷した際に粗く見えてしまったり、逆に不要に容量が大きくなったりする可能性があります。よく使われる目安として、画像解像度は線数の2倍程度が望ましいとされています。たとえば175lpiの線数で印刷する場合には350dpi程度の解像度が推奨されるわけです。この基準を知らずに低解像度の画像を配置してしまうと、仕上がりがぼやけてしまう原因になります。逆に過剰に高い解像度の画像を使っても印刷結果が向上するわけではなく、処理が重くなるだけなので注意が必要です。
印刷の現場では、lpiという数値が会話の中で頻繁に登場します。「今回のカタログは175lpiで進めましょう」や「新聞折込用なので85lpiにしておきます」といったやり取りは日常的です。このやり取りの裏側には、紙の種類や用途、仕上がりイメージを踏まえた判断が込められています。だからこそ、初心者の方もlpiという単位を知っておくことで、印刷という世界がより理解しやすくなり、実際に印刷物を依頼する際にも納得感を持って選択できるようになるのです。
総じて言えるのは、lpiは印刷の品質を左右する数値でありながら、同時にコストや実用性とのバランスも考えなければならない指標だということです。デザインの美しさ、読みやすさ、紙の特性、印刷機の能力、そして予算や納期など、さまざまな条件が重なり合って最終的な線数が決まります。その意味で、lpiという単位を理解することは、印刷を単なる作業ではなく「表現」として捉える第一歩にもなるのです。
線数と網点の見え方の関係、仕上がりの美しさとの違い!
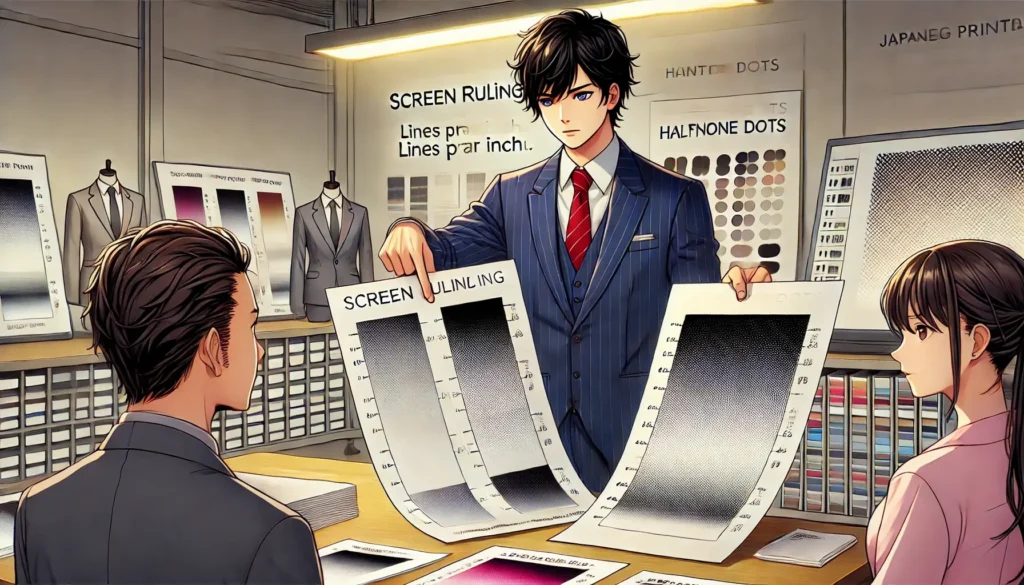
印刷物を目にしたときに「きれいだな」と感じるか「少し粗いな」と思うかは、人それぞれの感覚にもよりますが、その多くは線数と網点の見え方によって決まります。線数は網点の数を示す数値であることはすでに触れましたが、ここでは実際にその数値がどのように見え方に影響を与えるのかを、もう少し具体的に解説していきます。
網点とは、小さな点の集合で濃淡を表す方法です。遠くから見ると点の集まりが写真やイラストに見えるのですが、近づいてよく観察すると点が規則正しく並んでいることがわかります。線数が低いと点が大きく配置されるため、近づかなくても点が見えやすく、全体的にざらついたような印象を与えます。逆に線数が高いと点が細かく並ぶため、肉眼では粒がほとんど見えず、滑らかで精細な仕上がりに見えるのです。この違いが「網点の見え方」として印刷物の質感に直結します。
たとえば、新聞を思い浮かべてみましょう。新聞は大量に早く印刷する必要があり、紙質もインキを吸いやすい非塗工紙が使われています。そのため線数は85lpiから100lpi程度と比較的低く設定されています。結果として文字や写真をよく見ると点が粗く、写真はややざらざらとした質感になります。しかし新聞に求められているのは高級感や美術的な再現性ではなく、情報を早く安価に届けることです。その目的には低い線数でも十分対応できているのです。
一方、写真集や高級カタログなどを手に取ると、印刷の滑らかさに驚くことがあります。これは175lpiや200lpiといった高い線数が使われているためで、写真のグラデーションや人物の肌の質感が自然に再現されます。粒が目立たないため、まるで本物を見ているかのように感じられるのです。線数が高いほど繊細な表現が可能になり、見た人に高級感や信頼感を与える効果もあります。
また、網点の見え方は距離によっても変化します。印刷物を手元で読む場合と、ポスターのように数メートル離れて眺める場合では、同じ線数でも印象が違って感じられます。遠くから見ると低い線数でも粒が気にならず、十分にきれいに見えることがあります。逆に手元でじっくり読むパンフレットや雑誌は、粒が見えやすいのである程度高い線数が必要になります。つまり線数は、用途だけでなく想定される閲覧距離にも関係しているのです。
さらに、網点の見え方には人間の目の特性も関わっています。人間の目は小さな点をある程度の距離から見ると、自然にぼかして認識する働きがあります。この性質を利用して、網点を組み合わせて色や濃淡を表現しているのが印刷の仕組みです。線数が低いと人の目でも点の大きさを認識してしまうため粗く見えますが、線数が高ければ目のぼかし機能によって点が融合して見え、自然な色合いや階調として感じられるのです。このように、人間の視覚と線数の関係を理解すると、なぜ線数が印刷品質に大きな影響を与えるのかがよくわかります。
ただし、線数を高くすれば必ず美しい印刷が得られるというわけではありません。網点が細かすぎるとインキが紙に広がる影響を受けやすくなり、逆に点がつぶれてしまうことがあります。これにより濃淡の差が失われ、べったりとした印象になることもあります。つまり、仕上がりの美しさは単純に線数だけで決まるものではなく、用紙やインキの性質、印刷機の性能などさまざまな要素のバランスによって左右されるのです。
また、線数と見え方の関係を理解しておくと、印刷データの作成にも役立ちます。たとえば、解像度の低い画像を高い線数で印刷すると、画像が粗く引き伸ばされたように見えてしまいます。これは、網点が細かくても元のデータに情報が足りないためです。逆に十分な解像度を持つ画像を使えば、線数に見合った滑らかな仕上がりを得ることができます。このことから、線数はデータ解像度との関係も考慮しながら選ぶことが大切だといえます。
具体的な印象を例に挙げると、133lpiの印刷は一般的なカタログや雑誌でよく使われ、落ち着いたきれいさを持ちながらコストとのバランスも取れています。175lpiは高級カタログや写真集で多く使われ、より繊細でなめらかな表現が可能です。そして新聞のように85lpi程度になると、粗さは目立つもののスピードとコストで大きなメリットがあります。つまり「美しさ」という観点で線数を考えるときには、必ずその印刷物の目的や使用シーンと一緒に捉える必要があるのです。
このように、線数と網点の見え方は切っても切れない関係にあり、その違いが印刷物の美しさに直結しています。線数が低いと粒状感が残り力強さやシンプルさを感じさせ、高いと繊細で滑らかな印象を与えることができます。印刷の仕組みを知らなければ気づかないかもしれませんが、実は日常で目にする印刷物の質感の差は、この線数という数値によって大きく変わっているのです。
代表的な線数175lpiや133lpiなどの数値が実際にどのように使われるのか
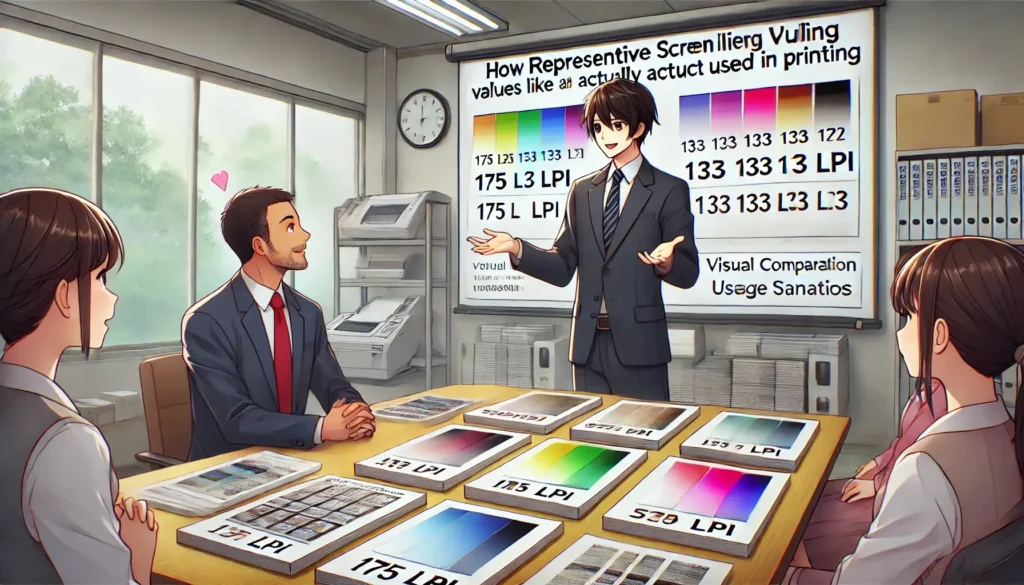
印刷の世界でよく耳にする線数には、いくつか代表的な数値があります。その中でも特に知られているのが175lpiや133lpiです。これらの数値は単なる目安ではなく、印刷物の種類や用途に応じて実際に幅広く活用されています。ここでは、それぞれの線数がどのような場面で使われているのかを具体的に紹介していきます。
まずは175lpiについて見ていきましょう。175lpiは「高精細な印刷」と言われることも多く、雑誌や高級カタログ、写真集など、特にビジュアルを重視する印刷物に採用されることが多い数値です。線数が高いため網点が細かく、写真の肌の質感や風景のグラデーションをより自然に再現することができます。読者がページをめくったときに「きれいだな」と感じやすいのは、この線数が持つ滑らかさによるものです。実際に商業印刷の現場でも標準的な高精細印刷の基準として使われており、印刷会社の説明でも「このカタログは175lpiで仕上げています」と案内されることが多いです。
一方で、133lpiはコストと品質のバランスが取れた線数として広く利用されています。一般的な企業のパンフレットや販促用のチラシ、定期的に発行される雑誌などでは133lpiがよく使われます。この数値は175lpiほどの精細さはありませんが、十分にきれいな印刷が可能でありながら、印刷の安定性やコスト面でも優れています。そのため、多くの企業がマーケティングツールとして利用する印刷物には、この133lpiが採用されるケースが非常に多いのです。コート紙やマットコート紙のような比較的表面が滑らかな紙との相性も良く、実用性が高い線数だと言えるでしょう。
さらに、新聞などで使われるのは85lpiから100lpiといった低めの線数です。新聞紙はインキを吸収しやすく、細かい網点を表現することが難しいため、高い線数を使うと点がつぶれてしまいます。そのため意図的に低い線数を選び、粗くても情報が伝わることを優先しています。結果として写真は粒状感が強く出ますが、速報性や大量印刷の効率を考えると合理的な選択となります。
こうした代表的な数値を比較すると、それぞれの印刷物の性格が浮かび上がってきます。175lpiは「美しさ」を重視する場面、133lpiは「実用性」と「コストバランス」、85lpiは「スピードと効率」といった具合に、線数は単なる数値ではなく、印刷物の目的を象徴する選択肢でもあるのです。
また、近年では200lpi以上の高精細印刷も登場しています。特にアート関連の出版物や高級ブランドのカタログなど、ビジュアルの印象が売上やブランド価値に直結する分野では200lpiや250lpiが使われることもあります。こうした超高精細印刷は、紙の質や印刷機の性能が十分に対応できる場合に限られますが、仕上がりは驚くほど繊細で、美術作品を再現する際には欠かせない技術となっています。
ただし、線数を高くすればするほど必ずしも良いというわけではなく、用途やコストとのバランスを見ながら選択される点が印刷の難しさでもあります。たとえば、全国に大量に配布するチラシに200lpiを適用すると、確かにきれいに見えるものの印刷コストが大幅に上がってしまい、費用対効果が低くなってしまいます。逆に高級カタログに133lpiを使ってしまうと、ビジュアルの魅力が半減し、ブランドイメージにも影響が出かねません。こうした判断を適切に行うために、印刷業界では175lpiや133lpiといった代表的な数値が基準として定着しているのです。
さらに、印刷データを準備するデザイナーにとっても、どの線数で印刷されるのかを知っておくことは重要です。133lpiで印刷されると分かっていれば、必要な画像解像度はおよそ266dpi以上を用意すれば十分ですし、175lpiであれば350dpi程度が目安となります。こうした基準を知らずに低解像度の画像を使ってしまうと、せっかく高い線数で印刷しても仕上がりが粗くなってしまいます。逆に必要以上に高解像度の画像を使っても、データが重くなって処理に時間がかかるだけで、印刷の品質が上がるわけではありません。つまり、代表的な線数を理解しておくことは、データ作成の効率化にもつながるのです。
このように、175lpiや133lpiといった代表的な線数は、単なる数値の違いではなく、印刷物の用途や目的に応じた選択肢として存在しています。それぞれの線数には適した場面があり、その選び方ひとつで印刷物の印象は大きく変わります。印刷を依頼する立場にある企業担当者にとっても、この知識を持っていることで、印刷会社とのやり取りがより具体的でスムーズになり、納得のいく仕上がりを得ることにつながります。
線数が高すぎると網点がつぶれるリスクがある理由と避けるための工夫

印刷における線数は、高ければ高いほどきれいに見えるというイメージを持つ人が多いかもしれません。確かに線数が高いほど網点は細かくなり、写真やグラデーションをより自然に表現することが可能になります。しかし、線数を過度に高く設定すると、逆に仕上がりが悪くなってしまうことがあります。その代表的なトラブルが「網点のつぶれ」です。ここでは、なぜ網点がつぶれるのか、その原因と背景、そして避けるための工夫について詳しく解説していきます。
網点のつぶれとは、印刷に使われる小さな点が紙の上で本来の形を保てず、インキが広がって隣の点とつながってしまう現象です。これが起こると、写真の細部が潰れてしまったり、色の濃淡が再現できなくなったりします。結果として全体が黒っぽくなり、せっかくのデザインが台無しになってしまうのです。
原因のひとつは「インキの広がり」です。印刷ではインキが版から紙に転写されますが、その際にインキはわずかに紙の繊維に浸透しながら広がります。この現象は「ドットゲイン」と呼ばれ、印刷業界ではよく知られています。ある程度のドットゲインは想定の範囲内として設計されますが、線数を過剰に高くすると網点同士の間隔が極端に狭くなるため、少しでもインキが広がると点がつながってしまい、結果的につぶれてしまうのです。
もうひとつの要因は「用紙の特性」です。紙には光沢があり表面が滑らかなものもあれば、繊維が荒くざらついた質感を持つものもあります。光沢のあるコート紙やアート紙であればインキが表面に留まりやすく、細かい網点でも比較的再現しやすいのですが、新聞紙や上質紙などインキを吸収しやすい紙では、網点が広がりやすいため高い線数には不向きです。つまり、紙の性質と線数の相性を無視して設定すると、網点のつぶれは避けられなくなります。
印刷機の精度や環境も大きく影響します。最新の高性能印刷機であればインキの転写や乾燥の制御が精密に行えるため、細かい線数でも対応可能ですが、古い設備や調整不足の状態では安定した印刷が難しくなります。また、温度や湿度の変化によって紙やインキの状態が変わるため、印刷環境の管理も欠かせません。
では、網点のつぶれを避けるためにはどのような工夫が必要なのでしょうか。まず第一に挙げられるのは、印刷物の用途や用紙に合わせて適切な線数を選ぶことです。たとえば、上質紙や新聞紙を使う場合には、細かさよりも安定性を優先して133lpiや100lpi程度を選ぶとよいでしょう。一方、アート紙やコート紙を使用し、ビジュアルを重視する印刷物なら175lpiや200lpiが適しています。このように、線数の選択は「紙質」と「目的」に応じたバランスが求められるのです。
次に、印刷データの準備段階でも工夫ができます。たとえば、画像解像度を線数に合わせて適切に設定することです。先ほども触れたように、一般的には線数の2倍程度の解像度(dpi)が推奨されます。175lpiなら350dpi、133lpiなら266dpiといった具合です。これを守らずに低解像度の画像を使うと、印刷機側で補正しようとしてインキが過剰に広がり、結果的に網点のつぶれを引き起こす原因になってしまいます。
さらに、印刷現場での管理も重要です。インキの粘度や水分量の調整、乾燥の速度管理などを適切に行うことで、網点が安定して再現されやすくなります。特にオフセット印刷では、水とインキのバランスが仕上がりに直結するため、オペレーターの経験と技術がものを言います。こうした調整を怠ると、どんなに高性能な機械を使っても網点のつぶれを防ぐことはできません。
また、最近では「FMスクリーン」という技術も広がっています。これは従来の網点を規則的に配置する方法(AMスクリーン)とは異なり、ランダムに配置して濃淡を表現する方式です。FMスクリーンでは点の大きさは常に一定で、密度を変えることで濃淡を作るため、従来のように網点同士が近づきすぎてつぶれるリスクが減ります。この方式を導入することで、高精細な印刷をより安定して行えるようになってきています。
網点のつぶれを避ける工夫は、単に美しい印刷を実現するだけでなく、コストや効率の面でも大切です。つぶれた印刷は見栄えが悪いだけでなく、再印刷や修正の原因になり、時間とコストが余計にかかります。最初から適切な線数を選び、データと環境を整えることで、無駄を防ぎながら安定した品質を確保できるのです。
まとめると、線数を高く設定しすぎると網点がつぶれる理由は、インキの広がり、紙質の特性、印刷機や環境の条件といった複数の要素が重なることにあります。そのリスクを避けるためには、適切な線数の選択、データの解像度設定、印刷現場での調整や管理、そして必要に応じた新しい技術の導入といった工夫が必要です。こうした知識を持つことで、印刷物の品質を安定させ、目的に合った美しい仕上がりを実現することができるのです。
用紙の種類ごとに最適な線数の選び方、印刷物の仕上がりを高める方法!

印刷物の仕上がりを大きく左右する要素のひとつに「用紙」があります。紙には種類ごとに質感や吸収性があり、それによってインキの広がり方や発色の仕方が変わります。そして、こうした性質に合わせて線数を選ばなければ、美しい印刷を実現することはできません。ここでは、代表的な用紙の種類ごとにどのような線数を選ぶと効果的なのかを丁寧に解説していきます。
まず、もっとも一般的に使われるのが「コート紙」です。表面にコーティングが施されており、光沢感があり滑らかな手触りを特徴としています。インキが表面に留まりやすく、網点が広がりにくいため、高めの線数に適しています。たとえば175lpiや200lpiといった細かい線数を使うことで、写真のグラデーションや細かいディテールがきれいに表現されます。カタログや写真集、パンフレットなど、ビジュアルの美しさを重視する印刷物にはコート紙と高い線数の組み合わせがよく使われています。
次に「マットコート紙」について見てみましょう。コート紙の一種ですが、表面の光沢を抑えて落ち着いた質感を持つ紙です。マット調の仕上がりは高級感を演出できるため、企業の会社案内や高級ブランドのカタログなどでよく使われます。インキのにじみは比較的少ないため175lpi程度まで対応可能ですが、光沢がないぶん色の再現性はやや抑えられる傾向にあります。そのため、あえて線数を高くしすぎず133lpiから175lpiあたりを選ぶことで、落ち着いた色調と見やすさを両立させることができます。
「上質紙」は、表面にコーティングが施されていない紙で、書籍やコピー用紙としてもおなじみです。ざらつきがあり、インキを吸収しやすいため、細かい網点はどうしてもつぶれやすくなります。そのため線数は低めに設定するのが一般的で、100lpiから133lpi程度がよく用いられます。会社の資料や冊子、配布用のパンフレットなど、情報をしっかり伝えることが目的で、過度な美しさを求めない印刷物にはこの組み合わせが適しています。
さらに、「新聞用紙」のように極端にインキを吸収しやすい紙では、線数をさらに下げる必要があります。一般的には85lpiから100lpiが用いられ、粗さは目立つものの、大量印刷やスピード重視の媒体には適しています。新聞に掲載される写真が少し粗いのは、この線数の低さが理由です。しかし、情報を迅速に伝えるという新聞本来の目的を考えれば、この選択は理にかなっていると言えます。
最近では「アート紙」や「高級特殊紙」と呼ばれる紙も注目されています。アート紙は非常に滑らかで発色が良く、200lpi以上の高い線数にも対応できる場合があります。美術書や高級写真集、ブランドカタログなど、極めて繊細な表現を必要とする印刷物に適しています。ただし、扱いが難しくコストも高いため、印刷会社と十分な打ち合わせが必要です。特殊紙についても同様で、表面に凹凸がある紙や和紙のような独特な素材では、細かい線数は再現できず、逆に粗い線数を使ったほうが味わい深い仕上がりになる場合があります。
このように、用紙ごとに適した線数は大きく異なります。印刷物を企画する段階で「どんな紙を使うのか」「どんな仕上がりを目指すのか」を明確にすることで、線数の選択が自然と決まってきます。たとえば「高級感のある会社案内を作りたい」という目的ならマットコート紙に175lpi程度を組み合わせ、「配布用の情報チラシを大量に印刷したい」なら上質紙に133lpi程度を選ぶといった判断です。
また、用紙の選択は見た目だけでなく、コストや実用性にも影響します。コート紙やアート紙は高価ですが、細かい表現に向いています。一方で上質紙や新聞紙は安価で扱いやすく、情報伝達に向いています。これらを踏まえて線数を決めることで、コストパフォーマンスの高い印刷を実現できるのです。
用紙ごとに適した線数を理解することは、印刷物の仕上がりを高めるうえで欠かせない知識です。紙の特性を無視して高い線数を選んでも網点のつぶれを招く可能性があり、逆に紙の良さを活かしきれなくなることもあります。大切なのは、用紙の性質を理解し、それに合わせて線数を選ぶことです。そうすることで、印刷物の完成度は大きく向上し、目的に合った効果をしっかりと発揮できるようになります。
オフセット印刷やデジタル印刷における線数の考え方と印刷方式による違い
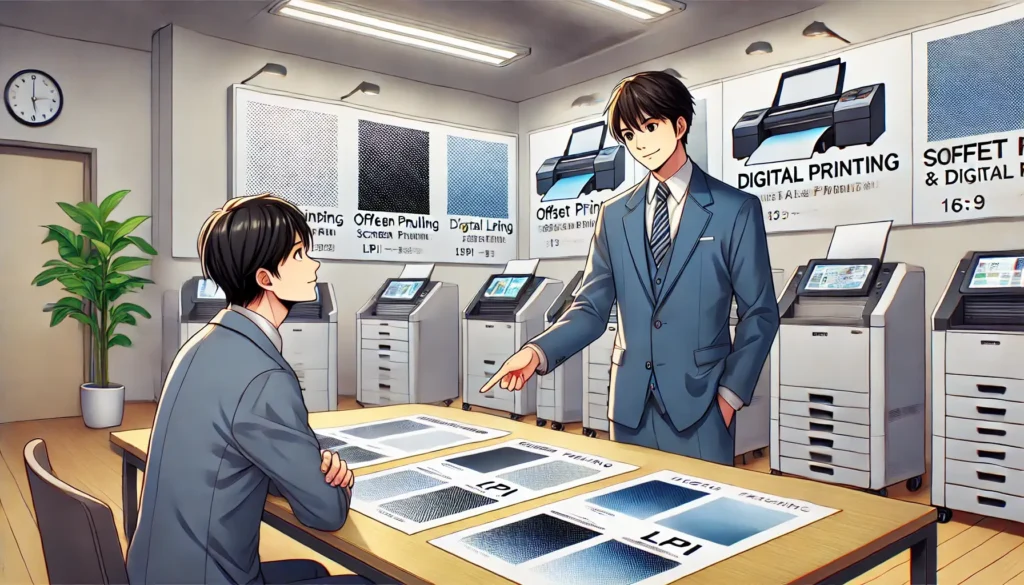
印刷の仕上がりを考えるときに欠かせない線数は、使用する印刷方式によっても考え方が変わります。特に代表的な印刷方式であるオフセット印刷と、近年急速に普及しているデジタル印刷では、線数の扱い方や適用の仕方に違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、印刷物の目的に合った最適な線数を選ぶことができ、仕上がりの品質やコストの面で満足度を高めることができます。
まず、オフセット印刷について見てみましょう。オフセット印刷は版を作って大量に印刷する方式で、商業印刷の多くに採用されています。この方式では、網点を使って色を表現する「AMスクリーン」が一般的に用いられています。線数は網点の細かさを表すため、133lpi、175lpiといった数値が基準としてよく使われています。オフセット印刷では紙やインキ、印刷機の調整によって線数の再現性が左右されるため、適切な数値を選ばなければ網点がつぶれたり、逆に薄く見えてしまったりすることがあります。高級カタログや写真集で175lpiが標準とされているのも、オフセット印刷の特性を踏まえた判断です。
また、オフセット印刷は大量印刷に向いているため、コストと品質のバランスが重要です。線数を高く設定すると美しい仕上がりが得られますが、インキの管理や版の精度に高い水準が求められるため、そのぶんコストや手間がかかります。逆に線数を抑えると安定して印刷でき、大量に刷る場合には効率的ですが、仕上がりの繊細さは犠牲になります。このようにオフセット印刷では、印刷物の目的や配布部数、想定される読者層に合わせて線数を調整するのが一般的です。
次にデジタル印刷について解説します。デジタル印刷は版を作らずにデータから直接印刷できる方式で、小ロットやオンデマンド印刷に広く使われています。近年では技術が進化し、オフセット印刷に近い品質を再現できるようになってきていますが、線数の考え方には少し違いがあります。デジタル印刷では、必ずしも従来の「lpi」という表現を使わない場合があり、プリンターの解像度を示す「dpi」で語られることが多いのです。たとえば、1200dpiの解像度を持つプリンターであれば、それ自体が網点の再現性に直結し、オフセット印刷の175lpiに匹敵する、あるいはそれ以上の表現が可能になります。
ただし、デジタル印刷には独特の制約もあります。インキではなくトナーやインクジェット方式を使うため、紙質によっては色の定着や発色が変わりやすく、細かい線数を理論上は再現できても実際には表現が難しいこともあります。特にインクジェット方式では、インキの吸収具合や紙の表面の凹凸が仕上がりに影響を与えやすいため、オフセット印刷ほど自由に線数をコントロールできない場合があります。そのため、デジタル印刷で高級感を出したい場合には、プリンターの解像度だけでなく、紙との相性を考えることが欠かせません。
一方で、デジタル印刷にはメリットも多くあります。小部数であればオフセット印刷のように版を作る必要がないためコストを抑えられますし、可変印刷と呼ばれる一枚ごとに内容を変える印刷も可能です。線数に関しても、印刷機ごとに最適化されているため、ユーザーが数値を指定しなくても自動的に適切な細かさで出力されるケースが増えています。つまり、デジタル印刷では線数を直接的に意識する必要が少なくなっているとも言えるでしょう。
さらに最近では「FMスクリーン」と呼ばれる方式もオフセット・デジタル両方で使われるようになってきました。これは網点を規則正しく並べる従来のAMスクリーンとは異なり、ランダムに配置して濃淡を表現する方式です。点の大きさは常に一定で、密度を変えることで階調を表すため、網点がつぶれるリスクが少なく、高精細な表現を可能にします。FMスクリーンは従来の「lpi」という概念に必ずしも当てはまらないため、新しい印刷方式では「線数」という言葉が持つ意味合いも変わりつつあるのです。
このように、オフセット印刷とデジタル印刷では、線数の考え方や扱い方に違いがあります。オフセット印刷では従来通り133lpiや175lpiといった具体的な数値で表され、紙やインキ、機械の性能に合わせて選ばれます。一方デジタル印刷ではdpiで語られることが多く、機械の解像度やアルゴリズムに依存するため、線数を数値として意識するよりも「どのくらいの品質を得られるか」という観点で考えることが重要です。
印刷方式による違いを理解することで、目的に応じて最適な手段を選べるようになります。たとえば、大量に高品質なカタログを作るならオフセット印刷で175lpiを選ぶのが適していますが、少部数で短納期のパンフレットならデジタル印刷で十分な品質を得られるかもしれません。線数は印刷の仕組みと深く結びついており、方式による違いを知っておくことで、より効果的に活用できるのです。
線数と印刷コストの関係をわかりやすく説明

印刷物を制作する際、多くの企業担当者が気にするのは「仕上がりの美しさ」と「コスト」のバランスです。線数は仕上がりを大きく左右する要素ですが、同時に印刷コストにも少なからず影響を与えます。線数をどのように設定するかによって、印刷にかかる費用や効率が変わるため、この関係を理解しておくことはとても大切です。ここでは、線数とコストがどのように関わっているのかを具体的に解説し、企業担当者が印刷を依頼するときに参考にできる視点をお伝えします。
まず、線数が高いと仕上がりはきれいになりますが、その分だけ印刷工程に求められる精度が上がります。高精細な印刷を行うには、インキの管理、印刷機の調整、版の精度、そして用紙の品質までを細かく整える必要があります。これらを高いレベルで維持するには時間や手間がかかるため、必然的にコストが上がってしまうのです。たとえば175lpiや200lpiといった線数で美しい仕上がりを目指す場合、印刷会社側は高性能な機械や丁寧な調整を行う必要があるため、通常よりも高い料金が設定されることがあります。
一方、133lpiや100lpiといった標準的な線数を用いた場合は、印刷の安定性が高く、スピードも速いためコストを抑えやすくなります。大量に印刷するチラシや配布物では、このように線数を抑えて効率を優先することが一般的です。特に数万部以上を刷るような場合には、線数を少し下げるだけで大きなコスト削減につながることがあります。つまり、線数は単なる美しさだけでなく、経済性を考える上でも重要な判断材料なのです。
ここで押さえておきたいのは、線数が直接的に「インキの使用量」を大きく変えるわけではないという点です。網点の大きさや配置が変わっても、全体として使うインキの量はそれほど大きな差が出ません。しかし、線数を高めることで印刷の難易度が上がり、不良品ややり直しのリスクが高まります。その結果、追加のコストが発生する可能性があるのです。逆に線数を抑えれば、印刷の安定性が増すためロスが少なく、全体としてコストを抑える効果があります。
また、線数の選択は「用紙コスト」にも影響します。高い線数で印刷する場合は、インキがにじみにくく、細かい網点をしっかり表現できる高品質な紙が必要になります。コート紙やアート紙といった滑らかな紙は単価が高いため、線数を高く設定すると必然的に用紙代がかさみます。一方で、上質紙や新聞用紙など安価な紙では高い線数を使うことができないため、線数を抑えてコストと仕上がりのバランスを取ることになります。つまり、線数の設定は印刷料金だけでなく、用紙の選択や総合的なコスト構造にも深く関わっているのです。
企業担当者が印刷物を発注するときには、「どこにお金をかけるべきか」を明確にすることが求められます。たとえば高級感を演出してブランドイメージを高めたいパンフレットであれば、多少コストがかかっても175lpi以上を選ぶ価値があります。しかし、イベントで大量に配布するフライヤーであれば、133lpiや100lpiにして費用を抑える方が合理的です。目的やターゲットに応じて線数を選ぶことで、費用対効果の高い印刷が可能になるのです。
さらに、印刷会社とのやり取りにおいても、線数の知識を持っていることは有利に働きます。担当者が「この印刷物は133lpiで十分だと考えていますが、コストはどの程度抑えられますか?」と具体的に質問できれば、印刷会社も的確な見積もりや提案をしやすくなります。漠然と「きれいに印刷してください」と依頼するよりも、線数を基準にした具体的な相談をすることで、予算内で最適な仕上がりを実現できる可能性が高まります。
また近年では、印刷方式の進化により線数とコストの関係も変化しつつあります。デジタル印刷では機械の解像度に依存する部分が大きく、従来のようにlpiを意識する場面は減ってきています。小部数であれば線数にこだわらなくてもオフセット印刷に近い品質を得られる場合もあります。とはいえ、大量印刷や高精細な再現を求める印刷物では依然として線数の知識が欠かせません。
結局のところ、線数とコストの関係は「印刷物の目的」「想定される発行部数」「求める仕上がり」「予算」という複数の要素を総合的に判断することによって決まります。すべての印刷物に高い線数を使えば理想的な見た目になりますが、それは現実的ではなく、かえって費用対効果を損なうことになります。逆に、低い線数を選んでしまうと、商品の魅力やブランドイメージが十分に伝わらなくなるリスクもあります。そのため、企業担当者にとって最適な線数の選択は「コストを削減するための工夫」であると同時に「効果的に価値を伝えるための投資」でもあるのです。
線数を選ぶときに考慮すべき印刷データ作成や入稿時の注意点

印刷を依頼するときには、どの線数で仕上げるのかを印刷会社と相談することが大切ですが、それと同じくらい重要なのが「データの作り方」と「入稿時の注意点」です。どんなに高い線数を設定しても、元のデータに不備があれば思った通りの仕上がりにはなりません。ここでは、線数を選ぶ際に意識しておきたいデータ作成や入稿時のポイントを整理し、失敗を防ぐための知識をお伝えします。
まず最初に考えるべきは「画像解像度」です。線数と解像度には深い関係があり、一般的には線数の2倍程度の解像度を用意するのが理想とされています。たとえば175lpiで印刷するなら350dpi程度、133lpiなら266dpi程度が目安です。これより低い解像度の画像を使うと、印刷時にぼやけたり粗く見えたりしてしまいます。逆に過度に高解像度の画像を使用しても、印刷の品質が劇的に向上するわけではなく、データが重くなり処理に時間がかかるだけです。効率的に作業を進めるためには、線数に適した解像度を守ることが重要です。
次に注意すべきは「カラーモード」です。パソコンの画面はRGB(赤・緑・青)の光で色を表現していますが、印刷物はCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)のインキで再現します。そのため、データを作成するときには必ずCMYKに変換しておく必要があります。RGBのまま入稿してしまうと、印刷時に自動変換され、意図しない色の変化が起こることがあります。特に線数を高めて繊細な色の再現を狙う場合、カラーモードの違いによる色のズレは大きな問題となります。
さらに「フォントの扱い」にも注意が必要です。入稿データに使用しているフォントをそのまま残しておくと、印刷会社の環境に同じフォントがなければ文字化けやレイアウト崩れの原因になります。これを防ぐためには、フォントをアウトライン化するか、埋め込み設定をしておくことが推奨されます。線数を細かくして美しい印刷を目指しても、文字が崩れてしまっては意味がありません。データの体裁を整える作業は入稿前に必ず確認しておきましょう。
また「トリムマーク(トンボ)」や「塗り足し」も入稿時に忘れてはならない要素です。トンボは断裁位置を示すために必要で、塗り足しは仕上がりサイズよりも外側までデザインを伸ばして印刷するために設定します。これを怠ると、断裁時に白いフチが出てしまい、完成物の見栄えが悪くなります。特に高い線数で精細に印刷した場合は、こうした不備が目立ちやすくなるため、事前の準備が大切です。
さらに入稿時の注意点として「カラープロファイル」の設定があります。印刷会社によって推奨されるプロファイルが異なる場合があるため、事前に確認して合わせておくことが必要です。プロファイルを統一していないと、画面で見た色と印刷結果が大きく違ってしまうことがあります。これは線数に関わらず起こり得る問題ですが、繊細な色表現を求める高線数印刷では特に注意が必要です。
入稿データを作成するときには「不要なレイヤーや隠しオブジェクトを残さない」ことも忘れてはいけません。余計な要素が残っていると、印刷時に予期せぬ不具合を引き起こす可能性があります。データを整理してシンプルにしておくことは、印刷の安定性を高めるうえで非常に有効です。また、入稿形式も印刷会社によって指定があるため、PDF/X-1aやPDF/X-4などの形式を確認して従うようにしましょう。
さらに、印刷会社に入稿する際には「想定する線数」を伝えておくことも大切です。データの準備は線数に基づいて行われるため、175lpiで仕上げたいのか、133lpiで十分なのかを明確にしておくことで、印刷会社側も適切な処理を行うことができます。これを曖昧にしたまま入稿してしまうと、思っていたより粗い仕上がりになったり、逆にコストが上がってしまったりすることがあります。
最後に、入稿前には必ず「校正」を行うことをおすすめします。校正刷りを確認することで、線数の設定が適切かどうか、網点の見え方が狙い通りかをチェックできます。本番印刷に入ってからでは修正が難しいため、事前に確認する工程を設けることは失敗を防ぐために欠かせません。
まとめると、線数を選ぶときに考慮すべき注意点は、解像度やカラーモードの設定、フォントの処理、トンボや塗り足しの有無、カラープロファイルの統一、データ整理、そして入稿時に線数を明確に伝えることなど多岐にわたります。これらをきちんと押さえておけば、線数を活かした美しい印刷を実現できるだけでなく、トラブルを防ぎ、スムーズな進行にもつながります。
線数を理解することで印刷物をより魅力的に仕上げるための知識
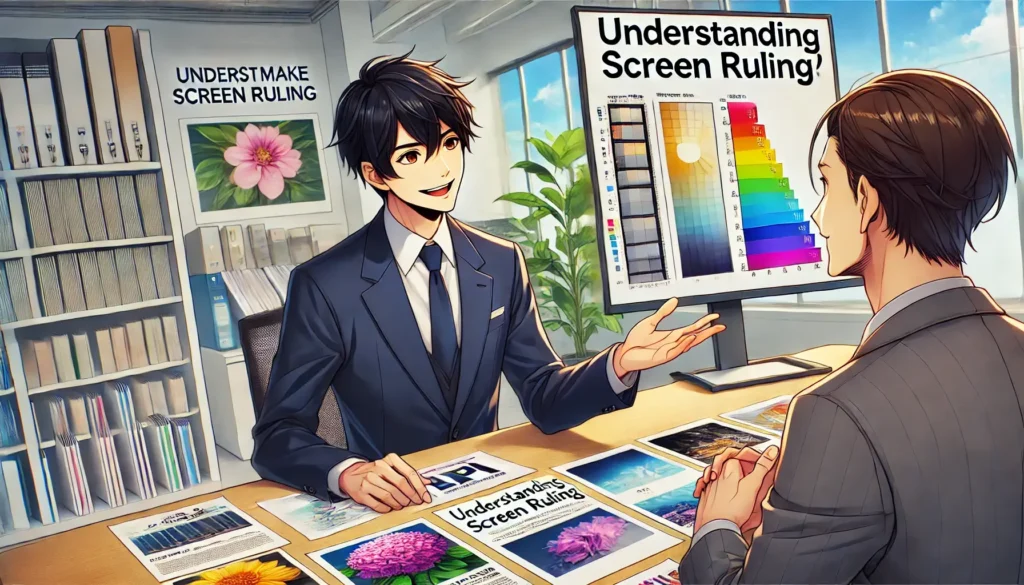
印刷物を制作する場面では、デザインの美しさや情報のわかりやすさだけでなく、その仕上がりを支える技術的な知識も欠かせません。その中で「線数」という概念を理解しているかどうかは、最終的な成果に大きな違いを生みます。線数は印刷の仕上がりを決定づける要素でありながら、選び方を誤るとせっかくのデザインが台無しになってしまうこともあります。しかし逆に正しく理解し、実務に活かすことができれば、印刷物の魅力を最大限に引き出すことができるのです。ここでは、線数の知識を具体的にどのように使えばよいのかを整理してご紹介します。
まず、線数を理解することの一番の利点は「印刷会社とのコミュニケーションがスムーズになる」という点です。印刷を依頼する際、多くの担当者は「とにかくきれいに仕上げてください」と漠然と伝えてしまいがちですが、これでは印刷会社側も具体的な判断が難しくなります。線数についての知識があれば「今回は高級感を重視したいので175lpiでお願いします」や「配布用なので133lpiで十分です」といった明確な要望を伝えることができます。これにより、印刷会社からもより的確な提案や見積もりが返ってきやすくなり、仕上がりとコストのバランスを最適化することが可能になります。
次に、データ制作の現場でも線数の理解は大きな力を発揮します。デザイナーが印刷データを作る際、どの線数で仕上げるのかを想定して画像の解像度を設定することが必要です。たとえば175lpiなら350dpi程度の解像度が必要となるため、それを意識して素材を準備することで、印刷時にぼやけることなくきれいに再現できます。逆に線数を考慮せずに低解像度の画像を配置してしまうと、完成物はどうしても粗く見えてしまい、クオリティに影響します。つまり線数の知識はデザインの完成度を左右する実務的な基礎知識なのです。
さらに、マーケティングや営業活動においても線数の知識は役立ちます。企業が制作する印刷物は、商品カタログ、会社案内、チラシ、ポスターなど多岐にわたりますが、それぞれ目的が異なります。高級感を打ち出したい場合には高めの線数を選び、大量配布で効率を重視したい場合には線数を下げるなど、目的に応じた判断が求められます。線数を適切に選ぶことで、商品やサービスの価値を的確に伝えることができ、結果として営業効果の向上にもつながるのです。
また、線数の知識はコスト管理にも直結します。高い線数を選べば美しい印刷が可能ですが、そのぶん印刷の難易度が上がりコストも高くなります。逆に線数を下げればコストを抑えられますが、仕上がりに影響が出る場合があります。どの印刷物に予算をかけ、どこで効率を重視するかを判断する際、線数の知識は非常に有効です。担当者が線数を理解していれば、目的に応じて的確な選択ができ、費用対効果の高い印刷を実現できるでしょう。
さらに近年では、オフセット印刷だけでなくデジタル印刷の普及により、線数の考え方も変化しています。デジタル印刷では機械の解像度に依存する部分が多く、従来のlpiという概念に必ずしも縛られる必要がないケースもあります。しかし、オフセット印刷とデジタル印刷を比較検討する場面では、線数の理解が判断材料のひとつになります。どちらの方式が目的に合っているのかを見極めるためにも、線数を正しく理解しておくことは有効です。
線数を実務に活かす方法として忘れてはならないのが「校正の重要性」です。理論上の数値や知識だけでは、必ずしも最終的な仕上がりを正確に想像できるわけではありません。校正刷りを確認し、網点の見え方や全体の質感が目的に合っているかをチェックすることで、最終的な失敗を防ぐことができます。印刷を発注する立場にある企業担当者にとっても、校正の段階で線数を意識して見ることは、完成物の満足度を大きく高めることにつながります。
総じて言えるのは、線数の知識を単なる専門用語として覚えるのではなく、実際の業務や判断に結びつけることが重要だということです。印刷会社とのやり取り、データ制作、マーケティング効果の最大化、コスト管理、そして校正の確認といった一連の流れの中で線数を意識することで、印刷物の完成度は格段に上がります。そして最終的には「きれいに印刷できた」だけでなく「目的に合った効果的な印刷ができた」と感じられる結果を生み出すことができるのです。
印刷は単なる情報伝達の手段ではなく、企業や商品の魅力を伝える大切なコミュニケーションツールです。その印象を決定づける要素のひとつが線数であり、それを理解して実務に活かすことは大きな価値を持っています。担当者が線数の知識を持ち、適切に判断できるようになれば、印刷物はより魅力的に仕上がり、見る人に強い印象を残すことができるでしょう。
まとめ
印刷物の仕上がりを左右する要素のひとつである「線数」は、網点の細かさを示す数値であり、印刷の美しさや表現力に直結する大切な指標です。線数が高ければ網点は目立たず、写真やグラデーションが滑らかに再現されますが、高すぎると網点がつぶれてしまうリスクがあり、紙や印刷機の特性とのバランスを取る必要があります。逆に線数を低くすれば粗さは残るものの、印刷の安定性や効率性に優れるため、大量印刷やスピードを重視する媒体には適しています。
代表的な線数には、新聞などで使われる85lpi、一般的なパンフレットやチラシで多用される133lpi、そして写真集や高級カタログで採用される175lpiがあります。さらに200lpi以上の高精細印刷も存在し、アート関連や高級ブランドの印刷物に活用されています。これらの数値は単なる目安ではなく、印刷物の目的や読者に与える印象を決める具体的な選択肢として機能しています。
用紙との相性も重要なポイントです。コート紙やアート紙のように表面が滑らかな紙は高い線数に対応できますが、上質紙や新聞紙のように吸収性が高い紙では低い線数が適しています。印刷方式による違いもあり、オフセット印刷では133lpiや175lpiが基準となる一方、デジタル印刷ではdpiが品質を決める要素として重視されることもあります。FMスクリーンなどの新しい技術も登場し、線数の考え方は少しずつ変化してきています。
線数は印刷コストにも影響を与えます。高い線数を選べば美しい仕上がりが得られる反面、調整や管理に手間がかかるためコストが上がります。逆に線数を抑えれば効率的に印刷でき、大量印刷の際にはコスト削減につながります。そのため、企業担当者にとっては「どこに投資し、どこで効率を重視するか」を見極める判断材料となります。
さらに、データ作成や入稿時にも線数を意識することが欠かせません。画像解像度を線数に合わせて設定する、RGBではなくCMYKでデータを準備する、フォントをアウトライン化する、塗り足しやトンボを正しく設定するなど、基本的な注意点を守ることでトラブルを防げます。校正刷りを確認することで、網点の見え方や全体の質感を事前にチェックできるのも大切な工程です。
総合的に見れば、線数の知識は印刷物を単に「きれいに仕上げる」ためだけでなく、「目的に合った効果的な印刷を実現する」ための判断軸でもあります。印刷会社とのやり取りを円滑にし、データ制作を効率的に進め、コストを最適化しながら魅力的な印刷物を作り上げるための大きな力となります。線数を理解し実務に活かすことで、印刷物はより高い完成度を持ち、見る人に強い印象を与えるコミュニケーションツールとして輝くのです。
よくある質問Q&A
-
線数とは何ですか?
-
線数とは、印刷物の網点の細かさを表す数値で、1インチあたりにどれくらいの点が並ぶかを示しています。単位はlpiで表され、133lpiや175lpiといった数値がよく使われます。数値が大きいほどきめ細やかになり、写真やグラデーションが滑らかに再現されます。
-
線数が高いと印刷は必ずきれいになるのですか?
-
高い線数は滑らかで美しい仕上がりを実現できますが、必ずしも常に良い結果になるとは限りません。紙の種類や印刷機の性能によっては、点がつぶれてしまい逆に見づらくなる場合もあります。用途や環境に合った線数を選ぶことが大切です。
-
線数が低いとどのような仕上がりになりますか?
-
線数が低いと網点が大きくなるため、写真や濃淡の再現が粗く見えることがあります。しかし、新聞やチラシなどのように情報を伝えることを目的とする印刷物では十分で、印刷の安定性や効率を優先できる利点もあります。
-
よく使われる代表的な線数には何がありますか?
-
一般的には新聞などで85lpiから100lpi、販促物やチラシでは133lpi、高級感を重視するカタログや写真集では175lpiが多く用いられます。さらに美術書やブランドカタログなどでは200lpi以上の超高精細印刷が選ばれることもあります。
-
線数と解像度の関係を教えてください。
-
線数に応じて画像解像度を設定することが推奨されています。基本的には線数の2倍程度の解像度が目安で、175lpiなら350dpi、133lpiなら266dpiが望ましいとされています。これを守らないと印刷が粗く見えたりデータが重くなりすぎることがあります。
-
線数を選ぶときに注意するべき紙の種類はありますか?
-
はい。コート紙やアート紙のように表面が滑らかな紙は高い線数に対応できますが、上質紙や新聞紙はインキを吸収しやすいため低い線数が適しています。紙の特性と線数のバランスを取ることで、見栄えとコストの両方を満たせます。
-
線数を高く設定するとコストは上がりますか?
-
直接的にインキの使用量が増えるわけではありませんが、高い線数は印刷の精度を求められるため管理が難しくなり、不良や調整のコストが増える傾向があります。さらに高品質な紙を使う必要がある場合も多く、結果として費用が上がるケースがあります。
-
デジタル印刷でも線数を意識する必要はありますか?
-
デジタル印刷では解像度を示すdpiが基準になることが多いため、従来のlpiという概念を直接意識する機会は少ないです。ただし仕上がりの品質を考えるうえで「どの程度の細かさで出力されるか」を理解しておくことは役立ちます。
-
線数が高すぎると何が起きますか?
-
線数を高くしすぎると、インキが広がって網点がつぶれやすくなります。結果として写真の細部がつぶれたり、全体が黒っぽく見えてしまうことがあります。紙質や印刷機の性能を考え、適切な線数を選ぶことが必要です。
-
線数と網点のつぶれを防ぐ方法はありますか?
-
適切な線数を選ぶのが第一歩です。さらに、画像解像度を正しく設定することや、印刷機でのインキや水分量の管理、温湿度の安定化も大切です。最近ではFMスクリーンという方式を使うことで、網点のつぶれを軽減する工夫も行われています。
-
線数と用紙コストにはどのような関係がありますか?
-
高い線数で印刷する場合は、インキがにじみにくく細かい表現に対応できる紙が必要になるため、コート紙やアート紙のような高品質な紙が選ばれることが多くなります。結果として紙代が高くなり、総合的なコストに影響を与えることがあります。
-
線数を決めるときに企業担当者が意識するべきことは何ですか?
-
目的とターゲットを明確にすることです。高級感を伝えたい印刷物なら高い線数を選び、大量に配布するチラシなら効率を重視して標準的な線数を選ぶとよいでしょう。線数の知識を持つことで、印刷会社とのやり取りもスムーズになります。
-
線数と印刷方式の違いを教えてください。
-
オフセット印刷では133lpiや175lpiといった具体的な基準で語られることが多いですが、デジタル印刷ではdpiが基準となることが多く、数値の扱い方が異なります。方式ごとの特徴を理解して選択することで、最適な印刷が可能になります。
-
線数を決めたらデータ作成で注意することは?
-
画像解像度を線数に合わせること、カラーモードをCMYKに変換すること、フォントをアウトライン化することなどが大切です。塗り足しやトンボの設定を忘れないようにし、入稿時には想定する線数を印刷会社に伝えることでトラブルを防げます。
-
校正刷りはなぜ必要なのですか?
-
校正刷りを確認することで、実際の線数で印刷したときに網点の見え方や色の再現が期待通りかを事前に確認できます。本番印刷に入る前に修正ができるため、失敗を防ぎ、納得のいく仕上がりに近づけるために重要です。
-
線数の知識がないと何に困りますか?
-
印刷会社に漠然とした依頼しかできず、仕上がりやコストが思ったものと違う結果になりやすいです。線数を理解していれば、目的に応じて具体的な要望を伝えられるため、より効果的で満足度の高い印刷物を作ることができます。
-
線数を上げると発色も良くなりますか?
-
線数を上げるとグラデーションや細部は滑らかに表現されますが、必ずしも発色そのものが向上するわけではありません。発色はインキや紙の特性、印刷機の性能に依存します。ただし高精細に見えるため、結果的に色がより鮮やかに感じられることはあります。
-
FMスクリーンとは何ですか?
-
FMスクリーンは、従来の規則的な網点配置(AMスクリーン)とは異なり、点をランダムに配置して濃淡を表現する方式です。点の大きさは一定で密度を変えるため、網点がつぶれにくく、高精細な仕上がりが得られるという特長があります。
-
線数を選ぶときに失敗しないコツはありますか?
-
印刷物の目的を明確にし、用紙や印刷方式との相性を考えることが大切です。高級感を出したいのか、コストを抑えたいのか、配布対象は誰かといった要素を整理することで、線数を適切に判断できます。印刷会社と相談することも効果的です。
-
初心者でも線数を意識した方が良いのでしょうか?
-
はい。専門的な知識がなくても「どんな仕上がりにしたいか」を考えるうえで線数の理解は役立ちます。最低限の知識を持つことで、印刷会社との打ち合わせがスムーズになり、完成物が想像と違ってしまうリスクを減らせます。







