北九州市の印刷事情100年の歴史が紡ぐ地域産業の歩みとは?
2025.07.02

福岡県北九州市といえば、鉄鋼業や港湾産業で知られる工業都市というイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、この地にはもうひとつ、地域の発展とともに静かに歩み続けてきた産業があります。それが「印刷業」です。実は北九州市には、創業から100年を超える印刷関連の企業が今もなお存在し、地域の中で生活と密接に関わりながら、技術と文化を支えてきました。
この土地で印刷業が根付いた背景には、大正期の産業振興や交通インフラの発展、そして情報を伝える手段として紙媒体が果たしてきた役割の大きさがあります。新聞、教材、行政資料、販促物、地域の歴史を記録する冊子に至るまで、印刷物は人々の暮らしに溶け込み、誰にとっても当たり前のようにそこにありました。
そして、時代が進むにつれて印刷業にも変化の波が訪れます。戦中戦後の混乱を経て、高度経済成長期には大量印刷や多色刷りの技術革新により産業としての成長を遂げ、さらにバブル崩壊と経済再編を機に、地域密着型のきめ細やかなサービスへと軸足を移していきました。大量生産ではなく、一人ひとりに届く丁寧な印刷。そこには「顔が見える仕事」としての価値が再認識され始めた時代背景があります。
さらに近年では、印刷とデジタルの融合が進み、情報の届け方そのものが変わりつつあります。それでもなお、印刷物が持つ物理的な手触りや温度感、そして地域の記憶に残る力は、北九州市という土地で改めて見直されているのです。印刷は単なる製造業ではなく、「地域をつなぐ仕事」として、これからのまちづくりの中でも確かな役割を担い続けていくことでしょう。
本記事では、北九州市の印刷業が100年の歴史のなかでどのように変化し、地域とともにどのように歩んできたのかを、時代ごとの視点から丁寧にひも解いていきます。変わらないものと、変わり続けるもの。その両方を見つめながら、紙という媒体が今もなお人々の生活の中に息づいている理由を探っていきます。
- 北九州市の印刷事情はなぜ注目されるのか100年の背景から探る
- 昭和初期の北九州市における印刷業の始まりと地域との関わり
- 戦中戦後の混乱の中で北九州市の印刷事情はどのように生き残ったのか
- 高度経済成長期における北九州市の印刷業の拡大と地域企業の連携
- オフセット印刷の普及が北九州市の印刷事情に与えた影響を読み解く
- 北九州市の印刷会社が直面したバブル崩壊と経済再編の時代
- デジタル化の波とともに北九州市の印刷事情はどう変化したのか
- 地域密着型のサービスが北九州市の印刷業に新たな可能性をもたらす理由
- 環境配慮やサステナビリティを意識した北九州市の印刷業の新たな試み
- これからの北九州市の印刷事情は地域と共にどのように歩んでいくのか
- まとめ
- よくある質問Q&A
北九州市の印刷事情はなぜ注目されるのか100年の背景から探る
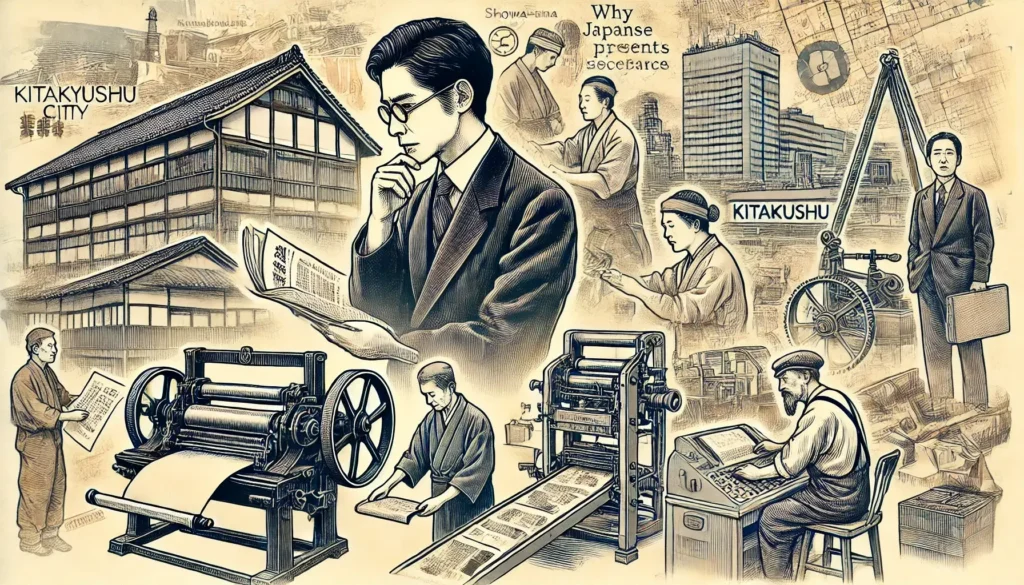
福岡県北九州市は、かつて炭鉱と鉄鋼で栄えた産業都市として知られていますが、印刷業の分野でも長い歴史と厚みのある地域性を築いてきました。印刷の始まりはおよそ100年前にさかのぼり、特に市内の港湾地域を中心に印刷会社が集まり始めたことで、その後の発展の土台が整えられていきました。これは、単に一地域の産業としての役割にとどまらず、時代ごとに移り変わる社会や経済の中で、地域に必要な情報や文化を届ける担い手として育ってきた背景があります。
昭和初期のころには、新聞や書籍の印刷が本格的に稼働し始め、それにともなって地域の教育・文化施設と連携するかたちで印刷業が根付いていきました。人々の暮らしとともにある印刷物は、家庭内で使う帳票類や包装資材なども含めて多岐にわたり、地元企業の広報や販売活動にも欠かせない存在となりました。こうして、印刷業は地域のインフラとして静かにその地位を築いていったのです。
戦後の混乱期には物資不足などの困難もありましたが、それでも地域の情報発信を支える存在として、印刷業は粘り強くその役割を果たし続けました。特に、復興に向けた行政文書や教育資料、地域新聞の印刷など、暮らしの再構築に欠かせない道具としての役割を担ったことで、多くの事業者が地元に根ざしたかたちで営業を続けることができたのです。このように、印刷業は地域再生の一端を支える存在として、歴史のうねりの中で信頼と機能を積み重ねてきました。
高度経済成長期に入ると、北九州市の印刷業はさらなる飛躍を遂げます。印刷機械の技術革新が加速し、オフセット印刷や製本技術が急速に進歩したことで、冊子類やパッケージ印刷の大量生産が可能になりました。これにより、製造業と密接に連携した印刷需要が拡大し、販促ツールや業務用書類など、多彩な分野での活用が進みました。この時期、多くの印刷業者が一貫生産体制を築き、地域内外の顧客に対応できる供給力を備え始めたのも特徴的です。
また、当時から継続的に受け継がれてきたのが「地域密着型」の姿勢でした。大規模な印刷会社とは異なり、地元に根ざした中小規模の事業者たちは、地域の声に耳を傾けながら柔軟に対応し、学校行事の印刷物や地域のお知らせ、地域企業の社史など、地域の記憶と記録をかたちに残す役割を果たしてきました。このような地道な営みの積み重ねが、北九州市の印刷業に対する信頼と親しみを生んでいったのです。
近年では、全国的にも珍しいほど長い歴史を持つ印刷業が多く残っている地域として、北九州市の存在があらためて注目されています。市内には創業から100年近く続く事業所が点在しており、それぞれが代を重ねながら印刷に関する技術と知識を次世代に伝え続けています。これらの企業の多くが、家族経営を基盤としながらも、時代のニーズにあわせた機器導入や新サービスの展開など、小回りのきく工夫を積極的に取り入れています。
こうした取り組みが、印刷という仕事の枠を超えて、まちづくりや地域文化の発信にもつながっています。たとえば地域イベントのポスターや案内パンフレット、自治体との連携による広報物の制作など、単なる印刷作業を超えた役割を担い、地域の魅力や情報をかたちにする担い手として、その存在感を放ち続けているのです。
北九州市が印刷業を支える土壌としてここまで成長できたのは、単に技術や設備の進化だけではありません。長年にわたり築かれてきた信頼関係と、地域との丁寧なやりとりを通じて育まれた実直な姿勢が背景にあります。これはまさに、現場の経験を積み重ねてきたことでしか得られない価値であり、他地域には容易に真似のできない文化的な厚みといえるでしょう。
このように、北九州市の印刷事情が注目される理由は、単なる歴史の長さだけでなく、地域の変化に寄り添いながら進化してきた柔軟性と、暮らしに密接に関わる文化的な役割を一貫して果たしてきた点にあります。今後、どれだけ技術や社会が変化しても、この100年の積み重ねが示してきた地域との向き合い方が、これからの方向性を形づくっていく手がかりとなっていくでしょう。
昭和初期の北九州市における印刷業の始まりと地域との関わり
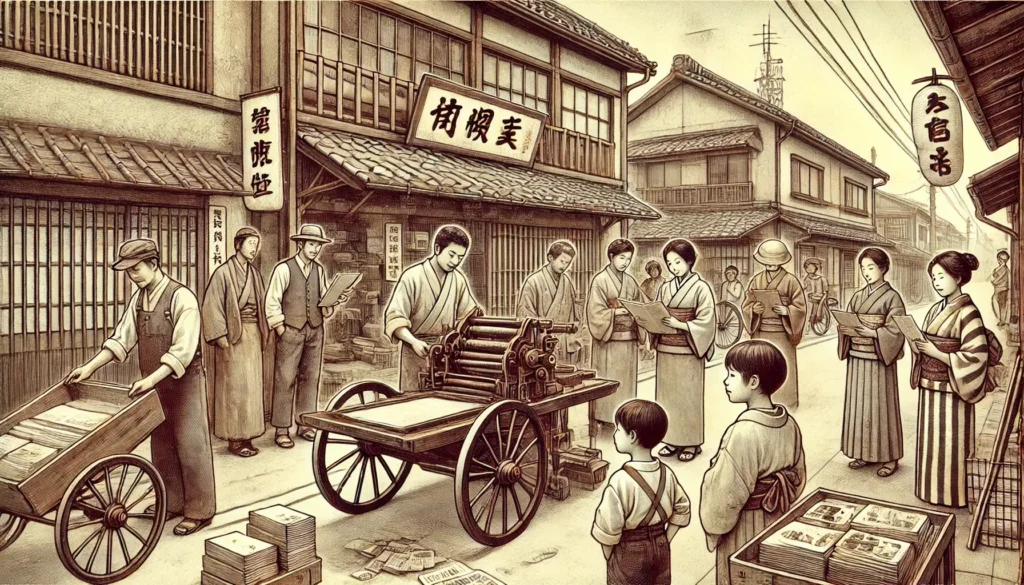
北九州市の印刷業は、昭和初期に本格的な広がりを見せ始めました。まだ市としての統合前であった当時、それぞれの地域、たとえば門司、小倉、若松などは独立した市として存在していました。その中で、とくに港や鉄道の結節点となっていたエリアを中心に、印刷業が物流や流通と密接に関わるかたちで発展していったのです。これは輸出入の書類や通関に関わる帳票類、商業広告、新聞の印刷需要が急速に高まったことによるものです。
昭和初期という時代は、まだ手作業による活版印刷が主流であり、活字を組み、版を作り、紙に一枚ずつ印刷するという緻密な工程が求められていました。こうした技術は習得に時間がかかるため、地域の中で職人としての育成や技能の伝承が自然に行われるようになりました。技術を持った人材が少なかったため、ひとつひとつの印刷工程には高い集中力と責任が求められ、地元の若者たちにとっては“職人の道”として誇りのある仕事でもありました。
この時代、北九州市の印刷業者は単に商業印刷を担うだけでなく、地域の教育や文化とも強く結びついていました。学校で配布される教材、卒業証書や通知表、地域のイベント告知のためのポスターやビラなど、暮らしの中に溶け込んだ印刷物は非常に多岐にわたっており、その一つひとつが市民の手元に届くことによって“情報”というものの価値が具体的な形で感じられていました。こうした背景のなかで、印刷業は地域社会の中で存在感を高めていったのです。
また、当時はまだ放送メディアが一般的に普及していなかったため、情報の伝達手段として最も身近で効果的だったのが紙による告知や報道でした。新聞はもちろん、地域ごとに配布されるお知らせや商店街の広告など、あらゆる情報は印刷物を通じて流通していました。印刷業者は情報の“発信者”ではないものの、その中継地点としてなくてはならない存在でした。誰かが書いた文章や描いた図案が、版を通じて多くの人の目に届くという役割は、現在のデジタル社会で言えばWeb配信に近い立ち位置と言えるかもしれません。
地域に密着した印刷業は、当時の行政とも強い関わりを持っていました。自治体が出す広報紙や通知文書の制作を請け負うことは、事業の安定にもつながりましたし、その一方で内容の正確さや迅速な対応力が問われる場面でもありました。こうした業務を長年にわたって続けていく中で、印刷業者は単なる外注先としてではなく、地域行政と協力しあうパートナーとしての関係性を築いていったのです。
特筆すべきは、地域の中に自然と形成されていった「信頼関係」です。印刷という仕事は、単に依頼された内容を形にするだけではなく、相手が求めているものを的確にくみ取り、さらに品質と納期を両立させながら応えていくことが求められます。昭和初期の北九州においても、こうした対応力は極めて重要でした。依頼者の要望に応える姿勢、細やかな確認作業、急な修正への柔軟な対応など、今では当たり前とされる「顧客ファースト」の考え方がすでにこの時代から根づいていたとも言えるでしょう。
さらには、印刷業に従事する人々の中には、地域活動に積極的に関わる者も少なくありませんでした。地元の文化団体や商店街組合などと協力しながら、印刷物の制作を通じて地域の魅力を発信する取り組みが各地で見られるようになり、「印刷」が単なる産業ではなく、地域の文化を支える表現手段としても機能するようになっていきました。
こうした歴史の蓄積は、後の時代に続く印刷業の発展に大きく影響を与えました。単に印刷技術を持つだけでなく、地域との関わりを大切にする姿勢が受け継がれ、その後のデジタル印刷やオンデマンド印刷といった新たな技術への移行期にも、多くの事業者がしなやかに対応できた理由のひとつとなっています。
昭和初期に始まった北九州市の印刷業は、物理的な紙の上に情報をのせるという行為の裏側で、地域と人とを結びつける重要な役割を果たしていました。それは決して目立つ存在ではなくとも、なくてはならないものとして、今なおその精神は引き継がれ続けています。
戦中戦後の混乱の中で北九州市の印刷事情はどのように生き残ったのか
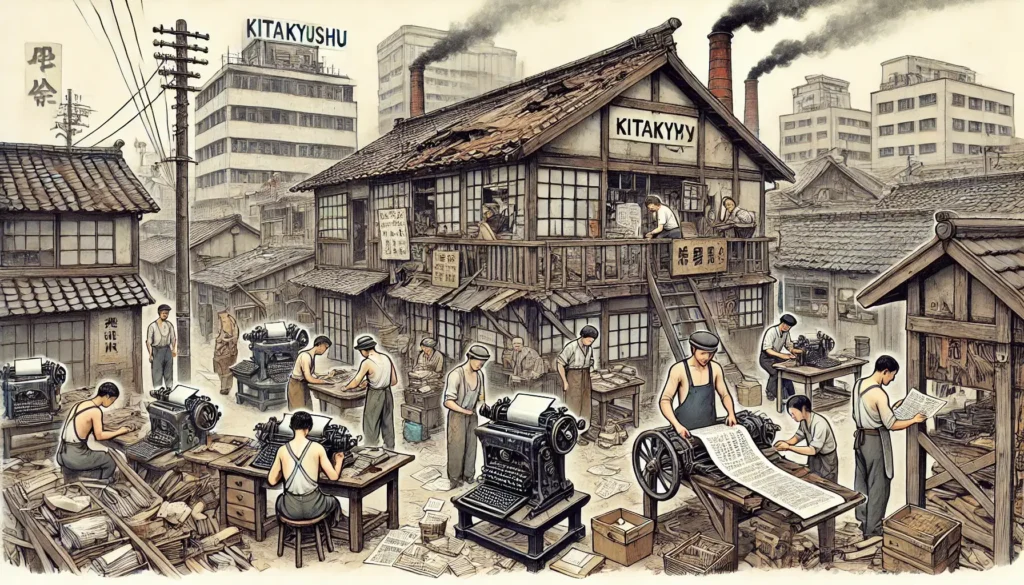
太平洋戦争の序盤から終戦直後にかけて、北九州市でも深刻な物資不足や空襲による被害が発生し、印刷業にも大きな影響が及びました。紙やインク、活字といった資材の入手が非常に困難となり、印刷所は操業停止や縮小を余儀なくされたケースも少なくありませんでした。株式会社ヤマガも戦時、鉄が不足しているという理由で印刷機を手放さなければなりませんでした。そのため北九州の印刷事業者は一時、活字を寄せ集めて再利用するなど、極限まで工夫をこらすことで、なんとか最低限の印刷を続けていく状況が続きました。
戦争中は配給制による抑制の中で印刷資材の使用量が限定され、宣伝や広告用の印刷はほぼ禁止となりました。そのため、印刷業者は戦時公報や命令文書、軍需書類など、政府の要請に応じた業務へと切り替える必要がありました。自由な表現の自由は奪われ、業種は“国家の道具”として存続をかけた適応を迫られる中、業者は厳しい選択を迫られながらも、その質を担保しつつ公的な役割を果たし続けました。
終戦直後に入ると、戦災で印刷設備が被災した事業所も多く、再建には大きな時間と労力が必要でした。焼け跡のなかで、限られた資材と労働力による再稼働が進められる一方で、地域新聞や復興チラシ、公共のお知らせなど、生活再建に向けた印刷需要が急増しました。印刷所は、復興の担い手として、行政や教育機関との連携を強め、生活に密接する書類や各種告知物を手掛けながら、ゆっくりとではありましたが地域社会に再び根を張り直しました。
こうした時期に重要だったのは、地域内に蓄えられた「人的ネットワーク」でした。多くの印刷に関わる人々が顔見知り同士で助け合い、困ったときには機材や作業場、情報といった資源を共有することで、効率的に再稼働を進めることができました。一部では、印刷業者が共同で印刷設備を運用したり、資材を共同購入するなど、小さな連帯が立ち上がり、無駄を省きつつも業務を維持する支えとなりました。
さらに、教育関係の印刷物や公的な文書が増えたことで、こうした需要に応えられる準備があったことが大きな強みとなりました。これは昭和初期に築いた行政との信頼関係が、国策に振り回される混乱期にも存続した結果であり、信頼関係の継続が技術面だけでなく業務面でも重宝されたのです。
また、戦後復興の象徴ともいえる国家の再建では、印刷物がその基盤を支える役割を果たしました。自治体や民間が主導する地域の再開発や学校再建などでは、設計図や行政資料、広報チラシといった多様な印刷物が必要とされ、活版印刷や新たに導入されたオフセット印刷の両方を駆使しながら対応が進められました。とりわけ、地元資材を活かしつつ最小限のコストと時間で印刷物を届けるための工夫が随所に見られました。
生活が落ち着きを取り戻すにつれ、印刷業は徐々に民需へと再び軸を移していきました。戦前には比較的少数だった民間向けのチラシやポスター、帳票物などの依頼が戻り始め、復興の象徴としての印刷物が街を彩るようになります。地域の商店や工場が再び営業を開始すると、広告や案内物などが街中にあふれ、紙による情報伝達の役割が再度重要な存在感を示し始めました。
このような歴史の中で、北九州市の印刷事情は多くの危機を乗り越えたことで、変化への柔軟性と持久力を備えていきました。技術や資材が不足する中でも人と人とのつながりを活かし、必要な情報を届け続ける営みを続けてきたことは、今日まで続く信頼性や専門性の源泉となっています。社会が不安定でも、印刷業が果たしてきた役割が、地域にとって必要不可欠なインフラであり続けた証しともいえるでしょう。
高度経済成長期における北九州市の印刷業の拡大と地域企業の連携
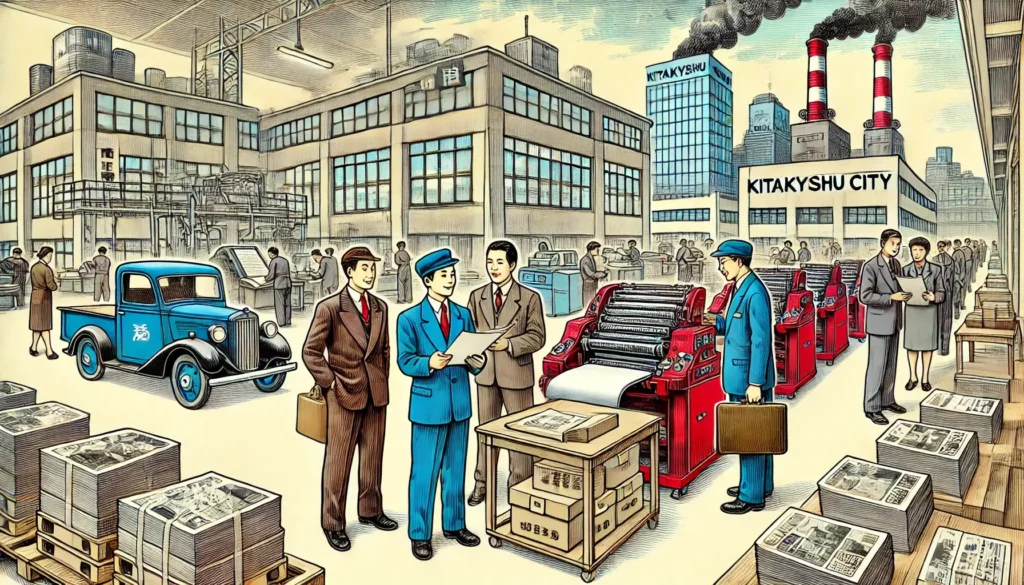
1950年代後半から1970年代前半にかけて、日本全国で経済が急激に発展した高度経済成長期。この時代、北九州市も例外ではなく、工業の集積地として一層の存在感を増すことになります。そのような産業の拡大と並行して、印刷業も急成長を遂げ、地域社会と産業基盤を支える大きな役割を果たしていきました。
北九州市は、もともと鉄鋼や化学といった基幹産業を中心に成り立っていた地域であり、大規模な工場や企業が市内の各地に集まり始めていました。こうした企業群の台頭に伴い、社内報、製品カタログ、技術資料、操作マニュアルといった印刷物の需要が飛躍的に増加しました。また、製品を流通させる際には包装資材や説明書、品質保証書など、情報を伝達する印刷物が不可欠となっていたため、それを受け止める体制を整える必要があったのです。
このような状況を背景に、印刷業者の多くは従来の技術だけでなく、新たに導入されつつあったオフセット印刷機や多色刷り機械の導入に踏み切り、製品ラインを多様化させていきました。高度成長期には需要が読みきれないほど膨らみ、受注量に応えるための増員や設備の拡充が続けられました。このような積極的な対応は、結果的に地域経済の成長を下支えする役割にもつながり、印刷業は工業と並んで市内の産業構造の中核を担う存在となっていきます。
さらに、地域の商業も活性化し、スーパーマーケットや専門店、飲食店などが次々と開業する中で、それらの宣伝や販促のためのチラシ、ポスター、プライスカードといった印刷物も多く求められるようになります。これに応じて、印刷業者は業務の幅を広げ、時にはデザインや企画の段階から関与するなど、単なる印刷業務を超えた提案型のサービスへと進化していきました。
こうした発展を可能にしたもう一つの要因は、「地域企業との密接な連携」でした。北九州市内では、多くの製造業や小売業が地場の印刷所をパートナーとして選ぶ傾向が強く、長年の付き合いを通じて築かれた信頼関係がありました。印刷業者にとっても、直接の依頼主と顔を合わせながらニーズを正確にくみ取れることは、大量の情報を紙媒体に落とし込むうえで大きなアドバンテージとなりました。
また、地域の自治体や公共機関との関わりも深まっていきます。住民向けの広報誌、都市計画関連資料、イベント案内、教育関連の文書など、行政のさまざまな業務が増加する中で、印刷物のニーズも比例して高まっていきました。印刷業者はそれらの業務に対応するだけでなく、提出物のフォーマット作成やスケジュール管理といった工程全体に対しても責任を持つ体制を整え、自治体にとっては頼れる業務パートナーとして重宝されていきました。
この時期に特徴的だったのは、多くの印刷所が「一貫生産体制」を築き始めたことです。これまでは印刷、製本、加工といった工程が分業されていたのに対し、すべての工程を自社で完結させる動きが広まりました。これにより、納期短縮やコスト削減、品質の安定化が実現され、地域内外からの受注に対しても高い対応力を示すことができるようになったのです。
さらに、学校や地域団体とのつながりも強まりました。学校行事のプログラム、卒業アルバム、地域祭りのポスターなど、人々の暮らしと密接に関わる印刷物の多くがこの時期に定着していきます。印刷所は単に依頼を受けるだけでなく、提案や構成段階からかかわるようになり、その存在はより身近なものとなっていきました。
このようにして、北九州市の印刷業は高度経済成長期という国全体のダイナミズムの中で、ただ規模を拡大するだけでなく、技術・人材・設備を適切に投じながら、地域企業や行政といったパートナーとともに歩む形でその地位を確立していったのです。そして、その成長の基盤には、ただモノを刷るだけではない、人の意図や思いをかたちにして届けるという姿勢が一貫して貫かれていたことが、この時代の印刷業に確かな輪郭を与えていました。
オフセット印刷の普及が北九州市の印刷事情に与えた影響を読み解く
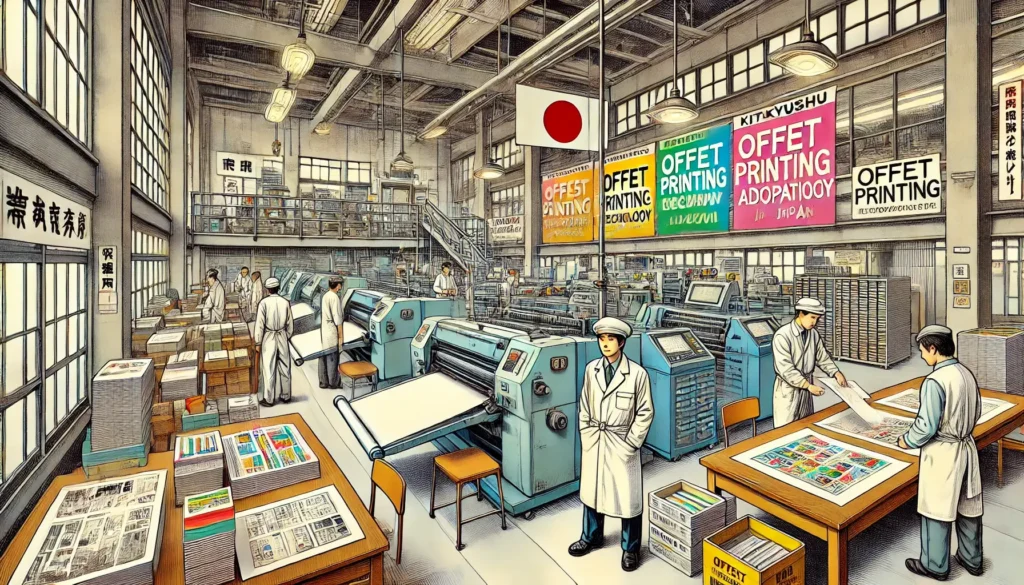
昭和中期から後期にかけて、日本全国の印刷業界では「オフセット印刷」という技術が急速に普及し、従来の活版印刷に代わって主流となっていきました。この変化は、印刷の現場に劇的な効率と表現力の向上をもたらしただけでなく、印刷物の役割そのものを変えていくきっかけともなりました。北九州市の印刷業界も、この波に大きく影響を受けることになります。
オフセット印刷は、版と紙が直接触れない仕組みで印刷されるため、版が傷みにくく、長時間の印刷にも安定した品質を維持できることが特長です。また、フルカラー印刷が比較的容易になり、写真やイラストの表現力も格段に向上しました。これにより、従来は単色または二色刷りが主流だったパンフレットやポスターも、多色刷りが可能となり、より視覚的な訴求力を持つ印刷物の需要が急増しました。
北九州市では、この技術革新をいち早く取り入れようとする動きが見られました。すでに市内に数多く存在していた印刷業者は、従来の設備に加えてオフセット印刷機を導入することで、大量印刷や精密なカラー印刷に対応できる体制を整えていきました。この設備投資には相応の資金と人材が必要であったものの、時代の変化に柔軟に適応しようとする姿勢が、結果的に地域の印刷事情全体のレベルアップにつながることになります。
とりわけ、カタログや広報誌などの印刷ニーズが高まる中で、オフセット印刷はまさに時代の要請に応える技術でした。これまで文字情報を中心とした紙面構成が多かったものが、写真や図解、グラフなどのビジュアル要素を効果的に取り入れられるようになり、読み手にとってもわかりやすく、親しみのある紙面が増えていきました。地域行政の広報活動や商業施設の販促物などにも、この技術は積極的に活用され、印刷物が果たす役割が一段と広がっていったのです。
さらに、印刷作業のスピードと正確性が飛躍的に向上したことで、短納期かつ高品質な仕上がりを求められる案件にも対応できるようになりました。これは地域企業にとっても大きなメリットとなり、北九州市内で印刷業者と取引を継続する理由の一つにもなっていきました。印刷業者にとっても、業務の幅が広がり、提案型の営業やデザイン業務への参入など、サービスの形を拡張する動きが活発になります。
このような技術革新の中で、印刷現場の働き方にも変化が生まれました。活版印刷時代は一人ひとりの職人技に大きく依存していたのに対し、オフセット印刷では機械操作の精度と全体工程の管理能力がより重要視されるようになります。これにより、業務は個人の技能からチームとしての効率へとシフトし、若い世代の雇用や人材育成にも新たな方向性が生まれていきました。
オフセット印刷の普及は、地域における印刷の価値を再定義する機会にもなりました。単に紙に情報を載せるのではなく、「どのように見せるか」「どう伝えるか」といった視点が求められるようになり、印刷物は“読まれるもの”から“感じられるもの”へと進化します。この変化は、北九州市が地域内外へ向けて情報を発信する際の手段として、印刷物がよりクリエイティブな表現の場となることを意味しました。
地域イベントの案内、文化施設のパンフレット、観光地の紹介冊子など、さまざまな用途に印刷物が用いられる中で、オフセット印刷の強みが最大限に発揮されます。多色で印刷された紙面は見る者の目を引き、印象に残るデザインが可能となり、これまで以上に情報の伝達力が高まりました。視覚的なインパクトが重視される現代において、この時期の技術革新がもたらした変化は、今もそのまま通じる価値を持っています。
また、オフセット印刷の普及によって、印刷物の単価が相対的に下がったことも、重要な変化のひとつです。大量印刷が効率的に行えるため、イベントなどでの配布物やチラシなどを低コストで提供できるようになりました。これは、地域の小規模団体や個人事業主にも印刷サービスの門戸が広がる結果となり、市民生活の中に印刷がより身近な存在として根づく要因ともなっていきました。
このようにして、北九州市の印刷事情は、オフセット印刷という革新的な技術によって新たな段階へと進んでいきました。それは単なる技術導入ではなく、地域社会の中における印刷の意味と価値を問い直し、より良いかたちで活かすための挑戦でもあったのです。時代に合わせた柔軟な変化を通じて、印刷業は再び地域の生活や文化を支える役割を強めていきました。
北九州市の印刷会社が直面したバブル崩壊と経済再編の時代
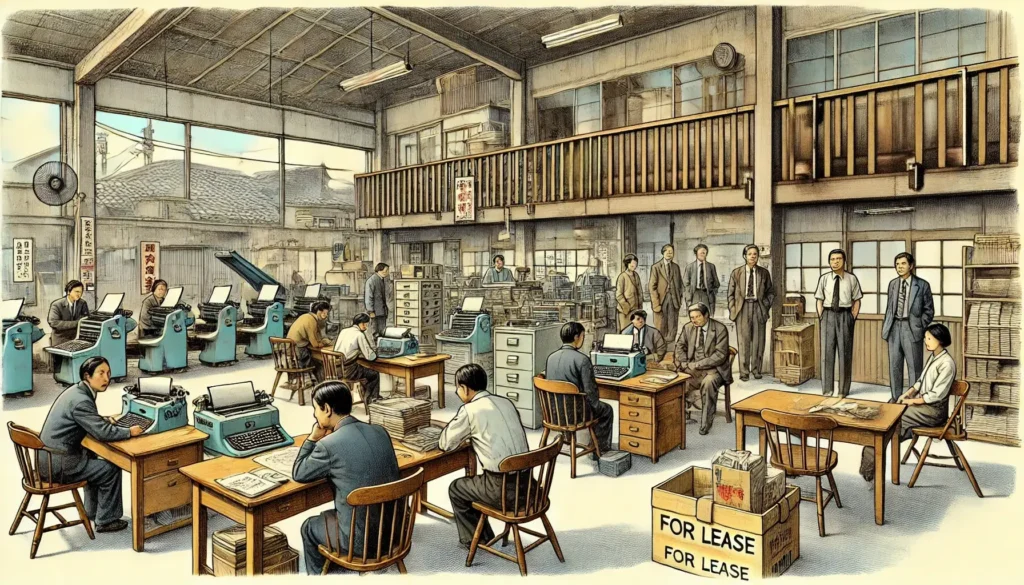
1990年代初頭、日本はバブル経済の崩壊を迎え、全国的に長期の不況に突入しました。高度経済成長期からの好景気に支えられていた多くの産業はこの激変に対応を迫られ、北九州市における印刷業も例外ではありませんでした。それまでの成長に甘んじることなく、変化する経済環境の中で生き残りをかけた再構築の時期が始まったのです。
バブル崩壊の影響は、印刷業界にも複合的に及びました。第一に、広告費の大幅な削減です。バブル期には企業が潤沢な資金を背景に大規模な印刷物を頻繁に発注していましたが、経費削減が求められるようになると、企業広報や販売促進に使われていた冊子やパンフレット、チラシなどの需要が急激に落ち込みました。そのため、従来の商業印刷を主軸に据えていた事業者は、受注減と価格競争の波に直面することになります。
次に、経済再編の波が押し寄せたことで、取引先の業態そのものが変化しました。大手企業の撤退、業種転換、倒産などが相次ぎ、安定した受注先を失った印刷業者は、地元での新たな顧客開拓を急務としました。一方で、新たなニーズとして登場したのが小規模事業者やNPO法人、教育関連施設など、より地域密着型のクライアントです。従来とは異なる柔軟な対応や、低予算での提案力が求められ、印刷業者はこれに応えるために業務の再設計を迫られました。
この時期、特に顕著だったのが「自社の価値を再確認する動き」です。それまでは大量印刷と価格競争が業界の中心でしたが、バブル崩壊以降は少部数・多品種対応や、短納期で高品質を維持する技術力、さらには相談から納品まで一括で任せられる一貫体制への信頼性が評価されるようになりました。価格だけではない選ばれる理由を、各社が模索し始めたのです。
また、印刷業界全体にITの導入が進み始めたのもこの頃です。デジタル入稿やオンデマンド印刷の技術が普及し始め、これまで手作業で行っていた組版や製版の工程が効率化されるようになりました。一方で、そうした新技術を導入するための初期投資や人材育成の負担は大きく、設備更新が追いつかない事業者にとっては淘汰の時代にもなっていきます。技術革新についていけなかった企業は、徐々に市場から姿を消していく厳しい現実に直面しました。
一方で、生き残った事業者の多くは、地域密着を強みに小回りのきくサービスを展開していきました。たとえば、学校や自治体の小規模な印刷ニーズ、町内会の回覧板、地域イベントの簡易なチラシなど、これまで注力されてこなかった分野に目を向け、丁寧な対応やスピード感のある納品を武器に支持を得ていきました。さらに、地域の人々との顔の見える関係性を強めることで、依頼者の意図や思いをくみ取りやすくし、質の高い成果物につなげていったのです。
この時代はまた、印刷業が「提案型の仕事」へと転換していった重要な局面でもありました。依頼されたものを刷るのではなく、どうすれば目的が達成できるかをともに考える姿勢が求められ、営業と制作のあいだにある役割の壁も徐々に薄れていきました。こうして、企画から制作、納品後の活用方法に至るまで包括的に対応する姿勢が根づいていきます。
地域内の印刷所同士でも、競争だけではなく連携の気運が高まりました。大量案件を複数社で分担したり、特色のある技術を持つ事業者と組んで共同提案を行うといった新たな動きが生まれ、こうした協力関係は業界全体の底上げにも貢献しました。困難な時代だったからこそ、共に助け合うという意識が強まり、地域全体での印刷ネットワーク形成につながっていったのです。
バブル崩壊と経済再編は、北九州市の印刷業界にとって厳しい試練の時代でした。しかしこの時期を通じて、「変化に向き合い、自らを更新し続ける力」が養われたことも事実です。価格競争の中でも信頼される理由を磨き、顧客とのつながりを大切にする姿勢を築き上げたことは、後の時代においても業界を支える大きな財産となっています。
デジタル化の波とともに北九州市の印刷事情はどう変化したのか

2000年代に入り、全国の印刷業界に大きな変革をもたらしたのが、急速に進んだデジタル化の波でした。紙を媒体とする情報伝達の役割が見直されるなかで、北九州市の印刷業界も従来のスタイルからの脱却を迫られ、これまでにない試行錯誤と挑戦が続くことになります。この変化は単なる印刷技術の移り変わりにとどまらず、業態全体のあり方、働き方、地域との関係性にまで影響を及ぼしました。
かつて印刷の工程といえば、原稿を紙で受け取り、活字や版を使って組み立て、校正を行い、印刷機で仕上げるという一連の流れが当たり前でした。しかし、パソコンの普及やデザインソフトの一般化により、デジタルデータによる入稿が主流となり、印刷会社側もそれに対応した制作体制を整える必要が出てきました。従来の職人的な感覚に頼る現場から、コンピュータの操作やデータ管理が主軸となる現場へと、日常の業務風景が大きく変わっていったのです。
こうした環境の変化に対して、北九州市の印刷会社の多くは、柔軟に対応しようとする姿勢を見せました。特に、コンパクトな組織体制で動いていた中小規模の印刷所は、変化に素早く適応しやすい面があり、必要な機材やソフトを取り入れて、少しずつ新しい体制を築いていきました。デザイナーとオペレーターの役割が重なるようになり、データ処理から印刷・加工までを一気通貫で担える人材が求められるようになります。
さらに、これまでは一部の顧客に限られていた「オンデマンド印刷」の技術が広がりを見せ、少部数かつ短納期の案件に迅速に対応できるようになったことは、北九州市の印刷事情にも新たな可能性をもたらしました。地域の小規模団体、個人事業主、学校などからの依頼が増え、以前であればコスト面から印刷が難しかった用途にも、気軽に対応できる環境が整っていきました。
また、印刷物そのものの役割も変化を見せ始めました。以前は情報を届ける手段としての役割が中心でしたが、デジタルとの併用が進む中で、印刷物には「質感」や「記憶に残る」ことへの価値が求められるようになります。たとえば、地域の観光パンフレットでは紙質や加工にこだわった表現が重視され、手に取った瞬間に情報が感覚に残るような工夫が施されるようになりました。
この時期、印刷会社の一部では、印刷だけでなく「提案型サービス」や「トータルデザイン」の提供にも乗り出すようになりました。単に紙を刷るのではなく、どのような媒体で、どのように伝えるのが最適なのかを顧客とともに考え、印刷とWeb、動画、SNSなどを組み合わせた「クロスメディア」の考え方が浸透し始めたのです。こうした動きは、地域内の企業や行政、学校とも連携しやすい体制を生み出し、業態の垣根を越えた新しい価値をつくり出す契機となりました。
北九州市という地域においても、印刷物の役割は“伝える”から“つながる”へとシフトしていきます。地域イベントの案内や企業パンフレットなどに加え、地域ブランドを強調した商品パッケージ、リーフレット、学校案内などでは、地域の人や文化、空気感をどう表現するかが問われるようになり、印刷物が果たす役割がより深くなっていきました。
このような中で、デジタル化は敵ではなく、むしろ印刷を進化させるための“共存のパートナー”として意識されるようになります。実際、Webとの連携やSNSとの補完関係を活かすことで、紙媒体に触れる人の数を広げ、より効果的にメッセージを届けることが可能になったという実感を持つ印刷業者も増えていきました。
一方で、すべての事業者がこの変化に対応できたわけではなく、デジタル環境の構築に後れをとったり、新しい機材投資が難しい事業所では、縮小や廃業といった決断を迫られることも少なくありませんでした。厳しい選択の中で、それでも地元に根づいた事業を続けたいという思いから、個人規模に近い形態で事業を継続する例もありました。
このようにして、北九州市の印刷業界は、デジタル化の波に直面しながらも、自らの役割を見つめ直し、対応を重ねながら進化を続けてきました。新しい技術を受け入れるだけではなく、それをどう活かし、地域に根づいたサービスとして形にするかという姿勢が、この街の印刷事情におけるしなやかな持ち味となっているのです。
地域密着型のサービスが北九州市の印刷業に新たな可能性をもたらす理由

北九州市の印刷業界が長く持ちこたえてきた要因のひとつに、「地域密着型のサービス」があります。大都市に比べて派手な成長や話題にはならなくとも、地元に深く根を張り、地域に寄り添った形で継続されてきた印刷業のあり方は、時代の流れの中で逆に大きな強みとして再評価されつつあります。全国的にデジタル化やオンライン化が進むなかで、あえて人と人のつながりを大切にする地場の印刷業が再び注目されているのです。
地域密着の印刷業者が果たしている役割は、単なる“印刷を請け負う”ことにはとどまりません。依頼者の意図や文脈を丁寧に読み取り、それを具体的な形に落とし込むまでの過程には、しばしば直接の対話や現場での細かなやり取りが伴います。こうしたプロセスを大切にするからこそ、結果として満足度の高い成果物が生まれ、それが信頼となって長期的な関係性につながっていきます。
たとえば、地元の学校行事に関する印刷物や、地域で行われるイベント、町内会のお知らせ、商店街のキャンペーンツールなど、他地域では見過ごされがちな小規模案件も、北九州市の印刷業者にとっては日常の中で大切にされる仕事です。こうした案件は利益率で見ると決して高くはないものの、地域とのつながりを維持し、顔の見える関係性を築いていくうえで極めて重要なものとなっています。
また、地元で活動する団体や商店主にとっては、印刷に関する専門知識を持って相談できる相手がすぐ近くにいるということが、大きな安心材料となります。オンラインの注文サイトでは得られない、ちょっとしたニュアンスの確認や、印刷物の持つ“温度感”に関する調整ができるのは、やはり地域密着型の強みです。地元の事をよく知る相手とやり取りをすることで、「これなら伝わる」「これなら手に取りたくなる」といった実感を持てる仕上がりが実現できるのです。
さらに、こうした地域に根ざした事業者同士のつながりは、新たな展開を生み出すことにもつながります。たとえば、地域の農家やクラフト作家と協力してオリジナルパッケージを作成したり、地元で開催されるマルシェや文化祭で、販促物を通じたプロモーション支援を行うといった事例も増えてきました。こうした取り組みは、印刷の役割を単なる「製造業」から「地域ブランドの共創者」へと進化させる契機となっています。
近年では、行政や地域団体との協働も活発化してきました。市民参加型のまちづくりイベント、地域の魅力を発信する観光冊子、子育て支援や高齢者福祉に関するガイドなど、さまざまな分野で印刷物が果たす役割が再認識されています。こうした印刷物は、デザイン性だけでなく、配布場所や想定される読者に対する理解が求められるため、地元の状況に精通している業者にしかできない仕事でもあります。
また、近年の感染症拡大など社会的な変化を受けて、地域のコミュニケーションの形も変化しています。その中で、ポスターやチラシ、リーフレットといった紙媒体は、改めて「人の目に自然に届く」存在としての価値を見直されています。オンラインに偏りがちな情報提供では届きにくい層への配慮や、日常生活にふと入り込む形での告知手段として、紙の印刷物が再評価されているのです。
こうした変化のなかで、北九州市の印刷業者は小さな声を丁寧にすくい上げ、かたちにして届ける仕事に再びやりがいと可能性を見出しています。大量に刷ることよりも、どれだけ丁寧に伝えられるか。誰に、どのように届くかを重視したきめ細かなサービスが、地域密着の姿勢を支え、さらにそれが支持される理由となっています。
さらに、この地域においては印刷会社がまちづくりの一員として位置づけられることも珍しくありません。地元の課題や魅力を発信するツールづくりに関わることで、印刷という仕事が単なるアウトプットではなく、地域のアイデンティティを表現する手段へと昇華しているのです。ここに、地域密着の本質的な価値があります。
つまり、地域密着型の印刷サービスとは、印刷という技術を通じて人と人をつなぎ、情報や想いを形にすることで地域社会の一部として機能するということです。これは大規模なシステムや全国チェーンでは到底真似のできない領域であり、北九州市の印刷業がこれからも地域に必要とされ続けるであろう強力な理由となっています。
環境配慮やサステナビリティを意識した北九州市の印刷業の新たな試み
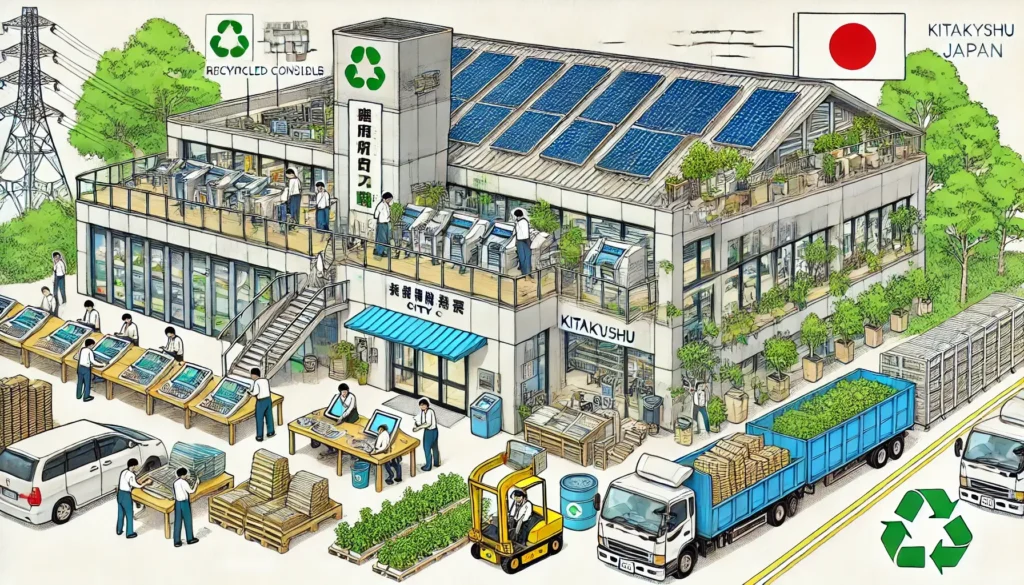
近年、世界的に広がりを見せるサステナビリティや環境への配慮といった価値観は、北九州市の印刷業界においても無視できない課題となりつつあります。従来の印刷業といえば、大量の紙資源、インク、電力を使用し、時には廃棄物も多く出るというイメージがありました。しかし、こうした業界特有の構造に向き合い、地元でできる環境配慮の在り方を模索する動きが静かに、しかし着実に広がってきています。
北九州市はもともと公害克服のまちとして知られており、行政と市民、企業が一体となって持続可能な都市づくりを進めてきた背景があります。そうした土壌の中で育ってきた印刷業者たちは、自社の業務が与える環境負荷について敏感に意識する傾向が強く、資源循環やエネルギー効率の向上を意識した取り組みに積極的です。
たとえば、再生紙の使用はそのひとつです。クライアントの希望に応じて再生率の高い用紙を選定するだけでなく、あらかじめ環境配慮型の素材を標準仕様として提示する印刷所も増えつつあります。紙の質感や発色などが気になるケースでも、実物サンプルを見せながら選択肢を提供することで、機能と環境のバランスを両立させる工夫がなされています。
廃材の管理も重要なテーマです。印刷業ではどうしても余紙や損紙といった廃棄物が発生しますが、それを単に処分するのではなく、リユースやアップサイクルに活用する動きも出てきています。たとえば、不要になった紙をノートやメモ帳として再加工したりと、こうした活動はコスト削減にもつながるうえ、地域との関係性を深める好機にもなっています。
さらに、近年では印刷工程全体のエネルギー消費を抑えるための設備投資も進んでいます。最新の印刷機器は、従来よりも消費電力が少なく、稼働音も小さいため、作業環境そのものの質も向上します。また、デジタル印刷技術の活用により、必要な分だけを無駄なく印刷する「オンデマンド型」の運用が進み、過剰在庫や廃棄ロスを抑える設計が自然と根づいてきています。
このような環境配慮の取り組みは、印刷所の内側だけで完結するものではありません。クライアントとの協働によって、紙の使用量を見直したレイアウト提案や、印刷せずに電子書籍(デジタルブック)での配布に切り替える相談を行うこともあり、単に請け負うのではなく、提案する側としての姿勢が評価されるようにもなってきました。持続可能な選択肢を示すことで、依頼者にとっても社会的意義のある取り組みに関わっているという実感が得られ、それが新たな信頼関係へとつながっていきます。
加えて、印刷物そのものにもサステナビリティの視点を織り込む動きが広がっています。地域イベントの案内チラシにエコ素材の情報を記載したり、学校や企業向けの冊子にリサイクル推進のアイコンを掲載したりすることで、読み手にも環境意識を促す設計がなされています。印刷物が「情報を届ける手段」から「意識を育てる媒体」へと役割を拡張している証しでもあります。
北九州市の印刷業界におけるこうした取り組みは、必ずしも大きな投資や革新的な技術に依存しているわけではありません。むしろ、地域に根ざした事業者だからこそ可能な、小さな改善や、日々の業務の中で積み上げる工夫が中心です。その積み重ねが、印刷業という業種の未来を支える土台となりつつあり、地域から社会全体に向けて、環境と共に生きる姿勢を静かに発信しているのです。
これからの北九州市の印刷事情は地域と共にどのように歩んでいくのか

100年という長い時間をかけて築かれてきた北九州市の印刷業は、過去を振り返るだけでなく、これからの歩みをどう描いていくかという点でも注目されています。これまでの歴史の中で培ってきた地域とのつながり、技術の継承、柔軟な対応力は、急速に変化する社会の中においても大切にされる要素であり、それを軸に今後も持続的に発展していくための土台となります。
これからの印刷業は、単に紙に情報を載せるという機能にとどまらず、情報を「どう見せるか」「どう伝えるか」という役割がより強く求められるようになります。これは、印刷がビジュアル・ストーリーテリングの手段のひとつとして再認識されているという変化でもあります。特に、地域における文化や風土、人々の営みを伝える手段として、印刷物は紙という形をとりながらも“心を伝える媒体”として機能していくことが期待されているのです。
北九州市では、少子高齢化や人口減少といった課題にも直面していますが、こうした社会的変化のなかでこそ、印刷業の役割が改めて見直されています。たとえば、高齢者に向けた行政のお知らせや、子育て世代向けの案内冊子、観光客向けのマップなど、誰もが必要な情報にアクセスできるようにするためには、デジタルだけではなく紙による伝達が重要であるという認識が広がっています。
こうした中で、北九州市の印刷業は“情報格差を埋める”存在としての価値を持ち続けています。特にスマートフォンやパソコンを使いこなすのが難しい世代に対して、目に見える形で届けられる情報は、そのまま安心感につながり、地域での生活を支える大きな要素になります。印刷物には、単に情報を伝えるだけでなく「信頼されるツール」としての強みがあるのです。
また、地域の課題や魅力を発信するための手段として、印刷物を活用したプロジェクトも徐々に増えてきています。地元の農産品や工芸品を紹介するパンフレット、地域史をまとめた冊子、小学校や中学校と連携した郷土学習の教材など、地域を知り、次世代に伝えていくための活動に印刷が関わる場面が広がりを見せています。こうした取り組みは、印刷業が“まちづくりの一翼”を担っていることの証でもあります。
未来に向けた動きのなかで、注目されているのがデジタルとアナログの融合です。印刷物にQR画像を埋め込んだり、AR(拡張現実)と連携させることで、紙の世界とデジタルの世界を行き来できるような体験設計が実現されています。このようにして、紙というメディアが新しい可能性を内包した媒体として生まれ変わりつつあるのです。
また、環境への配慮も、これからの印刷業にとって避けて通れないテーマです。持続可能な素材の選定、省エネルギー化された機械の導入、無駄を減らす生産体制の構築など、すでに多くの印刷会社が実践している小さな取り組みの積み重ねが、今後も継続されていくでしょう。それらが、印刷業の価値そのものを高め、地域社会における存在感をさらに強めていくと考えられます。
そして何より、地域の人々とのつながりを大切にし続ける姿勢が、北九州市の印刷業を支え続けています。対面での打ち合わせ、細やかなやり取り、相手の背景を汲み取った提案など、機械では代替できない人の力が介在するからこそ、印刷という仕事は“信頼される仕事”であり続けるのです。こうした人間的なつながりのなかでこそ、創造的なアイデアや、地域ならではの価値が生まれていくのではないでしょうか。
100年の歴史は、ただ長く続いたという記録ではなく、常に変化に向き合い、地域と共に歩みながらその存在を更新してきた軌跡です。その歩みを止めることなく、これからの北九州市の印刷業は、新たな社会のニーズやテクノロジーと向き合いながら、地域に根ざした形で発展していくことが求められています。変化の先にこそ、次の100年へとつながる道がある。その一歩一歩を、地域とともに踏み出していく姿勢こそが、これからの印刷業にとって最も大切な姿ではないでしょうか。
まとめ
北九州市における印刷業の歩みは、単なる紙媒体の進化を超え、地域と共に成長してきた文化と産業の記録そのものです。大正期に端を発したこの地域の印刷事情は、時代ごとの社会背景や技術革新と密接に関わりながら、多様な役割を果たしてきました。
昭和初期には、港町としての役割と教育文化の高まりが印刷業の基盤を形成し、戦中戦後の混乱期には限られた資源の中でも地域の情報インフラを支える存在として機能し続けました。高度経済成長期には大手企業との連携を強め、大量印刷と高精度な仕上がりを両立させながら、行政や教育機関とも密に連動する体制を整えました。
その後も、オフセット印刷の導入により表現の幅を広げ、バブル崩壊後の経済再編では地域に密着した少ロット・短納期・高付加価値のサービスへと舵を切ることで、厳しい状況下でも信頼をつないできました。さらに、デジタル化が進む中では、紙とデジタルの両方の特性を生かしたハイブリッドなサービス提供へと進化し、印刷の意味そのものを拡張していきました。
とりわけ、北九州市の印刷業が際立っているのは、地域密着型の姿勢と、人と人とのつながりを重視した柔らかな対応力です。地域イベント、教育現場、福祉施設、行政業務、さらには地域ブランドや観光資源の魅力を伝える役割など、生活のあらゆる場面に印刷物は浸透しており、それらを支えてきたのが地元の印刷事業者たちです。
近年では環境意識も高まり、再生紙や環境対応インク、省エネ機器の導入など、持続可能な取り組みも定着しつつあります。こうした姿勢は、印刷物をつくる工程そのものが社会への責任を果たす手段として認識され始めた証です。
そして今、印刷は単に“伝える手段”ではなく、“共に地域をつくる道具”として新たな意義を持ちはじめています。紙という物理的なかたちであるがゆえに、人の記憶に残り、手元に届き、暮らしの中に深く入り込む力を持つ。その可能性を地域の中で育て続けることこそが、北九州市の印刷業がこれからも歩み続ける理由となるはずです。
株式会社ヤマガ
代表取締役 山賀 克芳
よくある質問Q&A
-
北九州市で印刷業が発展したきっかけは何ですか?
-
北九州市で印刷業が発展した背景には、大正期の港湾機能の充実や産業の集積がありました。情報伝達の手段として紙媒体の重要性が高まり、教育機関や行政からの需要が地域内で急増しました。新聞や帳票、商業広告の印刷を支えるため、印刷所が次々と設立され、徐々に地域社会に欠かせない存在となっていきました。
-
昭和初期の北九州市の印刷事情にはどのような特徴がありましたか?
-
昭和初期の印刷業は手作業による活版印刷が主流で、職人技が重視されていました。地域の学校や行政、商店街などとのつながりも深く、教材や告知物、ポスターなど生活に密着した印刷物が多く製作されていました。印刷所は地域の“情報の橋渡し役”として、人々の暮らしを支えていたのが特徴です。
-
戦中戦後の混乱期に印刷業はどのように対応しましたか?
-
戦中は資材不足や統制経済の影響で、印刷業も大きな制限を受けましたが、必要最低限の情報を伝えるために縮小しながらも継続されました。終戦後は地域の再建を支えるため、自治体の広報や教育資料の印刷を担い、限られた資源と人材で復興に貢献しました。地域のネットワークが再建の力となった時期でもあります。
-
高度経済成長期にはどのような変化がありましたか?
-
高度経済成長期には、企業の需要が増大し、印刷業はオフセット印刷の導入など技術革新を取り入れて大きく拡大しました。地域の製造業や小売業、自治体との連携も強まり、大量生産と短納期に対応する体制が整備されました。この時期に一貫生産体制を確立する印刷所も増え、業界全体の地位が向上しました。
-
オフセット印刷の導入が印刷業に与えた影響とは?
-
オフセット印刷の導入により、多色刷りや写真印刷が容易になり、ビジュアル表現の幅が広がりました。大量印刷も効率的に行えるようになり、広告やカタログ、ポスターなどの質とスピードが大幅に向上しました。この技術革新により、印刷業はよりクリエイティブな分野へと進出する契機となりました。
-
バブル崩壊後、印刷業はどのように再編されましたか?
-
バブル崩壊後、多くの企業が広告費を削減し、印刷需要は大幅に減少しました。そのため、印刷業者は小ロット・短納期への対応や、地域密着型のサービスへとシフトしました。顧客との対話を重視し、提案型の営業や低予算対応が求められるようになり、信頼と柔軟性が生き残りの条件となっていきました。
-
デジタル化の進展により、どのような変化がありましたか?
-
デジタル化により、パソコンからのデータ入稿が主流となり、印刷所は制作体制の見直しを迫られました。オンデマンド印刷の普及で少部数の印刷も効率的に行えるようになり、個人事業主や地域団体の需要が拡大しました。印刷業者はデザインや企画提案を含む新たな業務領域に挑戦するようになります。
-
印刷物とデジタルメディアの違いは何ですか?
-
デジタルメディアは即時性や検索性に優れていますが、印刷物は手に取ったときの質感や記憶への残りやすさ、信頼感において強みがあります。特に高齢者やIT機器に不慣れな層にとっては、紙の印刷物のほうが安心感を与えやすく、公共情報や福祉案内などでは今も重宝されています。
-
地域密着型の印刷業が重視されている理由は何ですか?
-
地域密着型の印刷業は、依頼者の意図や背景を丁寧にくみ取り、対話を通じて柔軟に対応できる点が評価されています。顔の見える関係性が信頼につながり、地域イベントや小規模な業務にも丁寧に対応できるため、住民や団体との連携が自然と生まれます。地元とのつながりが価値を生む仕事なのです。
-
環境配慮において印刷業はどのような取り組みをしていますか?
-
再生紙や環境対応インクの使用、省エネ機器の導入、廃紙のリサイクルなど、印刷業は多方面で環境への配慮を進めています。さらに、紙の無駄を減らすレイアウト提案やオンデマンド印刷によるロス削減など、日常業務の中で持続可能性を意識した選択が増えています。小さな工夫の積み重ねが今後を支えます。
-
北九州市の印刷業にはどのような強みがありますか?
-
北九州市の印刷業の強みは、地域との深いつながり、時代に応じた技術導入、そして長年にわたって蓄積された信頼にあります。100年以上続く事業者も多く、地元の文化や事情を理解した対応が可能です。変化に適応しながらも、地域とともに歩んできた歴史がそのまま価値となっています。
-
地域の情報格差に印刷業はどのように貢献していますか?
-
デジタルにアクセスしづらい高齢者に対し、紙の印刷物はわかりやすく、必要な情報を確実に届ける手段として有効です。北九州市では、自治体のお知らせや福祉情報などを印刷で届ける取り組みが継続されており、地域の暮らしを支える情報インフラとしての役割を果たしています。
-
紙媒体の印刷物は今も必要とされていますか?
-
はい。デジタルが主流の現代においても、紙媒体は「目に触れやすく記憶に残る」という特性から、今なお多くの場面で活用されています。特に地域イベントや観光案内、学校・行政関連の資料などでは、手渡しの安心感や保存性が重視されており、紙の印刷物はその価値を保ち続けています。
-
印刷業者が地域社会と連携する具体的な例はありますか?
-
地域の農産品のパッケージ制作、学校との郷土学習教材の開発、イベントポスターのデザインなど、多くの場面で印刷業者が地元と協働しています。単なる請負ではなく、情報や魅力の発信に一緒に関わることで、地域づくりの一端を担う存在として活動しています。
-
印刷業はこれからどのような方向に進むと考えられますか?
-
印刷業は、単なる製造業から“表現の場”へと役割を広げつつあります。地域の価値を発信するツールとして、紙とデジタルを組み合わせたクロスメディア展開、環境意識との両立、そして一人ひとりに届く丁寧な提案がより求められていくでしょう。今後も地域とともに歩む姿勢が核となります。
-
印刷業で働く人にはどのような力が求められていますか?
-
技術力に加えて、顧客との対話力や提案力、さらには地域性への理解が求められます。印刷の仕事は単なる作業ではなく、依頼者の目的や思いを形にするプロセスそのものであり、柔軟に考え、共感しながら動ける人材が重宝されています。
-
地域ブランド構築に印刷業はどう関わっていますか?
-
印刷物は、視覚的な印象を通して地域の魅力を伝える力を持っています。ロゴ、パッケージ、パンフレット、観光マップなどを通して、地域の個性や価値観を表現する役割を担っており、ブランドイメージの統一や発信を支える存在となっています。
-
北九州市の印刷業が今後力を入れるべき分野は何ですか?
-
今後は、教育・福祉・観光といった地域に密着した分野での需要がさらに高まると予想されます。特に“情報をわかりやすく伝える”という基本を守りながら、デザインや編集、Web連携などの提案力を強化することが求められています。
-
地元住民・企業が印刷業に求めていることは何ですか?
-
地元住民・企業は、自分たちの声をしっかり聞いてくれる存在を求めています。急な対応、細かな注文、内容の確認など、柔軟で親身な対応が信頼につながります。また、地域の文化や状況を理解してくれる印刷業者は、情報発信のパートナーとして非常に重宝されています。
-
印刷業は地域にどんな価値を提供できるのでしょうか?
-
印刷業は、情報をかたちにすることで、人と人、地域と人をつなぐ力を持っています。暮らしに必要な情報の提供、地域の魅力の発信、記録や思い出の保存といった役割を通じて、地域社会の中でなくてはならない存在として価値を発揮し続けています。







